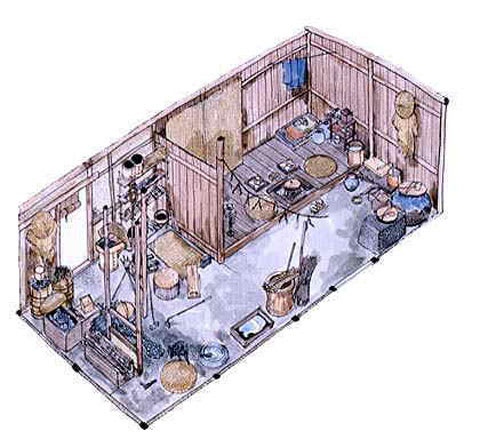以下は、HPに掲載した文章です。
東日本大震災から1年
並々ならない1年だったと思います。
多くの生命が失われ、人々の基本資産である住宅が毀損した昨年の震災発生以来
住宅雑誌Replanは、東北全域を対象とした住宅雑誌という立場から、
自分たちにも何ごとか、
この事態に役に立つことがあるのではないかと模索してきました。
そんな思いの中から、
「東北の住まい再生」というフリーマガジンを発行。
岩手・宮城・福島・山形の各県から「後援」をいただき、
仮設住宅から復興住宅への道筋が少しでもよい家づくりになることを祈りながら、
多くの皆さんに住宅の情報をお届けしてきました。
その活動を通して、実にたくさんの方々の思いにも触れてきました。
読者の皆さん、情報を提供していただだいた皆さん、
それぞれの立場から寄せられた真実の言葉をお伝えしていきたいと、
日々、住宅雑誌として努めています。
時間は、あの日から途切れることなく継続しています。
失われてしまったかけがえのない暮らしが、
災害に負けることなく再生していくよう願いを込めて、
これからも出版の仕事に邁進していきたいと考えています。
きっと多くのみなさんが同じような思いを抱きながら
それぞれに過ごしてきたと思います。
それぞれのフィールドで、できることを少しでもしたい、
そういうことを念願してきたと思います。
できることは限られています。
必ずしもうまくいくとも限りません。
そして、1年というのはひとつの区切りではあるけれど、
なによりも継続の力が大切なのだと思います。
震災後、東北に行けるようになるまでにジリジリとしながら過ごした
1カ月を要した日々。
なにかできることをしたい、
その思いがひとつの形をとって行動できるようになって、
そこからずっと、ひとつながりの時間の中にいるように思います。
札幌からは飛行機もなく、
ようやく石油の確保も可能になってきた状況を見て
車を駆ってフェリーに乗って、八戸の代替港・青森埠頭に着き、
暗い中を、ときおり大きな段差が残る東北道を南下し続け、
ようやく取れた宿泊先・古川のホテルで街の状況を見ていました。
最大震度7に近い揺れだった宮城県北部です。
そういうときにも余震は続いていた。
東北における建築知識の最大の拠点とも思われる
東北大学工学部のビルが
「使用不能」になっている惨状。
岩手県や宮城県の沿岸部の息をのむような状況。
さらに福島には近づくことも出来なかった・・・。
出会った多くのみなさんの元気な表情が救いだった。
宮古から北部三陸海岸を北上していった帰路の道筋。
そんな日々が思い起こされます。
これから、息の長い道のりがずっと続いていくと思います。
自分になにが出来るのか、
そういう自問自答を続けながら、関わり続けていきたいと思います。
犠牲になられたみなさんに、合掌。