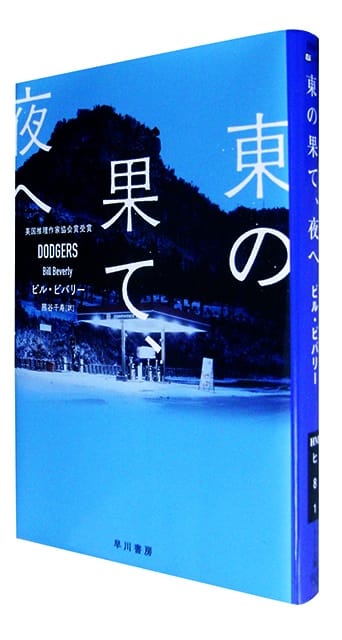ユベール・マンガレリ『しずかに流れるみどりの川』

父と息子の物語。
息子はまだ小さいのに、母の影がない。
父は仕事がうまくいかない。
そして貧しい。
父はたっぷりの愛情を息子に注ぎ、息子もそのことを理解している。
とても薄い本だけど、頭の中で膨らんで、その何倍もの厚みの本を読んでいるかのよう。
息子になり、父になり。
表紙に描かれた緑の濃淡は、底の見えない物語の深みに誘う危ない色。
少し怖く、忘れられない。
装丁は後藤葉子氏。装画はクサナギシンペイ氏。(2015)


父と息子の物語。
息子はまだ小さいのに、母の影がない。
父は仕事がうまくいかない。
そして貧しい。
父はたっぷりの愛情を息子に注ぎ、息子もそのことを理解している。
とても薄い本だけど、頭の中で膨らんで、その何倍もの厚みの本を読んでいるかのよう。
息子になり、父になり。
表紙に描かれた緑の濃淡は、底の見えない物語の深みに誘う危ない色。
少し怖く、忘れられない。
装丁は後藤葉子氏。装画はクサナギシンペイ氏。(2015)