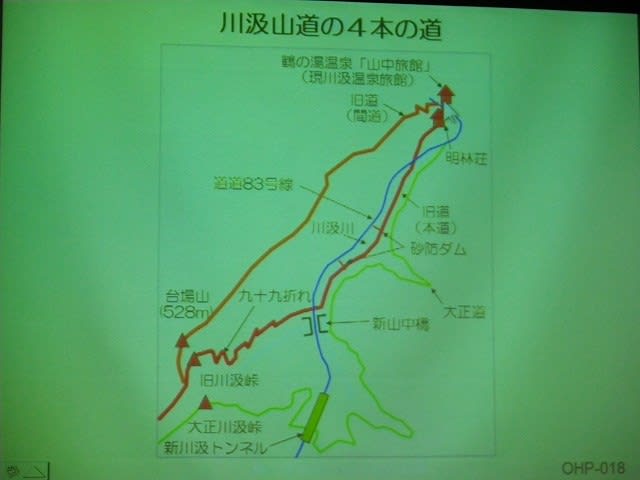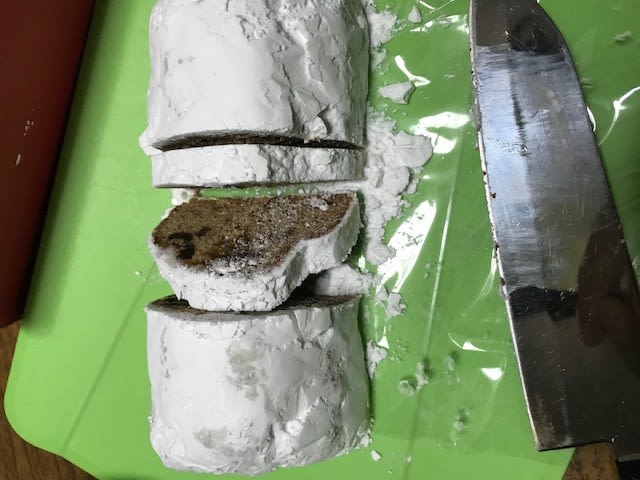花束を受け取るMAEちゃん
昨夜は、函館トライアスロンクラブ事務局長MAEちゃんの還暦祝いが、本町のイタリアンレストラン・クリエイティブ ディッシュ ゴエンで開催された。わざわざ、このために東京や札幌から参加された仲間もいた。
MAEちゃんは、自らもトップトライアスリートとしてみんなを引っ張っているほかに、マメな会報の発行、週末練習会や各種行事の企画・運営、公式ホームページの管理などを率先して取り組んでくれている。
年々若い会員も増え、今や海外の大会でも活躍する選手など80名もの会員を抱える道内トップのクラブへと発展してきたのは、ひとえにMAEちゃんの人柄と努力の賜物である。
自分はトライアスロンはやらないが、マラソンとXCスキーを通してのお付き合いである。MAEちゃんとの出会いは22年前になる。自分が52歳、MAEちゃんが38歳とお互いに若かった。
MAEちゃんは当時から函館トライアスロンクラブの事務局長をされていたが、トライアスロンの自転車の練習が冬にはできないので、その代わりにクラブとしてXCスキーに取り組んでいた。自分も個人的にXCスキーをやっていたので仲間に入れてもらったことが、このクラブとの出会いである。
その後、トライアスロンクラブが母体となって、XCスキークラブ「函館クロカンキッズ」が発足し、自分が会長を仰せつかり、事務局長をMAEさんが務めてくれた。しかし、会員減に伴い、数年前に解散して函館トライアスロンクラブに合流し、「函トラXC部」として活動を続けている。
自分がマラソンも取り組むようになったのも、このクラブのお陰である。常にステップアップを続けるこの仲間からは、いろいろ多くの刺激をいただいて、自分もアクティブな人生を送れている。ちなみに、会長のTaさんは79歳で、自分は年齢的にはその次である。

お祝いのアイアンマンのマフラーを首に下げる

お祝いの品(花束、アイアンマンのマフラー、サングラス)を身に付けてカメラに収まるMAEちゃん

料理の一部


談笑する会員のみなさん

最後にお祝いのケーキが用意される

奥さまからMAEちゃんへのア~ン。この後、切り分けられて全員に配られた

外へ出ての集合写真。このあとほかのメンバーは2次会へ流れたが、自分は失礼して家路へ就いた。