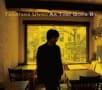『ザ・ハーダー・ゼイ・フォール:報復の荒野』(2021.12.5.Netflix)
荒くれ者のナット・ラヴ(ジョナサン・メジャース)は、20年前に両親を殺害した、ルーファス・バック(イドリス・エルバ)が釈放されることを知り、復讐を誓う。
だが、街に戻ったルーファスは、トルーディス・スミス(レジーナ・キング)、チェロキー・ビル(ラキース・スタンフィールド)をはじめとする、つわものたちを集めて街を牛耳る。
ナットもかつてのギャング仲間たちに声を掛け、元恋人のステージコーチ・メアリー(ザジー・ビーツ)、腹心のビル(エディ・ガテギ)、早撃ち自慢のジム(RJ・サイラー)、用心棒のカフィー(ダニエル・デッドワイラー)、保安官の(デルロイ・リンド)がナットのもとに集まる。そして、両者の対決の時がやってくる。
ヒップホップのジェイ・Z がプロデュースし、ジェームズ・サミュエルが監督した“ブラック・ウエスタン”。味わいとしては、マカロニウエスタンやそれに影響を受けたクエンティン・タランティーノの諸作や『マグニフィセント・セブン』(16)、あるいは『黒いジャガー』(71)に代表されるブラック・パワー・ムービーをほうふつとさせるところもある。
独特の音楽や色遣いなどを見ていると、今までにないポップな西部劇という感じもした。特にエルバとキングの怪演が目立った。ただし、西部劇としてはテンポや間が悪いのは否めない。特に前半はだらだらしていて睡魔に襲われた。
ところで、「ザ・ハーダー・ゼイ・フォール」というタイトル、どこかで見たことがあると思ったら、ハンフリー・ボガートの遺作で、ボクシングの八百長を描いた『殴られる男』(56)の原題と同じだった。
気になって、意味を調べてみたら、これは英語のことわざで「大物は激しく倒れる」。つまり「強大な権力を持った者が失敗したときは、激しい敗北を味わうことになる」という意味になるらしい。この映画の場合は、ルーファスのことを指すのだろう。
『殴られる男』
https://blog.goo.ne.jp/tanar61/e/2f39c0f3d4456a424bee2ccc1af229e7