20日(月).今夜7時15分から,すみだトリフォニー・ホールでダニエル・ハーディング指揮新日本フィルによるマーラー「交響曲第5番」のコンサートがあります 3.11東日本大震災チャリティー・コンサートと位置付けられています.
3.11東日本大震災チャリティー・コンサートと位置付けられています.
3月11日の午後,ハーディングは新日本フィルとのマーラー第5交響曲のゲネプロへ向かうために,都内を移動中でした.その途中で大地震に遭遇しました.当日午後7時15分からのコンサートには1801席ある大ホールのうち席を埋めたのはたったの105人でした.オーケストラとほぼ同じ人数といってもよいでしょう.それでもマーラーを演奏しました.私は翌12日のコンサート(同じプログラム)を聴く予定でしたが,それが叶いませんでした 最終的に彼は16日に日本を離れましたが,最後までコンサートの再開に向けて試行錯誤していたようです.
最終的に彼は16日に日本を離れましたが,最後までコンサートの再開に向けて試行錯誤していたようです.
3月12日の代替公演は明日(21日)開催されるので聴きに行きます それに先立つ本日(20日),ハーディングの強い希望により同じマーラー「第5交響曲」によるチャリティー演奏会が挙行されます.ハーディングは次のようなメッセージを寄せています.
それに先立つ本日(20日),ハーディングの強い希望により同じマーラー「第5交響曲」によるチャリティー演奏会が挙行されます.ハーディングは次のようなメッセージを寄せています.
「このチャリティー演奏会においてマーラー第5番を演奏 できることは私にとってこれ以上ないことです.この作品は,愛,悲劇,生命と死を描いた壮大な物語です.この交響曲を指揮することは私にとっていつも特別ですが,特に今回は,震災で亡くなられた方々,愛する人を失った方々,住む場所や生きる力を失った全ての方々に前身全霊を込めて捧げたいと思います
できることは私にとってこれ以上ないことです.この作品は,愛,悲劇,生命と死を描いた壮大な物語です.この交響曲を指揮することは私にとっていつも特別ですが,特に今回は,震災で亡くなられた方々,愛する人を失った方々,住む場所や生きる力を失った全ての方々に前身全霊を込めて捧げたいと思います 」
」
今夜の公演はUSTREAMで生中継されます.会場に行けない人はパソコン画面でご覧になってはいかがでしょうか アドレスは以下のとおりです.(新日本フィルのホームページからもアクセス可能です)
アドレスは以下のとおりです.(新日本フィルのホームページからもアクセス可能です)
http://www.ustream.tv/channel/harding-njpcharityconcert

 3.11東日本大震災チャリティー・コンサートと位置付けられています.
3.11東日本大震災チャリティー・コンサートと位置付けられています.3月11日の午後,ハーディングは新日本フィルとのマーラー第5交響曲のゲネプロへ向かうために,都内を移動中でした.その途中で大地震に遭遇しました.当日午後7時15分からのコンサートには1801席ある大ホールのうち席を埋めたのはたったの105人でした.オーケストラとほぼ同じ人数といってもよいでしょう.それでもマーラーを演奏しました.私は翌12日のコンサート(同じプログラム)を聴く予定でしたが,それが叶いませんでした
 最終的に彼は16日に日本を離れましたが,最後までコンサートの再開に向けて試行錯誤していたようです.
最終的に彼は16日に日本を離れましたが,最後までコンサートの再開に向けて試行錯誤していたようです.3月12日の代替公演は明日(21日)開催されるので聴きに行きます
 それに先立つ本日(20日),ハーディングの強い希望により同じマーラー「第5交響曲」によるチャリティー演奏会が挙行されます.ハーディングは次のようなメッセージを寄せています.
それに先立つ本日(20日),ハーディングの強い希望により同じマーラー「第5交響曲」によるチャリティー演奏会が挙行されます.ハーディングは次のようなメッセージを寄せています.「このチャリティー演奏会においてマーラー第5番を演奏
 できることは私にとってこれ以上ないことです.この作品は,愛,悲劇,生命と死を描いた壮大な物語です.この交響曲を指揮することは私にとっていつも特別ですが,特に今回は,震災で亡くなられた方々,愛する人を失った方々,住む場所や生きる力を失った全ての方々に前身全霊を込めて捧げたいと思います
できることは私にとってこれ以上ないことです.この作品は,愛,悲劇,生命と死を描いた壮大な物語です.この交響曲を指揮することは私にとっていつも特別ですが,特に今回は,震災で亡くなられた方々,愛する人を失った方々,住む場所や生きる力を失った全ての方々に前身全霊を込めて捧げたいと思います 」
」今夜の公演はUSTREAMで生中継されます.会場に行けない人はパソコン画面でご覧になってはいかがでしょうか
 アドレスは以下のとおりです.(新日本フィルのホームページからもアクセス可能です)
アドレスは以下のとおりです.(新日本フィルのホームページからもアクセス可能です)http://www.ustream.tv/channel/harding-njpcharityconcert
















 です.
です.
 ルチアが彼女に乗り移ったかのような狂気に満ちた迫真の演技,素晴らしい歌唱です.観客はただシーンとして彼女の姿を追い,その声に耳を傾けるばかりです.”狂乱の場”が終わって照明が落ちた後もしばらく
ルチアが彼女に乗り移ったかのような狂気に満ちた迫真の演技,素晴らしい歌唱です.観客はただシーンとして彼女の姿を追い,その声に耳を傾けるばかりです.”狂乱の場”が終わって照明が落ちた後もしばらく が鳴り止みませんでした.すごいとしか言いようがありません
が鳴り止みませんでした.すごいとしか言いようがありません
 最後に一発逆転でした
最後に一発逆転でした


 に行ったので帰宅が深夜になってしまいました.今日は午前中マンション管理組合の定時総会に出席して,午後,錦糸町のすみだトリフォニー・ホールに出かけました.夕べの疲れが残っていて辛いもの
に行ったので帰宅が深夜になってしまいました.今日は午前中マンション管理組合の定時総会に出席して,午後,錦糸町のすみだトリフォニー・ホールに出かけました.夕べの疲れが残っていて辛いもの がありましたが,今日の新日本フィルの第478回定期演奏会の指揮者は1975年生まれのイギリス出身のダニエル・ハーディング,演奏するのはブルックナーの「交響曲第8番ハ短調」という大曲
がありましたが,今日の新日本フィルの第478回定期演奏会の指揮者は1975年生まれのイギリス出身のダニエル・ハーディング,演奏するのはブルックナーの「交響曲第8番ハ短調」という大曲 たまりませんでした.なかなか音楽に集中できず,頭の中が朦朧としていました.コンサート・マスターはあの葉加瀬太郎似の崔文珠.きょうは椅子の高さがいつもよりは低いようです.いつもは中腰スタイルです.第2楽章「スケルツォ」からだんだん目が覚めてきて意識を集中して聴くようになりました.何といってもこの曲の白眉は第3楽章「アダージョ」でしょう.「荘重にゆっくりと,しかしひきずらないように」と題されたこの楽章をハーディングは丁寧にメロディーを歌わせていきます
たまりませんでした.なかなか音楽に集中できず,頭の中が朦朧としていました.コンサート・マスターはあの葉加瀬太郎似の崔文珠.きょうは椅子の高さがいつもよりは低いようです.いつもは中腰スタイルです.第2楽章「スケルツォ」からだんだん目が覚めてきて意識を集中して聴くようになりました.何といってもこの曲の白眉は第3楽章「アダージョ」でしょう.「荘重にゆっくりと,しかしひきずらないように」と題されたこの楽章をハーディングは丁寧にメロディーを歌わせていきます
 それにしても,演奏中に落ち着きなく頭を動かしたりするのはやめてほしいと思います.音楽を聴くことにおいてはプロのはず.どんなにりっぱな演奏評を書いても,聴くマナーが悪くては信用できませんね
それにしても,演奏中に落ち着きなく頭を動かしたりするのはやめてほしいと思います.音楽を聴くことにおいてはプロのはず.どんなにりっぱな演奏評を書いても,聴くマナーが悪くては信用できませんね
 を持って再度登場し,男性の第1バイオリン奏者に手渡しました.彼は花束を手に楽団員の拍手を受けていました.年のころ「アラ還」のようなので,今日の演奏会を最後にこのオーケストラを定年退職するのでしょう.去って行く者をみんなで温かく見送る・・・家族的でいいなぁと思います
を持って再度登場し,男性の第1バイオリン奏者に手渡しました.彼は花束を手に楽団員の拍手を受けていました.年のころ「アラ還」のようなので,今日の演奏会を最後にこのオーケストラを定年退職するのでしょう.去って行く者をみんなで温かく見送る・・・家族的でいいなぁと思います
 過ごしています.本当は昨夕,東銀座の東劇でMETオペラ・ライブビューイング
過ごしています.本当は昨夕,東銀座の東劇でMETオペラ・ライブビューイング ワグナー「神々の黄昏」を見たかったのですが,上映時間が5時間以上かかることから開始時刻が午後5時20分となっていたため,仕事の都合で諦めました
ワグナー「神々の黄昏」を見たかったのですが,上映時間が5時間以上かかることから開始時刻が午後5時20分となっていたため,仕事の都合で諦めました 毎週のように週末はコンサートを中心に予定が入っていて体を休める暇がありません
毎週のように週末はコンサートを中心に予定が入っていて体を休める暇がありません 本当は良くないこととは分かっているのですが,ほとんど半年前から予定を組んでしまっているので今更どうにもなりません.ほとんど病気です
本当は良くないこととは分かっているのですが,ほとんど半年前から予定を組んでしまっているので今更どうにもなりません.ほとんど病気です
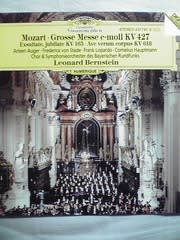
 」,岡田暁生「西洋音楽史」の5冊.ここではもちろん「西洋音楽史」を紹介します.新書版の帯封に次のうたい文句が書かれています.
」,岡田暁生「西洋音楽史」の5冊.ここではもちろん「西洋音楽史」を紹介します.新書版の帯封に次のうたい文句が書かれています.


 私の場合、定期会員になっている7つのオーケストラやオペラの座席をはじめ,単発で買うチケットの座席がほぼすべて通路側であるため、早めに席に着こうものなら、後から後から、奥の席の人が入ってきます
私の場合、定期会員になっている7つのオーケストラやオペラの座席をはじめ,単発で買うチケットの座席がほぼすべて通路側であるため、早めに席に着こうものなら、後から後から、奥の席の人が入ってきます 」とチラシを落とす不届き者がいます.あれは最低です
」とチラシを落とす不届き者がいます.あれは最低です

 これが守れない人は演奏会を聴きにくるべきではありません
これが守れない人は演奏会を聴きにくるべきではありません コンサートが台無しになります.私は以上のような常識をわきまえない人たちを「モンスター・ペアレンツ」に倣って「モンスター・オーディエンス」と呼んでいます.コンサートに行ったときの合言葉は「モンスター・オーディエンスになるな
コンサートが台無しになります.私は以上のような常識をわきまえない人たちを「モンスター・ペアレンツ」に倣って「モンスター・オーディエンス」と呼んでいます.コンサートに行ったときの合言葉は「モンスター・オーディエンスになるな と思っていると,いきなり音程が外れ
と思っていると,いきなり音程が外れ というトンデモ音楽です
というトンデモ音楽です と思うほど見事な外し方をしているのはウィリー・ボスコフスキー指揮ウィーン・モーツアルト合奏団による演奏です.つまり、楽譜通りに演奏しているということですね。
と思うほど見事な外し方をしているのはウィリー・ボスコフスキー指揮ウィーン・モーツアルト合奏団による演奏です.つまり、楽譜通りに演奏しているということですね。
 と思うようなイヤミなやつでした.こういうヤカラには定期会員の更新をして欲しくありませんね
と思うようなイヤミなやつでした.こういうヤカラには定期会員の更新をして欲しくありませんね


 ”と思いました.今回あらためて発見したのはアダージョ楽章の美しさです
”と思いました.今回あらためて発見したのはアダージョ楽章の美しさです
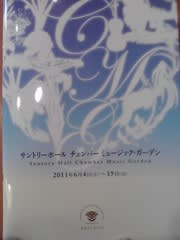




 METオペラ・ライブビューイングでは「イル・トロバトーレ」でルーナ伯爵を歌って盛んな
METオペラ・ライブビューイングでは「イル・トロバトーレ」でルーナ伯爵を歌って盛んな なしで渋谷の街を歩きました.
なしで渋谷の街を歩きました.





