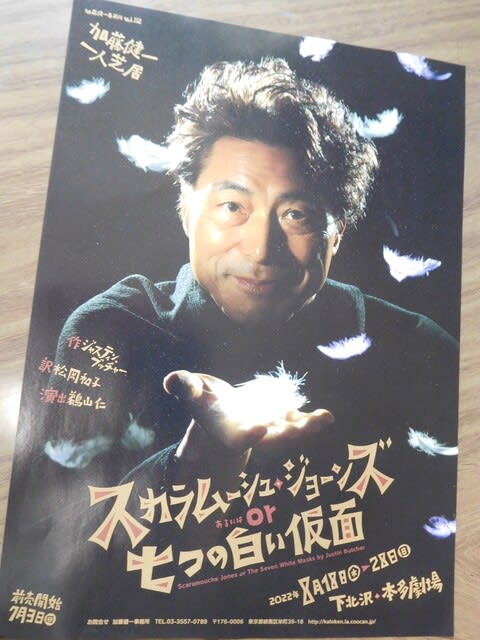<翻訳のこと~松岡和子訳との出会い>
5幕5場、王マクベスの元に、家来が夫人の突然の死の知らせを持って駆け込んで来る。
シートン:お妃さまが、陛下、お亡くなりに
マクベス:あれもいつかは死なねばならなかった。
このような知らせを一度は聞くだろうと思っていた。(小田島雄志訳)
これは私が慣れ親しんできた小田島訳だ。
高校生の頃読んでいた福田恆存訳もこれと同様。
シートン:は、お妃様が、お亡くなりあそばして。
マクベス:あれも、いつかは死なねばならなかったのだ、一度は来ると思っていた、そういう知らせを聞くときが。(福田恆存訳)
ところが、ある公演で、今まで一度も聞いたことがない次のようなセリフが耳に入って来た。
シートン:お妃様が、陛下、お亡くなりになりました。
マクベス:何も今、死ななくてもいいものを。
そんな知らせには、もっとふさわしい時があっただろうに。(松岡和子訳)
それは舞台を日本に置き換えた翻案物で、2007年4月、場所は国立能楽堂で、りゅーとぴあ能楽堂シェイクスピアシリーズの企画、演出は栗田芳宏、
このセリフを口にしていたのは主演の市川右近だった。

その日、私の頭の中はびっくりマークで一杯だった。
文字通り耳を疑った私は、帰宅後、急いで小田島訳を繰って確認した(当時まだ松岡訳を持っていなかった)。
思えばあれが、松岡訳との衝撃の出会いだった。
小田島訳でマクベスは、すでに妻の死を覚悟していて、理屈で自分を納得させよう、諦めようとしている。
松岡訳では、負け戦でただでさえ焦燥、憔悴している時に、かねて覚悟していたとは言え、ここまで苦楽を共にして来た唯一の同志とも言うべき妻の悲報を聞いて
打ちのめされ、ひたすら嘆いており、底知れぬ悲しみがにじみ出ている。
原文は
She should have died hereafter.
There would have been a time for such a word-
文法的にはどちらとも取れるが、日本語に訳すと意味が全く違ってくるので悩ましい。
この後すぐに、tomorrow speech と言われるマクベスの有名な独白が続くのである。
ちなみに、ちくま文庫には松岡氏自身の親切な解説がついていてありがたい。
この時は、まだブログ開設前だったので詳しい内容は覚えていないが、印象的だったのは、このセリフと、もう一つ。
4幕1場で、特別出演の藤間紫が演じたヘカテがゆっくりつぶやく「親指がチクチク痛い、何か悪いものがこっちへ来るよ」というセリフ。
今確認したら、このセリフは本来、魔女2が言うはずだが、この時はヘカテ役の藤間紫が言ったと記憶している。
この人の存在感が半端なく、魔界の雰囲気たっぷりでゾクゾクした。
15年も前のことなのに、その声音をはっきり覚えている。
<蜷川幸雄の「マクベス」>
この戯曲の後半で、主役のマクベスは暴君となり果ててしまうため、何とかしてこの残虐非道な男の暴走を止めて国の平和を取り戻さなくてはいけない、と
誰もが思うようになる。舞台上の人々も、そしてそれを見ている観客も。
そこではもはや、観客が感情移入するのはマクベスではなく、彼を成敗すべく立ち上がる高潔な王子マルカムと、王子を支えるマクダフらだ。
つまり、これまで主役だったマクベスから観客の気持ちが自然と離れてゆくように、戯曲が書かれているのだ。
だが、どうも多くの日本人にはそこが難しいようだ。
魔女たちにたぶらかされて道を誤り、滅びてゆく哀れな男、マクベス。
心優しい日本人は、この男にも「哀れさ」を感じてしまうのだ。
蜷川幸雄の演出はその典型だろう。
マクダフとの最後の一騎打ちは、蜷川が好んで使うスローモーションで、異常に長い時間をかけて見せられる。
戯曲では、セリフの応酬の後、「二人、闘いながら退場」というト書きがあるだけなのに。
アルビノーニの「アダージョ」の甘美な旋律が流れる中、桜吹雪が舞い散り、平幹二朗演じるマクベスは舞いを舞うかのように美しく死んでゆく。
すべてが美しい。
だが、彼の死をあまりに美化したために、すべてが平板になってしまった。
悪事も罪も、当人が死んでしまえばみな無かったことにされるというのだろうか?
一人の男の悲しい運命。諸行無常・・・。
いや、この戯曲は本来そういう話ではないのではなかろうか。
5幕5場、王マクベスの元に、家来が夫人の突然の死の知らせを持って駆け込んで来る。
シートン:お妃さまが、陛下、お亡くなりに
マクベス:あれもいつかは死なねばならなかった。
このような知らせを一度は聞くだろうと思っていた。(小田島雄志訳)
これは私が慣れ親しんできた小田島訳だ。
高校生の頃読んでいた福田恆存訳もこれと同様。
シートン:は、お妃様が、お亡くなりあそばして。
マクベス:あれも、いつかは死なねばならなかったのだ、一度は来ると思っていた、そういう知らせを聞くときが。(福田恆存訳)
ところが、ある公演で、今まで一度も聞いたことがない次のようなセリフが耳に入って来た。
シートン:お妃様が、陛下、お亡くなりになりました。
マクベス:何も今、死ななくてもいいものを。
そんな知らせには、もっとふさわしい時があっただろうに。(松岡和子訳)
それは舞台を日本に置き換えた翻案物で、2007年4月、場所は国立能楽堂で、りゅーとぴあ能楽堂シェイクスピアシリーズの企画、演出は栗田芳宏、
このセリフを口にしていたのは主演の市川右近だった。

その日、私の頭の中はびっくりマークで一杯だった。
文字通り耳を疑った私は、帰宅後、急いで小田島訳を繰って確認した(当時まだ松岡訳を持っていなかった)。
思えばあれが、松岡訳との衝撃の出会いだった。
小田島訳でマクベスは、すでに妻の死を覚悟していて、理屈で自分を納得させよう、諦めようとしている。
松岡訳では、負け戦でただでさえ焦燥、憔悴している時に、かねて覚悟していたとは言え、ここまで苦楽を共にして来た唯一の同志とも言うべき妻の悲報を聞いて
打ちのめされ、ひたすら嘆いており、底知れぬ悲しみがにじみ出ている。
原文は
She should have died hereafter.
There would have been a time for such a word-
文法的にはどちらとも取れるが、日本語に訳すと意味が全く違ってくるので悩ましい。
この後すぐに、tomorrow speech と言われるマクベスの有名な独白が続くのである。
ちなみに、ちくま文庫には松岡氏自身の親切な解説がついていてありがたい。
この時は、まだブログ開設前だったので詳しい内容は覚えていないが、印象的だったのは、このセリフと、もう一つ。
4幕1場で、特別出演の藤間紫が演じたヘカテがゆっくりつぶやく「親指がチクチク痛い、何か悪いものがこっちへ来るよ」というセリフ。
今確認したら、このセリフは本来、魔女2が言うはずだが、この時はヘカテ役の藤間紫が言ったと記憶している。
この人の存在感が半端なく、魔界の雰囲気たっぷりでゾクゾクした。
15年も前のことなのに、その声音をはっきり覚えている。
<蜷川幸雄の「マクベス」>
この戯曲の後半で、主役のマクベスは暴君となり果ててしまうため、何とかしてこの残虐非道な男の暴走を止めて国の平和を取り戻さなくてはいけない、と
誰もが思うようになる。舞台上の人々も、そしてそれを見ている観客も。
そこではもはや、観客が感情移入するのはマクベスではなく、彼を成敗すべく立ち上がる高潔な王子マルカムと、王子を支えるマクダフらだ。
つまり、これまで主役だったマクベスから観客の気持ちが自然と離れてゆくように、戯曲が書かれているのだ。
だが、どうも多くの日本人にはそこが難しいようだ。
魔女たちにたぶらかされて道を誤り、滅びてゆく哀れな男、マクベス。
心優しい日本人は、この男にも「哀れさ」を感じてしまうのだ。
蜷川幸雄の演出はその典型だろう。
マクダフとの最後の一騎打ちは、蜷川が好んで使うスローモーションで、異常に長い時間をかけて見せられる。
戯曲では、セリフの応酬の後、「二人、闘いながら退場」というト書きがあるだけなのに。
アルビノーニの「アダージョ」の甘美な旋律が流れる中、桜吹雪が舞い散り、平幹二朗演じるマクベスは舞いを舞うかのように美しく死んでゆく。
すべてが美しい。
だが、彼の死をあまりに美化したために、すべてが平板になってしまった。
悪事も罪も、当人が死んでしまえばみな無かったことにされるというのだろうか?
一人の男の悲しい運命。諸行無常・・・。
いや、この戯曲は本来そういう話ではないのではなかろうか。