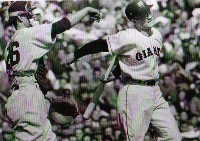今日(12月26日)は、「プロ野球誕生の日,ジャイアンツの日」
1934(昭和9)年、アメリカのプロ野球との対戦の為、日本初のプロ野球チーム・大日本東京野球倶楽部(読売巨人軍の前身)が12月26日に創立され、日本プロ野球の歴史がはじまった。
まさに、日本のプロ野球の歴史は巨人の歴史といっても過言ではないだう。1934(昭和9)年、当時人気の六大学野球に対して、「職業野球」と蔑視されながら、ノーヒットノーランを3回達成した豪腕沢村、初の三冠王中島らを擁し、高い技術を見せ付けて次第にファンを獲得。太平洋戦争で中断されるまでの9年間で8回の優勝(1936年は秋季、1937年は春季、1938年は秋季優勝、その後は一シーズン制)を飾り、第一期黄金時代を築いた。
そして、混乱期の中、ジャイアンツは快進撃を続ける。1940年代こそ優勝は一回だけだが、1950年代に入ると第二期黄金時代が幕を開ける。1951年からは日本シリーズ3連覇、一年おいて1955年にも日本一になるなど、その強さは別格であった。しかし、私を含めて、日本中の人々が、巨人の試合に興味を持ち始めたのは1958(昭和33)年からではないだろうか。立教大学時代、すでにプロ野球選手より人気のあった長嶋茂幾が巨人に入団した。長嶋は、もう、入団した時からスターだった。オープン戦9試合に7ホーマーとファンの期待に応え、その後、4月5日の国鉄スワローズとの開幕戦。国鉄のエース金田正一は、試合前「長嶋だけがプロ選手じゃーない」と言ってのけ、長嶋は見事4連続三振を食らった。さっそく、不名誉なプロ野球新記録の達成である。しかし、終わってみれば、長嶋はこの年、ホームラン王、打点王の2冠を取り、打率も2位。ミスタープロ野球の誕生であった。
1959(昭和34)年に王貞治も巨人に入団し、ON時代が始まる。この1959年6月25日の巨人VS阪神戦。この日プロ野球初の天覧試合が行われた。そして、同点で迎えた9回裏、長嶋は村山のこん身のストレートをスタンドへ運んだ。正に、スターの本領発揮であった。戦後の苦しみから立ち直り、これからの高度経済成長時代をむかえて、長嶋はその時代の牽引車となり、国民のヒーローとしてファンを魅了し続けた。それに対し、デビュー当初の王はパッとしなかったが、恩師・荒川の指導を得て一本足打法を開拓、1962年から1974年まで本塁王を独占することになる。そして、この時期ジャイアンツは、ONを軸に堀内、高橋(一)を中心とした投手陣、スピードに優れる柴田、高田ら脇役陣も充実し、それぞれが個性を発揮。圧倒的な強さで他チームを蹴散らし、1965(昭和40)年~1973(昭和48)年まで、巨人は9年連続日本一に輝いた。そういえば、この時期、終盤のピンチには必ず登板し、ピタっと反撃を抑えこんだ宮田征典投手は「8時半の男」と呼ばれていた。
この時代のジャイアンツは本当に魅力的であり、相撲や高校野球は大好きであったが、プロ野球にはそれほど興味のなかった私も、長嶋が巨人で選手とし在籍していた間は、ジャイアンツのファンであった。
しかし、その長嶋も、1974(昭和49)年10月14日、「巨人は永久に不滅です」の名言を残して引退してしまった。
長嶋が巨人に入団した1958年からスタートしたセ、パ6球団の12球団2リーグ制度。2004年・アテネ五輪で金メダルを獲得すべく「史上初・オールプロ」の長嶋ジャパンで試合に臨んだにもかかわらず、試合前に長嶋監督が脳梗塞(こうそく)で倒れ、オリンピックでの目的も達成出来なかった今年、プロ野球の12球団2リーグ制度が崩壊を始めたのは、偶然ではないかも知れないな~。記録だけ見るならば、川上や王、金田といった大物がずらりといる。しかし、プロ野球史上、彼ほどファンを沸かせた選手はいなかったものな~。
(画像は、公式戦デビュー第1打席はついに三振。長嶋は大きく腕を振って悔しがる。朝日クロニクル・週間20世紀より)
参考:
読売巨人軍
http://www.giants.jp/
プロ野球70年 みんな野球が好きだった (公式ページ)。
http://www.npb.or.jp/love/npb70tvprogram2.html
Sports-J Virtualプロ野球博物館
http://www.sports-j.net/museum/1_top.html
1934(昭和9)年、アメリカのプロ野球との対戦の為、日本初のプロ野球チーム・大日本東京野球倶楽部(読売巨人軍の前身)が12月26日に創立され、日本プロ野球の歴史がはじまった。
まさに、日本のプロ野球の歴史は巨人の歴史といっても過言ではないだう。1934(昭和9)年、当時人気の六大学野球に対して、「職業野球」と蔑視されながら、ノーヒットノーランを3回達成した豪腕沢村、初の三冠王中島らを擁し、高い技術を見せ付けて次第にファンを獲得。太平洋戦争で中断されるまでの9年間で8回の優勝(1936年は秋季、1937年は春季、1938年は秋季優勝、その後は一シーズン制)を飾り、第一期黄金時代を築いた。
そして、混乱期の中、ジャイアンツは快進撃を続ける。1940年代こそ優勝は一回だけだが、1950年代に入ると第二期黄金時代が幕を開ける。1951年からは日本シリーズ3連覇、一年おいて1955年にも日本一になるなど、その強さは別格であった。しかし、私を含めて、日本中の人々が、巨人の試合に興味を持ち始めたのは1958(昭和33)年からではないだろうか。立教大学時代、すでにプロ野球選手より人気のあった長嶋茂幾が巨人に入団した。長嶋は、もう、入団した時からスターだった。オープン戦9試合に7ホーマーとファンの期待に応え、その後、4月5日の国鉄スワローズとの開幕戦。国鉄のエース金田正一は、試合前「長嶋だけがプロ選手じゃーない」と言ってのけ、長嶋は見事4連続三振を食らった。さっそく、不名誉なプロ野球新記録の達成である。しかし、終わってみれば、長嶋はこの年、ホームラン王、打点王の2冠を取り、打率も2位。ミスタープロ野球の誕生であった。
1959(昭和34)年に王貞治も巨人に入団し、ON時代が始まる。この1959年6月25日の巨人VS阪神戦。この日プロ野球初の天覧試合が行われた。そして、同点で迎えた9回裏、長嶋は村山のこん身のストレートをスタンドへ運んだ。正に、スターの本領発揮であった。戦後の苦しみから立ち直り、これからの高度経済成長時代をむかえて、長嶋はその時代の牽引車となり、国民のヒーローとしてファンを魅了し続けた。それに対し、デビュー当初の王はパッとしなかったが、恩師・荒川の指導を得て一本足打法を開拓、1962年から1974年まで本塁王を独占することになる。そして、この時期ジャイアンツは、ONを軸に堀内、高橋(一)を中心とした投手陣、スピードに優れる柴田、高田ら脇役陣も充実し、それぞれが個性を発揮。圧倒的な強さで他チームを蹴散らし、1965(昭和40)年~1973(昭和48)年まで、巨人は9年連続日本一に輝いた。そういえば、この時期、終盤のピンチには必ず登板し、ピタっと反撃を抑えこんだ宮田征典投手は「8時半の男」と呼ばれていた。
この時代のジャイアンツは本当に魅力的であり、相撲や高校野球は大好きであったが、プロ野球にはそれほど興味のなかった私も、長嶋が巨人で選手とし在籍していた間は、ジャイアンツのファンであった。
しかし、その長嶋も、1974(昭和49)年10月14日、「巨人は永久に不滅です」の名言を残して引退してしまった。
長嶋が巨人に入団した1958年からスタートしたセ、パ6球団の12球団2リーグ制度。2004年・アテネ五輪で金メダルを獲得すべく「史上初・オールプロ」の長嶋ジャパンで試合に臨んだにもかかわらず、試合前に長嶋監督が脳梗塞(こうそく)で倒れ、オリンピックでの目的も達成出来なかった今年、プロ野球の12球団2リーグ制度が崩壊を始めたのは、偶然ではないかも知れないな~。記録だけ見るならば、川上や王、金田といった大物がずらりといる。しかし、プロ野球史上、彼ほどファンを沸かせた選手はいなかったものな~。
(画像は、公式戦デビュー第1打席はついに三振。長嶋は大きく腕を振って悔しがる。朝日クロニクル・週間20世紀より)
参考:
読売巨人軍
http://www.giants.jp/
プロ野球70年 みんな野球が好きだった (公式ページ)。
http://www.npb.or.jp/love/npb70tvprogram2.html
Sports-J Virtualプロ野球博物館
http://www.sports-j.net/museum/1_top.html