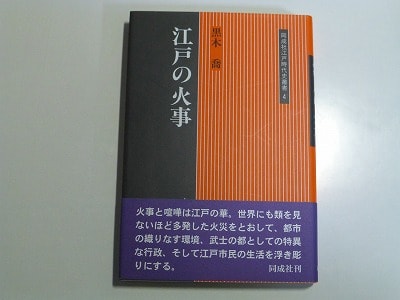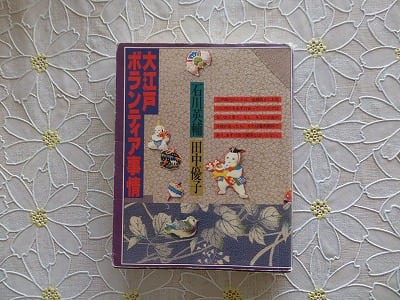昨年から、日本NPOセンターのオフィスに大き目のカップヌードルのようなものが置いてありました。
カップで育てるハーブとやらで、数日前に水をあげたら、もうバジルの芽が出てきました。

なかなかの代物だと思うのですが、疑問なことが二つほどあります。
その一
太陽光線の入らないビルのオフィスの蛍光灯の明かりだけで、このまま大きく育つのでしょうか。
その二
メーカーのHPを見たら、バジルの調理例としてピザが紹介されていましたが、ピザは誰が用意するのでしょうか。
二つの疑問を考えていると夜も眠れなくなります。
カップで育てるハーブとやらで、数日前に水をあげたら、もうバジルの芽が出てきました。

なかなかの代物だと思うのですが、疑問なことが二つほどあります。
その一
太陽光線の入らないビルのオフィスの蛍光灯の明かりだけで、このまま大きく育つのでしょうか。
その二
メーカーのHPを見たら、バジルの調理例としてピザが紹介されていましたが、ピザは誰が用意するのでしょうか。
二つの疑問を考えていると夜も眠れなくなります。