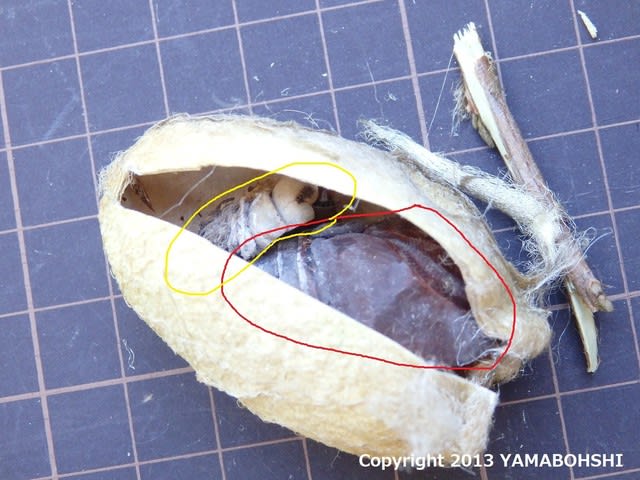犬と散歩をしていると、水田の小さな用水路のそばに小さな足跡がついていました。イタチのものだと思います。足跡は雪のトンネルで用水路に続いていました。
雪にところどころトンネルを掘って動き回るイタチの足跡は、以前、頼成の森の花しょうぶ田でよく見かけました。https://blog.goo.ne.jp/ranmoriblog/e/f2557956f1b10c8e46dc7e3114c03776

《犬との散歩道(右側は雪に覆われた水田) 2019/02/09》

《イタチの足跡(トンネルで用水路に続いています) 2019/02/09》

《イタチの足跡(トンネルで用水路に続いています) 2019/02/09》