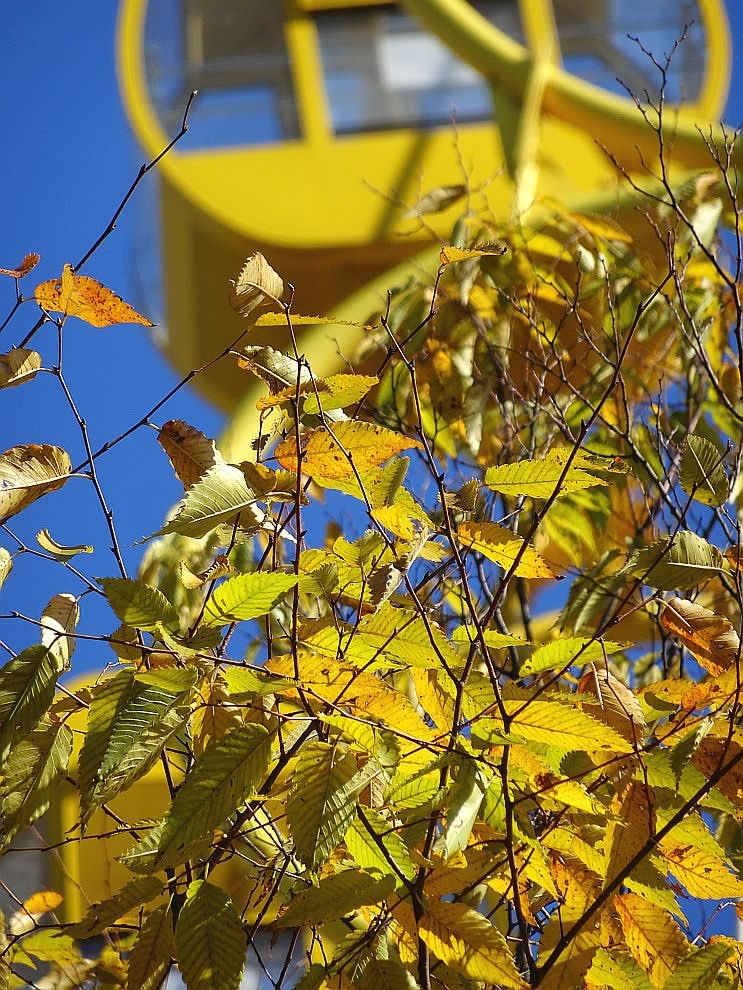おはようございます!
昨日は「晩秋のヒマワリ」をとりあげましたので、ヒマワリつながりで、今度は「コウテイヒマワリ」です。

といっても、「コウテイヒマワリ」は別名で、一般的な和名は「ニトベギク」です。
でも、「ニトベギク」はちょっとわかりにくい。

英語で Mexican Sunflower とか Tree Marigold と呼ばれているらしいです。
ニトベギクといってもこの木のようなヒマワリを想像しづらいので、「コウテイヒマワリ」でなければ、英語名のほうがふさわしい気がします。

「中米、東南アジア、アフリカなど熱帯・亜熱帯の地域に広く分布する。」
「日本では主に沖縄県で自生し、お茶として嗜まれている。」(wiki 「ニトベギク」)
「糖尿病への効果においてアメリカと日本の共同で特許を取得済みである。効果としては血糖値の減少と合併症の軽減、消失があげられる。葉には多くのポリフェノールや機能性成分が含まれており、糖尿病だけでなく癌、肝炎などに効く。」(同上)
以下、吸蜜するミツバチ

ウコギ科の花には ハエやアブが来ていましたが…

ヒマワリには ハチが訪れることが圧倒的に多いようです。

雄しべ筒の間をかき分けて…

蜜を吸います。