ウツギの名が付く花は多様ですが、アジサイ科のウツギ属(Deutzia)となると種類は限られてきます。
きょうはそのウツギ属の花をおおむね咲く順番に紹介します。
以下に 6種類紹介しますが、そのうち元々の(園芸品種でない)ウツギ属は ウツギ(卯の花)、ヒメウツギ、マルバウツギの3種類だけです。
ヒメウツギ

園芸品種でないウツギ属(Deutzia)のうち、一番早く咲くのは ヒメウツギです。
以下3枚は 3月10日に撮ったものです。


一枚目もそうですが、ウツギ属(Deutzia)の花の特徴は雄しべにあります。葯(花粉の袋)を持ちあげる花糸が ウツギ属のばあい、扁平できしめんのようなのです。これを花糸から翼が横に伸びているといいます。

ここからは4月25日に撮影したヒメウツギの花。

面白いことに翼のいちばん上の部分の形状が先ほどと異なります。
さっきの(3月10日の)花糸のいちばん上は直角でしたが、今度のは肩が吊り上がっています。

最後は4月27日に撮影のヒメウツギ。
花糸のいちばん上はやじろべいみたいな突起が出ています。
同じヒメウツギでも翼のいちばん上は直角~出っ張っているものと変異があるようです。
マルバウツギ

ウツギ3兄弟(ウツギ、ヒメウツギ、マルバウツギ)のうち2番目に咲くのは このマルバウツギです。
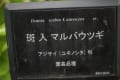
安城デンパークにて、5月2日の撮影です。

マルバウツギの花の特徴は中央の花盤の黄色がよく目立つことです。

名のとおり葉が丸いのも特徴ですが、雄しべの花糸にも特徴があります。翼の付いている花糸が扁平なのは他のウツギ属同様ですが、マルバウツギは葉が丸いのに合わせて花糸の肩の部分が「なで肩」なのです。
ウツギ・マギシェン

安城デンパークにて、5月13日の撮影です。

樹名板には 学名が Deutzia x hybrida 'Magicien' とまず書いてあり、
名がカタカナで 「デウィツィア ’マギシェン’」と書いてあります。
私はこのカタカナ名を見るたびに違和感を覚えます、「デウィツィア」の「ウィ」ってどこから来たのだろうと。
詳しくは 先日のスレッドを見てほしいのですが、Deutzia は、オランダの「Deutz(ドイツ)さん」の名にちなむものであること、しかしながらそうであっても学名はラテン語読みするものと決められているので、「デウツィア」「デゥツィア」と読むべきでは?というのが私の見解です。

ま、それはそうとして、雄しべの花糸ですが・・・ (´∀`)

ヒメウツギのツッパリ肩をさらに強調したような肩をしています。


ウツギ・ロザリンド Deutzia x elegantissima

安城デンパークにて、 5月5日の撮影です。とても小さな花です。

Deutzia x elegantissima 'Rosealind'
でも「ウツギ属(デゥツィア)」と樹名板に書いてあります。
先述した通り、「属名の Deutzia はツンベルクが後援者の「ドイツさん(Johan van der Deutz)」にちなんで名づけた。」(みんなの花図鑑)ものですから、それを鑑みれば「ドイツィア」なんでしょうが、学名はラテン読みするのが習わしなので「デウツィア」が妥当でしょう。

ウツギ属(デゥツィア)ということで、雄しべの花糸を観察するのですが・・・小さくてよく見えません。

それでも、この画像によると、「マギシェン」よりさらにいかり肩で、「くぎ抜き」みたいになっていることが分かります。
ウツギ(卯の花)

ようやく出て来ました。
過年度ですが、5月31日 愛知県緑化センターでの撮影です。

ユキノシタ科となってますが、ウツギ属は現在 アジサイ科となってることが多いです。

元祖?ウツギはいわゆる「卯の花」と呼ばれている樹です。

開き始めは エゴノキか、ハクウンボク(白雲木)のように見えることもしばしば。

さて、雄しべの花糸ですが、お~、翼のいちばん上から角が出てる!(^^)!

これなど、耳かきの先のよう (^_-)-☆

雨で落ちた花。
6月11日の撮影です。
ウツギの雄しべは「花糸の両側には狭い翼があり、上部は広がって、先端は歯牙状に鋭く突出する。」と言われてます。
またこういう記述もあります↓
「ウツギは雄蕊の花糸(かし)に翼(よく)と呼ばれる出っ張りができるが、これがほぼ真横に突き出るのが特徴。花がよく似るヒメウツギ(姫空木)の翼は斜め上に向かって突き出る。」(mirusiru.jp 「ウツギ」)
サラサウツギ

ウツギの園芸品種で、八重のものをサラサウツギと呼んでいます。

八重は雄しべが花弁になったものです。


雄しべはほとんど見えませんが、かろうじて残っているのを見ると、花糸はウツギの形(横に突き出す)のようです。
.
きょうはそのウツギ属の花をおおむね咲く順番に紹介します。
以下に 6種類紹介しますが、そのうち元々の(園芸品種でない)ウツギ属は ウツギ(卯の花)、ヒメウツギ、マルバウツギの3種類だけです。
ヒメウツギ

園芸品種でないウツギ属(Deutzia)のうち、一番早く咲くのは ヒメウツギです。
以下3枚は 3月10日に撮ったものです。


一枚目もそうですが、ウツギ属(Deutzia)の花の特徴は雄しべにあります。葯(花粉の袋)を持ちあげる花糸が ウツギ属のばあい、扁平できしめんのようなのです。これを花糸から翼が横に伸びているといいます。

ここからは4月25日に撮影したヒメウツギの花。

面白いことに翼のいちばん上の部分の形状が先ほどと異なります。
さっきの(3月10日の)花糸のいちばん上は直角でしたが、今度のは肩が吊り上がっています。

最後は4月27日に撮影のヒメウツギ。
花糸のいちばん上はやじろべいみたいな突起が出ています。
同じヒメウツギでも翼のいちばん上は直角~出っ張っているものと変異があるようです。
マルバウツギ

ウツギ3兄弟(ウツギ、ヒメウツギ、マルバウツギ)のうち2番目に咲くのは このマルバウツギです。
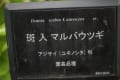
安城デンパークにて、5月2日の撮影です。

マルバウツギの花の特徴は中央の花盤の黄色がよく目立つことです。

名のとおり葉が丸いのも特徴ですが、雄しべの花糸にも特徴があります。翼の付いている花糸が扁平なのは他のウツギ属同様ですが、マルバウツギは葉が丸いのに合わせて花糸の肩の部分が「なで肩」なのです。
ウツギ・マギシェン

安城デンパークにて、5月13日の撮影です。

樹名板には 学名が Deutzia x hybrida 'Magicien' とまず書いてあり、
名がカタカナで 「デウィツィア ’マギシェン’」と書いてあります。
私はこのカタカナ名を見るたびに違和感を覚えます、「デウィツィア」の「ウィ」ってどこから来たのだろうと。
詳しくは 先日のスレッドを見てほしいのですが、Deutzia は、オランダの「Deutz(ドイツ)さん」の名にちなむものであること、しかしながらそうであっても学名はラテン語読みするものと決められているので、「デウツィア」「デゥツィア」と読むべきでは?というのが私の見解です。

ま、それはそうとして、雄しべの花糸ですが・・・ (´∀`)

ヒメウツギのツッパリ肩をさらに強調したような肩をしています。


ウツギ・ロザリンド Deutzia x elegantissima

安城デンパークにて、 5月5日の撮影です。とても小さな花です。

Deutzia x elegantissima 'Rosealind'
でも「ウツギ属(デゥツィア)」と樹名板に書いてあります。
先述した通り、「属名の Deutzia はツンベルクが後援者の「ドイツさん(Johan van der Deutz)」にちなんで名づけた。」(みんなの花図鑑)ものですから、それを鑑みれば「ドイツィア」なんでしょうが、学名はラテン読みするのが習わしなので「デウツィア」が妥当でしょう。

ウツギ属(デゥツィア)ということで、雄しべの花糸を観察するのですが・・・小さくてよく見えません。

それでも、この画像によると、「マギシェン」よりさらにいかり肩で、「くぎ抜き」みたいになっていることが分かります。
ウツギ(卯の花)

ようやく出て来ました。
過年度ですが、5月31日 愛知県緑化センターでの撮影です。

ユキノシタ科となってますが、ウツギ属は現在 アジサイ科となってることが多いです。

元祖?ウツギはいわゆる「卯の花」と呼ばれている樹です。

開き始めは エゴノキか、ハクウンボク(白雲木)のように見えることもしばしば。

さて、雄しべの花糸ですが、お~、翼のいちばん上から角が出てる!(^^)!

これなど、耳かきの先のよう (^_-)-☆

雨で落ちた花。
6月11日の撮影です。
ウツギの雄しべは「花糸の両側には狭い翼があり、上部は広がって、先端は歯牙状に鋭く突出する。」と言われてます。
またこういう記述もあります↓
「ウツギは雄蕊の花糸(かし)に翼(よく)と呼ばれる出っ張りができるが、これがほぼ真横に突き出るのが特徴。花がよく似るヒメウツギ(姫空木)の翼は斜め上に向かって突き出る。」(mirusiru.jp 「ウツギ」)
サラサウツギ

ウツギの園芸品種で、八重のものをサラサウツギと呼んでいます。

八重は雄しべが花弁になったものです。


雄しべはほとんど見えませんが、かろうじて残っているのを見ると、花糸はウツギの形(横に突き出す)のようです。
.



























































































































































































