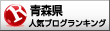第2農場といえば園芸科学科と環境システム科の温室群が立ち並んでいますが
さらにその奥に足を踏み入れると、初めての方には珍しく
昔の名農を知っている人にとっては懐かしい施設や設備を見ることができます。
さあこのスペースXの発射台のようなものは何でしょう。
かなり大きいものです。名前はベールエレベーター。
ベールとは牛の餌となる干し草を圧縮梱包したもの。
つまりこれは少人数でキューブに梱包された干し草を
トラックなどに積み込むための装置というわけです。
ただ最近は干し草を大きなロールにしてポリシートで
巨大なトイレットペーパーのように梱包する方法が一般的になったので
あまり見ることはなくなったのではないでしょうか。
さてこの酪農で使う農業機械ですが、動物のない名農になぜあるのでしょうか。
実はその昔、名久井農業高校には畜産科があったのです。
学科再編で閉科してしまいましたが、農業動物を学ぶ教材として
10年ほど前まで肉牛を飼育していました。
この農機はそんな時代の遺産なのです。
名農には農業科、生活科、農芸化学科などいろいろな学科がありました。
農場を歩くと名農の歴史、つまり農業の歴史を物語る遺産を見つけられます。
ちょっとしたタイムトラベル。静かな農場に吹く風を感じながら魔を閉じると
当時の様子が蘇ってくるかのようです。
さらにその奥に足を踏み入れると、初めての方には珍しく
昔の名農を知っている人にとっては懐かしい施設や設備を見ることができます。
さあこのスペースXの発射台のようなものは何でしょう。
かなり大きいものです。名前はベールエレベーター。
ベールとは牛の餌となる干し草を圧縮梱包したもの。
つまりこれは少人数でキューブに梱包された干し草を
トラックなどに積み込むための装置というわけです。
ただ最近は干し草を大きなロールにしてポリシートで
巨大なトイレットペーパーのように梱包する方法が一般的になったので
あまり見ることはなくなったのではないでしょうか。
さてこの酪農で使う農業機械ですが、動物のない名農になぜあるのでしょうか。
実はその昔、名久井農業高校には畜産科があったのです。
学科再編で閉科してしまいましたが、農業動物を学ぶ教材として
10年ほど前まで肉牛を飼育していました。
この農機はそんな時代の遺産なのです。
名農には農業科、生活科、農芸化学科などいろいろな学科がありました。
農場を歩くと名農の歴史、つまり農業の歴史を物語る遺産を見つけられます。
ちょっとしたタイムトラベル。静かな農場に吹く風を感じながら魔を閉じると
当時の様子が蘇ってくるかのようです。