大阪七坂めぐりウォーキング、無事完歩いたしました。
ご参加頂きました皆様、お疲れ様でございました。
歴史が多く感じられるコースですが、私には心得が無く、御説明不足で失礼をしました。
楽しい今日の道を思い出しながら、解説を補足させていただきますね。
というわけで、長文です!
四天王寺聖徳太子が建立。『日本書紀』によれば推古天皇元年(593年)に造立が開始されたそうです。奈良の飛鳥寺と並んで日本最古の本格的な仏教寺院。
現在の「天王寺」は四天王寺の略称だそうです。
六時堂(重要文化財)前の「亀の池」の中央にある石舞台は「日本三舞台」の一つとされ、これも重要文化財。
Tさん・・・亀さん、キレイに写れましたか~?


さあ、大阪七坂めぐりスタート!!
大阪市の中心部を南北に走る上町台地(北は馬場町から南は手塚山辺りまで続く台地)の西縁に沿って谷町筋と松屋町筋の間にある代表的な7つの坂。
逢坂
さあ1つ目の坂は 逢坂。皆さん、通った事に気づかれましたか?
昔は「合坂」とも表記されていました。この坂の下の辻は「合法ヶ辻(がっぽうがつじ)」と呼ばれ、聖徳太子と物部守屋が仏法を論じ合い、法を比べ合わせた場所だといわれています
現在、ここは 大きな国道となっています。
 天神坂
天神坂
2つ目の坂は 天神坂。天神坂の横上に建つ安居神社には 大阪夏の陣で負傷した豊臣方の智将・真田幸村がこの地で徳川方の急襲に遭い、戦死したと伝えられ、本殿脇には真田幸村戦死跡之碑があります。
またこの辺りは 大阪は水の都と言われますが、その昔は町の井戸水の質が悪く、飲料水の確保が困難だった中、ここ天王寺は、亀井・逢坂・玉手・安井・増井・有栖・金龍の名水が湧き、天王寺七名水と呼ばれたそうです。
清水坂


3つ目の坂は 清水坂(きよみずさか)。
うさぎ年生まれの同級生おふたりは 仲良しですね。
さて、この横の清水寺には 大阪で唯一の滝、玉手の滝があります。滝に打たれながら真言を唱え、礼拝すると抜苦与楽、福寿増長、心願成就の霊験が授かるといわれています。
本日は 寄りませんでしたが、夏にでも滝修行にまいりましょうか??
愛染坂

 4つ目の坂は 愛染坂。
4つ目の坂は 愛染坂。
こちらには 愛染さんと呼ばれる勝鬘院愛染堂があります。聖徳太子創建、豊臣秀吉再建の重要文化財です。
縁結びの神様としても有名で、映画「愛染かつら」の舞台です。
今日ご参加の方で、この映画を3回も見に行ったという方がいらっしゃいました。
ちなみにこの映画は 田中絹代、上原謙主演。1938年上映です。
私は その時・・・???
口縄坂
5つ目の坂は 口縄坂。
昔、蛇を口縄と呼び、坂の形状が蛇に似ていたのだそうです。
大阪を代表する坂として、よく被写体となる人気の坂で、坂の上には、織田作之助の文学碑があります。
「木の都」の一節、「口縄坂は寒々と木が枯れて、白い風が走つていた。私は石段を降りて行きながら、もうこの坂を登り降りすることも当分あるまいと思つた。青春の回想の甘さは終り、新しい現実が私に向き直つて来たように思われた。風は木の梢にはげしく突っかかっていた」が刻まれています。
この本が読みたくなり、帰りに梅田の紀伊国屋に寄りましたが、残念ながら在庫がありませんでした。織田作之助さんの夫婦善哉も私が育った地がたくさん出てくるので、読んでみたいな~。
寺町
「お寺」の多い地域で、昔、大相撲大阪場所の時は各部屋の宿舎はこの辺りに集中し、「ごひいき」様のことを「谷町」と云うのもこの辺りの事からきているそうです。
私が小学生の頃、千日前で飲食店を営んでいたうちの店にも相撲部屋の親方、力士、谷町の旦那様がお越しくださり、ぽっちゃりしていた弟が親方にスカウトされていました。
只今、相撲界は 大変なことですが・・・。
源聖寺坂
 6つ目の坂は 難所です。 介助についていたため、写真は ありません。
6つ目の坂は 難所です。 介助についていたため、写真は ありません。
お相撲さんも、昇ったり、下ったりしてトレーニングをしていた坂だそうです。
この坂は登り口に源聖寺があるので、その名を取っているそうです。
付近一帯は、寺町として長い歴史を持つ坂を挟む齢延寺には、幕末に泊園書院を興して活躍した藤沢東畡・同南岳父子の墓があり、向かい側の銀山寺には、近松門左衛門の「心中宵庚申」にでてくるお千代、半兵衛の比翼塚が建てられているそうです。
齢延寺では住職さんがパンフレットなどを配ってくださり、御親切にして頂きました。
生國魂神社から真言坂
 日本国土の御神霊、八十島神である生島大神・足島大神を祀られ、国土平安を祈請された事に始まる大阪最古にして日本総鎮守の神社。
日本国土の御神霊、八十島神である生島大神・足島大神を祀られ、国土平安を祈請された事に始まる大阪最古にして日本総鎮守の神社。
毎年7月11日・12日には生玉・天満・住吉と続く、大阪三大夏祭りのさきがけ「いくたま夏祭」が盛大に行われます。
ちなみに大阪の夏祭りの始まりは 先ほどの愛染さんのお祭りです。
生國魂神社をあとにして、最後の7つめの坂、真言坂。
このあたりに生國魂神社の神宮寺だった法案寺をはじめとした真言宗の仏教寺院が十坊(「生玉十坊」と呼ばれた)あったことに由来します。
この坂だけが生國魂神社から千日前筋へ南北に通る短い坂です。
高津神社
さあ、ゴールは 梅の開花が楽しみな高津神社。
残念ながら梅は まだ咲かず・・・でしたが、皆さんは 笑顔満開でゴール!!

高津神社は 浪速の地を皇都(高津宮)と定められ大阪隆昌の基を築かれた仁徳天皇を王神と仰ぐ神社だそうです。
大阪市歌(そんなん、あったん?)には「高津宮の昔より代々栄えをかさねきて民のかまどに立つけむりのにぎわいにまさる大阪市・・・」と歌われています。
また今日、歩いた道は 古典落語の舞台としても登場するところが多いのですが、特にこの高津神社は “高津の富”という落語の舞台となっています。
落語“高津の冨”淀屋橋のみなみ大川町にあった宿屋に「鳥取の大金持ちだ」と大ホラ吹きまいて宿賃を踏み倒そうとする男がやってくる。大金持ちと言った手前、宿のおやじにすすめられた富くじを断り切れず、なけなしの一分でくじを買ったところ、その富くじが千両当ったからアラ大変、、、この富くじの抽選会場となったのが高津宮。昔のにぎわいが感じられます。
五代目 桂文枝之碑
 桂三枝さんの師匠 桂文枝さんは 平成十七年一月十日高津宮での「高津の富」を最後にお亡くなりになりました。この碑は 桂文枝さんの功績を称え、桂文枝さんが心血を注ぎ創作し演じた「熊野詣」にちなんで世界遺産にも登録された熊野の石材を用い長年の盟友であった三代目桂春団治さんの筆により建立されたそうです。
桂三枝さんの師匠 桂文枝さんは 平成十七年一月十日高津宮での「高津の富」を最後にお亡くなりになりました。この碑は 桂文枝さんの功績を称え、桂文枝さんが心血を注ぎ創作し演じた「熊野詣」にちなんで世界遺産にも登録された熊野の石材を用い長年の盟友であった三代目桂春団治さんの筆により建立されたそうです。
桂文枝さんの落語は 聞いたことないけれど、テレビの素人名人会の審査員で上品な方やな~との印象が残っています。
 みなさん、今日歩いた場所をまた、どなたかと一緒に歩いてみてください。
みなさん、今日歩いた場所をまた、どなたかと一緒に歩いてみてください。
梅の咲く頃、桜の咲く頃、夕日の頃、夏まつりの頃・・・
色々な味わいをお楽しみいただけることと思います。
楽しい1日をありがとうございました。
嬉しさあまり、長々と書いてしまいました。
あれあれ??
お帰りに、こちらの味わいを楽しまれていますね~!?


ご参加頂きました皆様、お疲れ様でございました。
歴史が多く感じられるコースですが、私には心得が無く、御説明不足で失礼をしました。
楽しい今日の道を思い出しながら、解説を補足させていただきますね。
というわけで、長文です!
四天王寺聖徳太子が建立。『日本書紀』によれば推古天皇元年(593年)に造立が開始されたそうです。奈良の飛鳥寺と並んで日本最古の本格的な仏教寺院。
現在の「天王寺」は四天王寺の略称だそうです。
六時堂(重要文化財)前の「亀の池」の中央にある石舞台は「日本三舞台」の一つとされ、これも重要文化財。
Tさん・・・亀さん、キレイに写れましたか~?


さあ、大阪七坂めぐりスタート!!
大阪市の中心部を南北に走る上町台地(北は馬場町から南は手塚山辺りまで続く台地)の西縁に沿って谷町筋と松屋町筋の間にある代表的な7つの坂。
逢坂
さあ1つ目の坂は 逢坂。皆さん、通った事に気づかれましたか?
昔は「合坂」とも表記されていました。この坂の下の辻は「合法ヶ辻(がっぽうがつじ)」と呼ばれ、聖徳太子と物部守屋が仏法を論じ合い、法を比べ合わせた場所だといわれています
現在、ここは 大きな国道となっています。
 天神坂
天神坂2つ目の坂は 天神坂。天神坂の横上に建つ安居神社には 大阪夏の陣で負傷した豊臣方の智将・真田幸村がこの地で徳川方の急襲に遭い、戦死したと伝えられ、本殿脇には真田幸村戦死跡之碑があります。
またこの辺りは 大阪は水の都と言われますが、その昔は町の井戸水の質が悪く、飲料水の確保が困難だった中、ここ天王寺は、亀井・逢坂・玉手・安井・増井・有栖・金龍の名水が湧き、天王寺七名水と呼ばれたそうです。
清水坂


3つ目の坂は 清水坂(きよみずさか)。
うさぎ年生まれの同級生おふたりは 仲良しですね。
さて、この横の清水寺には 大阪で唯一の滝、玉手の滝があります。滝に打たれながら真言を唱え、礼拝すると抜苦与楽、福寿増長、心願成就の霊験が授かるといわれています。
本日は 寄りませんでしたが、夏にでも滝修行にまいりましょうか??
愛染坂

 4つ目の坂は 愛染坂。
4つ目の坂は 愛染坂。こちらには 愛染さんと呼ばれる勝鬘院愛染堂があります。聖徳太子創建、豊臣秀吉再建の重要文化財です。
縁結びの神様としても有名で、映画「愛染かつら」の舞台です。
今日ご参加の方で、この映画を3回も見に行ったという方がいらっしゃいました。
ちなみにこの映画は 田中絹代、上原謙主演。1938年上映です。
私は その時・・・???
口縄坂

5つ目の坂は 口縄坂。
昔、蛇を口縄と呼び、坂の形状が蛇に似ていたのだそうです。
大阪を代表する坂として、よく被写体となる人気の坂で、坂の上には、織田作之助の文学碑があります。
「木の都」の一節、「口縄坂は寒々と木が枯れて、白い風が走つていた。私は石段を降りて行きながら、もうこの坂を登り降りすることも当分あるまいと思つた。青春の回想の甘さは終り、新しい現実が私に向き直つて来たように思われた。風は木の梢にはげしく突っかかっていた」が刻まれています。
この本が読みたくなり、帰りに梅田の紀伊国屋に寄りましたが、残念ながら在庫がありませんでした。織田作之助さんの夫婦善哉も私が育った地がたくさん出てくるので、読んでみたいな~。
寺町

「お寺」の多い地域で、昔、大相撲大阪場所の時は各部屋の宿舎はこの辺りに集中し、「ごひいき」様のことを「谷町」と云うのもこの辺りの事からきているそうです。
私が小学生の頃、千日前で飲食店を営んでいたうちの店にも相撲部屋の親方、力士、谷町の旦那様がお越しくださり、ぽっちゃりしていた弟が親方にスカウトされていました。
只今、相撲界は 大変なことですが・・・。
源聖寺坂
 6つ目の坂は 難所です。 介助についていたため、写真は ありません。
6つ目の坂は 難所です。 介助についていたため、写真は ありません。お相撲さんも、昇ったり、下ったりしてトレーニングをしていた坂だそうです。
この坂は登り口に源聖寺があるので、その名を取っているそうです。
付近一帯は、寺町として長い歴史を持つ坂を挟む齢延寺には、幕末に泊園書院を興して活躍した藤沢東畡・同南岳父子の墓があり、向かい側の銀山寺には、近松門左衛門の「心中宵庚申」にでてくるお千代、半兵衛の比翼塚が建てられているそうです。
齢延寺では住職さんがパンフレットなどを配ってくださり、御親切にして頂きました。
生國魂神社から真言坂
 日本国土の御神霊、八十島神である生島大神・足島大神を祀られ、国土平安を祈請された事に始まる大阪最古にして日本総鎮守の神社。
日本国土の御神霊、八十島神である生島大神・足島大神を祀られ、国土平安を祈請された事に始まる大阪最古にして日本総鎮守の神社。毎年7月11日・12日には生玉・天満・住吉と続く、大阪三大夏祭りのさきがけ「いくたま夏祭」が盛大に行われます。
ちなみに大阪の夏祭りの始まりは 先ほどの愛染さんのお祭りです。
生國魂神社をあとにして、最後の7つめの坂、真言坂。
このあたりに生國魂神社の神宮寺だった法案寺をはじめとした真言宗の仏教寺院が十坊(「生玉十坊」と呼ばれた)あったことに由来します。
この坂だけが生國魂神社から千日前筋へ南北に通る短い坂です。
高津神社
さあ、ゴールは 梅の開花が楽しみな高津神社。
残念ながら梅は まだ咲かず・・・でしたが、皆さんは 笑顔満開でゴール!!

高津神社は 浪速の地を皇都(高津宮)と定められ大阪隆昌の基を築かれた仁徳天皇を王神と仰ぐ神社だそうです。
大阪市歌(そんなん、あったん?)には「高津宮の昔より代々栄えをかさねきて民のかまどに立つけむりのにぎわいにまさる大阪市・・・」と歌われています。
また今日、歩いた道は 古典落語の舞台としても登場するところが多いのですが、特にこの高津神社は “高津の富”という落語の舞台となっています。
落語“高津の冨”淀屋橋のみなみ大川町にあった宿屋に「鳥取の大金持ちだ」と大ホラ吹きまいて宿賃を踏み倒そうとする男がやってくる。大金持ちと言った手前、宿のおやじにすすめられた富くじを断り切れず、なけなしの一分でくじを買ったところ、その富くじが千両当ったからアラ大変、、、この富くじの抽選会場となったのが高津宮。昔のにぎわいが感じられます。
五代目 桂文枝之碑
 桂三枝さんの師匠 桂文枝さんは 平成十七年一月十日高津宮での「高津の富」を最後にお亡くなりになりました。この碑は 桂文枝さんの功績を称え、桂文枝さんが心血を注ぎ創作し演じた「熊野詣」にちなんで世界遺産にも登録された熊野の石材を用い長年の盟友であった三代目桂春団治さんの筆により建立されたそうです。
桂三枝さんの師匠 桂文枝さんは 平成十七年一月十日高津宮での「高津の富」を最後にお亡くなりになりました。この碑は 桂文枝さんの功績を称え、桂文枝さんが心血を注ぎ創作し演じた「熊野詣」にちなんで世界遺産にも登録された熊野の石材を用い長年の盟友であった三代目桂春団治さんの筆により建立されたそうです。桂文枝さんの落語は 聞いたことないけれど、テレビの素人名人会の審査員で上品な方やな~との印象が残っています。
 みなさん、今日歩いた場所をまた、どなたかと一緒に歩いてみてください。
みなさん、今日歩いた場所をまた、どなたかと一緒に歩いてみてください。梅の咲く頃、桜の咲く頃、夕日の頃、夏まつりの頃・・・
色々な味わいをお楽しみいただけることと思います。
楽しい1日をありがとうございました。
嬉しさあまり、長々と書いてしまいました。
あれあれ??
お帰りに、こちらの味わいを楽しまれていますね~!?













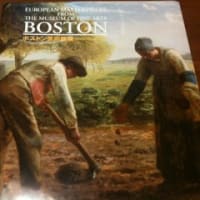







プログで 田中絹代で 検索して ランダムに
コメントしています。
大阪 七坂めぐり というのがあるんですね
さだまさし さん の 無縁坂を なんとなく思い出します
コメント、ありがとうございます。
大阪は 本来、「大坂」なのですよね。
大阪の良いところ、是非おいでやす。
さだまさしさん…好きです。