「ママ、変な人やと思われるよ!」
と娘に注意されるのですが、落語の稽古をしながらウォーキングをするのが実に心地よいのです。
そろそろ寒くなってきたので、マスクをすると変人は回避できるかな。
心地が良いのは・・・
長時間歩くのも苦痛なくアッというまに時間が過ぎ、歩数が稼げる。
じっとして稽古するより、不思議と落語の覚えが良い。
脳にも足腰にも心地よいのです。
本日、ある打ち合わせで認知症と運動の関係をお話し、運動が脳の働きを良くして、認知症や鬱にも効果があるのは分かっているけれど、どれぐらいの運動量が良いのだろう?という話題になり、さっそく調べました。
筑波大学大学院人間総合科学研究科・征矢英昭教授の研究によりますと・・・
心拍数1分間90~100拍程度の低強度運動(速歩き程度)を1日10分、2週間続ければ脳神経が増え、6週間で認知機能自体が向上することが証明されたそうです。
(*エネルギー代謝を増やし、体脂肪を減らすには10分では少ないですが)
認知機能をつかさどるのは脳の海馬という部位で学習や記憶などの役割を持つ部分。
さらに、もう少し強度を高め、心拍数110~130拍程度の中強度であれば(ジョギング程度)、前頭前野にある、情報を統合する役割の46野を活性化させることができるそうです。
46野は分析や判断、集中力に関係している部位でもあり、この部位の活動が低下すると、認知症や鬱病を患う可能性があるそうです。
このあたりの運動までが脳を鍛え、健康にし、認知症の予防に効果があるようです。
これ以上激しい運動は 視床下部という部位を刺激し、ストレスや雑念を感じるようです。
低強度で鍛えられる海馬は、欲望やストレスの脳である視床下部が暴走するのを制御する働きがあり、海馬を鍛えることで、ストレスに強い脳を作ることができる・・・とも考えられるようです。
加えて、
「昔のギリシャでは哲学者が歩きながら議論していましたが、彼らは軽い運動が発想を豊かにすることを知っていたのでしょう。」との記載がありました。
これも調べますと・・・
古代ギリシャの哲学者、ソクラテス、プラトン、アリストテレスらの人びとは、歩きながら、さまざまな議論を闘わせていたことから、逍遥(しょうよう:ぶらぶらと歩くこと)派と呼ばれていたそうです。
日本でも、哲学者、西田幾多郎が、京都の南禅寺あたりから、銀閣寺までの小道を思索にふけりながら散歩していたことから、この小道を「哲学の道」と呼ぶようになった・・・
ぶらぶら歩いて落語の稽古にもエビデンスがあったわけでございます。
と娘に注意されるのですが、落語の稽古をしながらウォーキングをするのが実に心地よいのです。
そろそろ寒くなってきたので、マスクをすると変人は回避できるかな。
心地が良いのは・・・
長時間歩くのも苦痛なくアッというまに時間が過ぎ、歩数が稼げる。
じっとして稽古するより、不思議と落語の覚えが良い。
脳にも足腰にも心地よいのです。
本日、ある打ち合わせで認知症と運動の関係をお話し、運動が脳の働きを良くして、認知症や鬱にも効果があるのは分かっているけれど、どれぐらいの運動量が良いのだろう?という話題になり、さっそく調べました。
筑波大学大学院人間総合科学研究科・征矢英昭教授の研究によりますと・・・
心拍数1分間90~100拍程度の低強度運動(速歩き程度)を1日10分、2週間続ければ脳神経が増え、6週間で認知機能自体が向上することが証明されたそうです。
(*エネルギー代謝を増やし、体脂肪を減らすには10分では少ないですが)
認知機能をつかさどるのは脳の海馬という部位で学習や記憶などの役割を持つ部分。
さらに、もう少し強度を高め、心拍数110~130拍程度の中強度であれば(ジョギング程度)、前頭前野にある、情報を統合する役割の46野を活性化させることができるそうです。
46野は分析や判断、集中力に関係している部位でもあり、この部位の活動が低下すると、認知症や鬱病を患う可能性があるそうです。
このあたりの運動までが脳を鍛え、健康にし、認知症の予防に効果があるようです。
これ以上激しい運動は 視床下部という部位を刺激し、ストレスや雑念を感じるようです。
低強度で鍛えられる海馬は、欲望やストレスの脳である視床下部が暴走するのを制御する働きがあり、海馬を鍛えることで、ストレスに強い脳を作ることができる・・・とも考えられるようです。
加えて、
「昔のギリシャでは哲学者が歩きながら議論していましたが、彼らは軽い運動が発想を豊かにすることを知っていたのでしょう。」との記載がありました。
これも調べますと・・・
古代ギリシャの哲学者、ソクラテス、プラトン、アリストテレスらの人びとは、歩きながら、さまざまな議論を闘わせていたことから、逍遥(しょうよう:ぶらぶらと歩くこと)派と呼ばれていたそうです。
日本でも、哲学者、西田幾多郎が、京都の南禅寺あたりから、銀閣寺までの小道を思索にふけりながら散歩していたことから、この小道を「哲学の道」と呼ぶようになった・・・
ぶらぶら歩いて落語の稽古にもエビデンスがあったわけでございます。











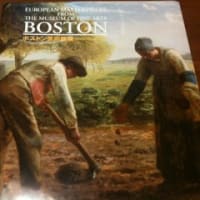







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます