産婦人科診療ガイドライン産科編2011
CQ314 妊娠糖尿病、妊娠時に診断された明らかな糖尿病、 ならびに糖尿病合併妊婦の管理・分娩は?
Answer
1. 早朝空腹時血糖値≦95mg/dL、食前血糖値≦100mg/dL、食後2時間血糖値≦120mg/dLを目標に血糖を調節する。(C)
2. 耐糖能異常妊婦ではまず食事療法を行い、血糖管理できない場合はインスリン療法を行う。(B)
3. 妊娠32週以降は胎児well-beingを適宜NST、BPS(biophysical profile score)などで評価し、問題がある場合は入院管理を行う。(C)
4. 血糖コントロール良好かつ胎児発育や胎児well-beingに問題ない場合、以下のいずれかを行う。(B)
1)40週6日まで自然陣痛発来待機(待機的管理)と41週0日以降の分娩誘発
2)頸管熟化を考慮した37週0日以降の分娩誘発(積極的管理)
5. 遷延分娩時、陣痛促進時、あるいは吸引分娩時には肩甲難産に注意する。(C)
6. 血糖コントロール不良例、糖尿病合併症悪化例や巨大児疑い合併例では分娩時期、分娩法を個別に検討する。(B)
7. 39週未満の選択的帝王切開例、血糖コントロール不良例、あるいは予定日不詳例の帝王切開時には新生児呼吸窮迫症候群に注意する。(B)
8. 糖尿病合併妊婦分娩中においては連続的胎児心拍数モニタリングを行う。(B)
9. 分娩時は母体血糖値70~120mg/dLの正常範囲にコントロールする。(C)
10. 分娩後はインスリン需要量が著明に減少する。インスリン使用例では低血糖に注意し、血糖値をモニターしながらインスリンを減量もしくは中止する。(B)
******
妊娠糖尿病、妊娠時に診断された明らかな糖尿病、ならびに糖尿病合併妊娠の診断については、
を参照されたい。
******
妊娠中の管理
妊娠糖尿病、妊娠時に診断された明らかな糖尿病、ならびに糖尿病合併妊娠のいずれにおいても、食前血糖値≦100mg/dL、食後2時間血糖値≦120mg/dLを目標として、食事療法、運動療法(妊娠中は制限される)を行い、コントロール不良の場合はインスリン療法を行う。妊娠32週までの良好な血糖コントロールを目標とする。
妊娠時に診断された明らかな糖尿病や糖尿病合併妊娠では、SMBG(self-monitoring of blood glucose: 食前、食後2時間、入眠前の1日7回血糖自己測定)を行う。妊娠糖尿病には糖尿病に準した食事療法を行う。
一日の平均血糖値が105mg/dL以上の場合はlarge for gestational age infant(LGA)が増加し、87mg/dL未満であるとsmall for gestational age infant(SGA)が増す。
HbA1c は過去1ヵ月間の血糖調節状態を反映したものであり、HbA1c も管理指標として使用される場合がある。HbA1c を血糖調節指標として加える場合にはHbA1c ≦6.2%(HbA1C(JDS)≦5.8%)が目安となる。
耐糖能異常妊婦に塩酸リトドリンを用いる場合、血糖上昇が起こることがあるので注して使用する。代替薬として硫酸マグネシウムの使用も考慮される。
******
妊娠時の食事療法
普通の体格の妊婦(非妊時BMI<25): 標準体重 x 30 + 200 kcal
肥満妊婦(非妊時BMI≧25): 標準体重 x 30 kcal
標準体重=身長(m) x 身長(m) x 22
高血糖を予防し、血糖の変動を少なくするために4~6分食にする。
食事・運動療法だけで血糖管理が困難な場合は、インスリンを使用する。
******
インスリン療法
妊娠中は特に厳格な血糖コントロールが必要であり、通常のインスリン療法でうまく血糖がコントロールできない場合は、インスリンの基礎量と追加量を補充する強化インスリン療法、すなわちインスリンの頻回注射療法(multiple insulin injection therapy: MIT)やインスリン持続皮下注入療法(continuous subcutaneus insulin infusion therapy: CSII)などが推奨されている。また、食後血糖が高い場合は、分割食にせず超速効型インスリンを用い食後高血糖を是正する方法が普及しつつある。
******
インスリン使用妊婦の分娩時の血糖管理
糖尿病合併妊娠では分娩時に胎児機能不全を示しやすいため、原則として連続胎児モニタリングを行う。
5%ブドウ糖液100mL/時間の輸液を行い、1~3時間おきに血糖値を測定し、血糖を70~120mg/dLに維持する。必要に応じ速効性インスリンを使用する。
インスリン需要量は分娩後急速に低下するので、分娩後は低血糖に十分注意し、適宜インスリンの減量・投与中止を行う。通常、出産直前の1/2~2/3のインスリン量あるいは妊娠前の使用量に戻すことが多い。
******
産褥期の管理
GDM妊婦では、分娩後6~12週で75gOGTTを実施する。また“妊娠時に診断された明らかな糖尿病”妊婦でも分娩後に耐糖能を再評価する。
授乳期間中は、授乳のための付加カロリーとして、妊娠前摂取カロリーに450kcl(肥満者は200kcl)程度加える。
運動については、医師から特に制限指示がなければ、従前どおりとする。
経口糖尿病薬は児に低血糖を引き起こす場合があるので、授乳中は服用しない。
******
糖尿病による母体および児の合併症
******
糖尿病母体児
infant of diabetic mother; IDM
・ 血糖は胎盤を通過するが、インスリンは胎盤を通過しない。
・ 胎児への糖の過剰供給
→胎児膵のβ細胞からのインスリン過剰分泌
→胎児高インスリン血症
******
器官形成期の高インスリン血症 による胎児への影響
・ 心奇形
・ Caudal regression syndrome
・ 無脳症、髄膜瘤
・ 肺低形成
・ 呼吸窮迫症候群(RDS)
・ 口唇裂、口蓋裂
******
妊娠後期の高インスリン血症による影響
・ Fetal macrosomia(巨大児) 心臓、肝臓、筋肉組織への脂肪の過剰蓄積
・ 母体の血管損傷が著しい場合、胎盤血流も障害され、逆に胎児発育不全(FGR)を呈する。
******
出生直前の高インスリン血症 による児への影響
・ 出生後の低血糖症
・ 新生児仮死
・ 出生後の低Ca血症
・ 多血症(高粘稠度症候群、血栓症、 高ビリルビン血症)
****** 問題
糖尿病合併妊娠で正しいのはどれか。2つ選べ。
a. 治療にはインスリンを用いる。
b. 新生児は高血糖をきたしやすい。
c. 妊娠高血圧症候群を合併しやすい。
d. 血糖値の管理は妊娠中期以降に開始する。
e. 食後2時間の血糖値を150mg/dL以下に保つ。
------
正解:a. c.
a. インスリンは胎盤を通過しないため、胎児に影響を及ぼさないことからインスリンを用いる。経口の血糖降下薬は胎盤を通過するため、胎児の低血糖を引き起こす可能性があり使用しない。
b.妊娠中は高血糖に曝されるため、胎児もインスリン分泌が亢進し、分娩後、低血糖をきたしやすい。
c. 母体高血糖により血管障害が生じ、PIHを合併しやすい。
d. 胎児奇形や流産を予防するためには妊娠前からの血糖コントロールが必要である。
e. 妊娠中の合併症を予防するために非妊娠時よりも厳しい血糖コントロールを必要とし、目標血糖値は食前を100mg/dL以下、食後2時間を120mg/dL以下とする。
****** 問題
糖尿病合併妊娠について誤っているのはどれか。
a 2型糖尿病が多い。
b 糖質摂取量は維持する。
c 経口糖尿病薬を用いる。
d 血糖管理で新生児合併症は減少する。
e 早朝空腹時血糖は95mg/dL以下を目標とする。
------
正解:c
a 1型糖尿病(インスリン依存型):5%
2型糖尿病(インスリン非依存型):95%
b 妊娠中は適正な栄養、糖質摂取が必要。
c 妊娠中、経口糖尿薬は禁忌。
d 妊娠中の血糖管理が重要。
e 早朝空腹時血糖値≦95mg/dL、食前血糖値100mg/dL以下、食後2時間の血糖値120mg/dL以下を目標とする。
****** 問題
糖尿病合併妊娠について誤っているのはどれか。
a 妊娠初期は経口血糖降下薬で管理する。
b 妊娠初期の血糖コントロールが不良の場合は先天奇形の頻度が高い。
c 羊水過多症の合併頻度が増える。
d 分娩後はインスリン必要量が減少する。
e 新生児低血糖に注意する。
------
正解:a
経口血糖降下薬は胎盤通過性があり、妊娠初期では催奇形性、妊娠中期以降は胎児低血糖の危険があり、原則禁忌である。血糖のコントロールには胎盤を通過しないインスリンを用いる。
****** 問題
塩酸リトドリンによる有害事象で誤っているのはどれか。1つ選べ。
a 高インスリン血症
b 低カリウム血症
c 高カルシウム血症
d 高アミラーゼ血症
e 血中CPK値の上昇
------
正解:c
塩酸リトドリン
・ 選択的β2刺激薬であるが、いくらかのβ1刺激作用も出現するため、ほとんどの症例で頻脈の訴えがある。
・ 経口:1日15~20mg(1錠5mg)
点滴静注:5%ブドウ糖注射液に溶解し50~200μg/分で投与する。(1A50mg)
・ 副作用
①生理的変化: 不安感、頭痛、嘔気、頻脈、不整脈、嘔吐、発熱、神経過敏、幻覚
②代謝性変化: 高インスリン血症、高血糖、乳酸アシドーシス、低カリウム血症、低カルシウム血症、トランスアミナーゼ上昇、抗利尿作用
③心血管系: 頻脈、肺水腫、低血圧、不整脈、心不全、心筋虚血
④胎児: 頻脈、不整脈、心筋の肥厚、心筋虚血、高血糖
⑤新生児: 高ビリルビン血症、心筋虚血、心筋収縮能低下、低血圧、脳室内出血
⑥その他:
Ⅰ 高アミラーゼ血症 耳下腺腫脹を生じることがある。
Ⅱ 顆粒球減少 顆粒球が1500/μL以下になることがある。投与中は白血球とくに顆粒球を検査する。
Ⅲ 横紋筋融解症 筋肉痛、脱力感、CPK上昇、血中および尿中ミオグロビン上昇を特徴とする。筋緊張性(強直性)ジストロフィー等の筋疾患またはその既往歴のある患者では慎重投与。











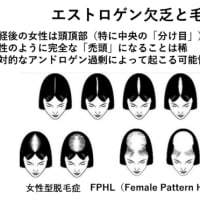


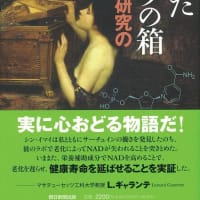
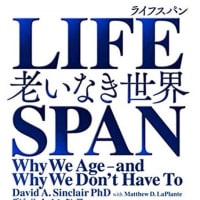
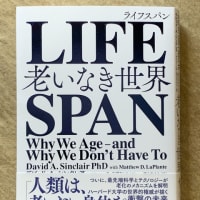
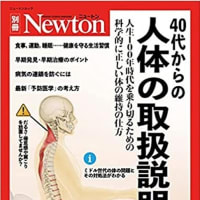
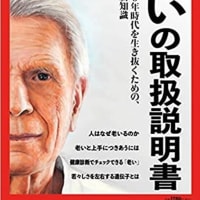
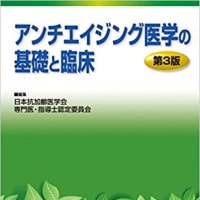

初産の妹が日曜日の夜中に破水してからまだ出産していません。前期破水だと思うのですが、今の時点で子宮口は5cm、胎児3500g。ここまで我慢するのは普通でしょうか?母や妹の旦那さまの「先生が大丈夫って言っているから」との気楽な言葉が心配で少しパニックになっています。ご教示いただければ幸いです。