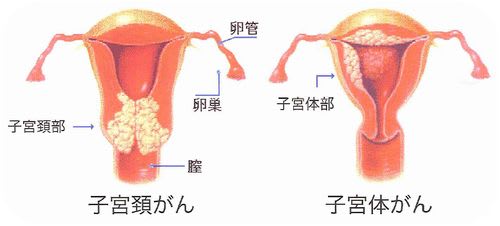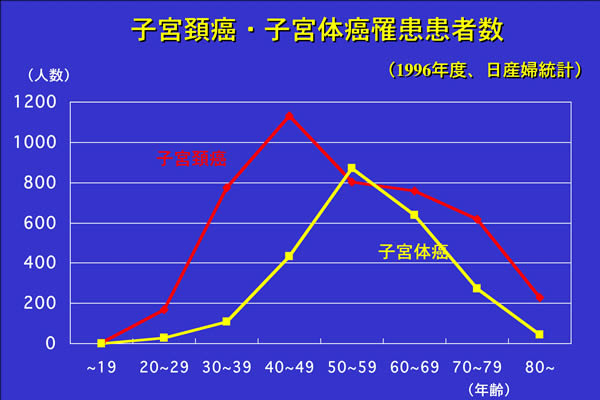コメント(私見):
上田市を中心とした上田小県(うえだ・ちいさがた)地域は、上小(じょうしょう)地域とも呼ばれ、長野県の10医療圏(佐久、上小、諏訪、上諏訪、飯伊、木曽、松本、大北、長野、北信)の一つを形成しています。
この上小医療圏(人口:約22万人、分娩件数:約1800件)は、長野県の東部に位置し、上田市、東御(とうみ)市、青木村、 長和町などで構成されています。
現在、上小医療圏で分娩に対応している医療機関は、上田市産院、上田原レディース&マタニティークリニック、角田産婦人科内科医院の3つの一次施設のみです。ハイリスク妊娠や異常分娩は、信州大付属病院(松本市)、県立こども病院(安曇野市)、佐久総合病院(佐久市)、長野赤十字病院(長野市)、篠ノ井総合病院(長野市)などに紹介されます。分娩経過中に母児が急変したような場合は、救急車でこれらの医療圏外の高次施設に母体搬送されることになり、医療圏内に母体搬送を受け入れる産科二次施設は存在しません。また、産婦人科医は産科だけでなく婦人科疾患にも対応してますから、この地域で、婦人科の急性疾患や良性・悪性疾患で手術などの治療を要する場合は、ほぼ全例で隣接医療圏の施設に紹介されているものと思われます。
2005年、当時の信州大教授が、このまま放置したのではこの地域の周産期医療体制が崩壊する可能性が高いことを危惧され、(2つの大学から派遣されている)長野病院と上田市産院の産婦人科医を集約し、この地域の周産期医療体制を強化する決断をされました。
当時の状況であれば、この2施設のスタッフを集約すれば計6名の産婦人科医からなる非常に強力な産婦人科の二次医療チームを構成することも可能でした。その構想の実現に向けて多くの人が努力しましたが、諸事情により残念ながらその構想は現実化しませんでした。
地域の産婦人科二次医療体制を支えていた多くの人がこの地域から去ってしまった今となっては、この地域に産婦人科二次医療チームを再び創設するには、ベテランから若手を含めて少なくとも4~5人の産婦人科医を日本のどこかから連れてくる必要があります。しかし、現在の全国的な産科医不足の状況では、それは非常に困難だと言わざるを得ません。
当面の現実的な方策としては、隣接医療圏の周産期医療体制をより強化して、地域の周産期医療体制の崩壊がこれ以上拡大しないように努力するしかないのかもしれません。
参考記事:
「バースセンター」構想 上田の母親ら「集い」発足 (信濃毎日新聞)
****** 信濃毎日新聞、2008年12月29日
長野病院 出産受け付け休止から1年
医師確保 続く苦闘
上田市の国立病院機構長野病院が、昭和大学(東京)から産科医の引き揚げを通告され、新たな出産の受け付けを休止して1年。4人いた産科医は順次引き揚げられ、今年8月からは残った1人の医師が婦人科の外来診療のみを担う。病院や市は医師確保に向けた苦闘を続けているが、産科再開の見通しは立っていない。一方で住民側からはリスクの高い「飛び込み出産」を減らす呼び掛けなど、地域医療を支えようとする動きも生まれている。【袮津学】
「自分の周りでも、佐久総合病院(佐久市)まで通っている妊婦がいる。普通だとは思えない」。今月14日、上田市民有志でつくるグループが、地域医療をテーマに開いた意見交換会。参加者から切実な声が上がった。
上田小県地域の医療機関での出産は年間2千件ほど。長野病院は、危険度の高い「ハイリスク出産」を中心にこのうち5百件弱を担ってきた。
同病院が出産受け付けを休止したのは昨年12月3日。休止に伴う影響について明確なデータはない。市内には民間医療機関や市産院があるが、ハイリスクの妊婦は県厚生連の佐久総合や篠ノ井総合病院(長野市)に通うケースも少なくないとされる。
市や市内の病院によると、地域ではこの1年余、妊婦が複数の病院から受け入れを断られ、重篤な事態に陥るなどの事例は表面化していないものの、市民の不安は根強い。
「この1年間で、全国の17大学を訪ね、産科医派遣を直接依頼した」。長野病院の進藤政臣院長は懸命の努力を明かす。しかし、全国的な産科医不足の中で、どの大学も新たに派遣する余裕はない。昭和大は現在1人残る産科医についても、来年4月以降は引き揚げる方針だ。
◇・・・・・・・・・・・・・◇
短期的な解決の糸口が見つからない中で、病院や行政は将来の医師確保につなげようと模索を続けている。
常勤麻酔科医の確保も課題となっている長野病院は今年、病院の「グランドデザイン」をまとめた。現在35人前後の医師数を60人台まで増やすなど、約5年先に目指す病院の姿を示すことで、医師に勤務を呼び掛ける狙いがある。11月に神経内科、12月には外科の医師が1人ずつ増えるなど、明るい兆しも見え始めた。
市は来年1月、医学生や研修医、医師に資金を貸与し、指定する医療機関に一定期間勤めれば、返済を免除する制度を始める。上小の5市町村でつくる上田地域広域連合も、長野病院の産科医や麻酔科医らに研究費を支給する制度を導入する予定だ。ただ、市の大井正行健康福祉部長は「市などが直接できる支援には限界がある」と漏らす。
国は来年度、全国の大学医学部の定員を計693人増員。信大は5人増えて110人となる。大学病院の研修医不足の一因とされる臨床研修制度も見直す方針だが、効果はまだ不透明だ。
「医療を社会インフラととらえ、どの地域でも一定水準を保つため医師を配置する仕組みがないと、地方の病院にとっては非常に厳しい」。進藤院長は訴える。
◇・・・・・・・・・・・・・◇
今年5月、上田市の母親らでつくるネットワーク「パム」は、妊婦に定期的な健診を呼び掛ける名刺大のカードを作った。市医師会と上田薬剤師会の協力で、薬局で妊娠検査薬を買う人に配っている。妊婦健診を受けていないと、危険な兆候があっても備えが取れず、妊婦、産科医双方のリスクが大きく増す。こうした「飛び込み出産」を減らす狙いだ。
11月には、長野病院の地元地区住民らでつくる「西部地区を考える会」が「かかりつけ医をさがせ」と題する住民向けの連続講座を始めた。住民がかかりつけの開業医を持つことは、一部の病院に過大な負担がかかるのを避ける効果があるとされる。
講座では初回、市の健康推進課長らが救急医療の現状などを紹介。その後も、神経内科や皮膚科の医師らを招き、それぞれの分野の病気についての知識を深めている。
産科をめぐる「危機」に地域が向き合ったこの1年。住民自身が当事者として問題を考える動きは広がりつつある。会の代表、鈴木永さん(54)はこう話した。「医療機関や行政に医師確保を求めるだけでなく、住民も一緒にできることを探すきっかけにしたい」
上田小県地域の周産期医療 長野病院の出産受け付け休止後は、上田市産院と同市内の民間の2医療機関が担う。このうち市産院は2005年8月、信大医学部の医師引き揚げ方針に伴い市が廃止を検討したものの、存続を求める運動が起き、06年1月に存続が決定。今年6月には市が移転・建て替え方針も示した。また、隣接する東御市は09年度、市民病院に院内助産院開設を目指している。
(信濃毎日新聞、2008年12月29日)