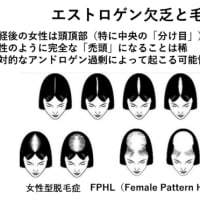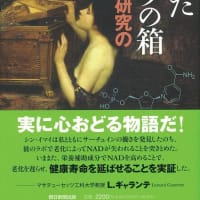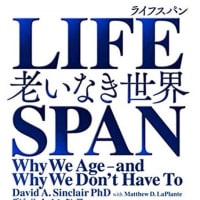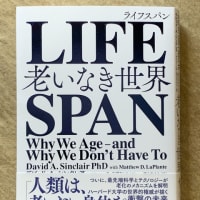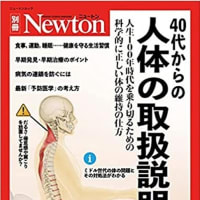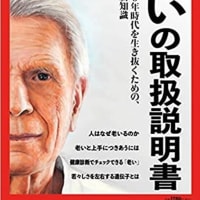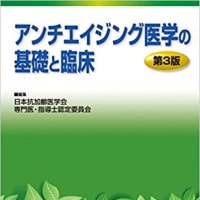コメント(私見):
妊娠している女性でも、突然、脳や心臓や肺などに重大な異変が生じることは決してまれではありません。そういう場合は、産科医だけでは対応できません。例えば脳の疾患であれば神経内科医や脳外科医、心臓の疾患であれば循環器内科医や心臓外科医が迅速に対応する必要があります。まずは、一刻も早く適切な専門医のもとに搬送されることが重要です。
しかし、妊婦の救急疾患の場合は、救急医療の搬送システムではなく、周産期医療の搬送システムで収容する病院を探すことになるので、産科医不在とかNICU満床とかの理由で、次々に母体搬送の受け入れを拒否されて、なかなか搬送先病院が決まらないことも起こり得ます。母体の救命のためには一刻も早く脳外科医のもとに搬送される必要があるのに、たまたま妊娠していたために搬送先病院がスムーズに決まらず、救命のチャンスが失われることもあり得ます。
また、周産期医療の救急疾患には、胎児疾患、新生児疾患、母体疾患がありますが、総合周産期母子医療センターであっても、胎児疾患と新生児疾患への対応を主として、母体疾患には対応できない施設もあります。
周産期医療と救急医療を連携させて、母体搬送をどの病院で受け入れるかをスムーズに決定するシステムを確立する必要があると思います。
****** 毎日新聞、2008年10月27日
妊婦死亡:搬送先検索システムを強化 厚労相が考え示す
舛添要一厚生労働相は27日、妊婦死亡問題に関して「周産期医療と救急医療の連携をどうするかが課題だ」と述べ、インターネットで急患の搬送先を検索するシステムを充実強化させる考えを示した。
東京都の江戸川区医師会の幹部と意見交換した舛添厚労相は、墨東病院が一般救急のER(救急治療室)も併設していた点に触れ「最初にERに運び、脳出血の処置をしながら近隣の産科医を呼んでいれば、どうだったか」と指摘。会談後、報道陣に「受け入れ可能な病院を地図で表示するようなシステムを政府としても考えたい。長期的にメディカルクラーク(医療事務員)を増やし、データ更新も早める」と述べた。【清水健二】
(毎日新聞、2008年10月27日)
****** 毎日新聞、2008年10月27日
妊婦死亡:母子対面できず「悲しい」「改善を」夫が訴え
東京都立墨東病院(墨田区)など8病院に受け入れを断られた後に脳出血で死亡した妊婦(36)の夫(36)が27日、厚生労働省内で会見し「母親と子供が互いの顔を見ることができなかったことが一番悲しい」と、時折声を詰まらせながら語った。病院や行政に対しては「誰かを責めるつもりはない。妻が死をもって浮き彫りにした問題を、力を合わせて改善してほしい」と訴えた。
夫によると、妻が急に激しい頭痛を訴えたのは、自宅で夫婦でDVDを見ていた4日夕。寝かせても一向に症状が治まらないため、救急車でかかりつけの産科医院に運んだ。電話口で搬送を次々と断られる産科医を見て「医療が発達している東京で、なぜ受け入れてくれる病院がないのか、やり切れない思いだった」と振り返る。
墨東病院に運ばれた時は、既に呼び掛けなければ目を開けない状態で、緊急手術の末、男児は助かったが、妻は脳死状態だった。3日後に亡くなる数時間前、病院は目を覚まさない妻の腕に抱かれるように、子供を置いてくれたという。
8年前に結婚した妻は、芯が強く優しい人柄で、初めての出産を前に胎教のCDを買い込み、おなかの子供に前もって決めていた名前で毎日話し掛けた。「将来、同じことが繰り返されないように医療が変わったら『変えたのはお前の母親だ』と言いたい」と語す。
墨東病院は22日の会見で「かかりつけ医から脳出血を疑われる症状は伝わらなかった」と説明したが、夫は「(医師は)私の目の前で『尋常じゃない』と、ちゃんと伝えていた」と強調。それでも「墨東病院の当直医が傷ついて病院を辞め、産科医が減るのは意味がない。今後も産科医としての人生を責任もってまっとうしてほしい」と力を込めた。【清水健二、奥山智己】
(毎日新聞、2008年10月27日)
****** 共同通信、2008年10月27日
救急搬送システム改善を検討 妊婦死亡で厚労相
東京で8つの病院に受け入れを断られ、最終的に搬送された都立墨東病院で妊婦(36)が死亡した問題で、舛添要一厚生労働相は27日、墨東病院の地元医師会の1つ、江戸川区医師会の幹部と意見交換した。
その後、舛添厚労相は記者団に「政府として救急搬送システムの改善を検討したい」と述べた。
医師会との意見交換で厚労相は「拠点病院をつくっても、その後情報収集しないままで、厚労省としても反省している。率直な意見を聴いて前に進みたい」と話した。
これに対し、同医師会の徳永文雄会長は、墨東病院の産科医師数が5年前から定数の9人を下回っていることについて、今年2月、都に対して改善を要望していたことを説明。「都から具体的な回答はまだない」と話した。
また「全国的な医師不足や、医師の養成過程の問題などが複合的に重なって医療が疲弊している」と訴えた。
墨東病院は、24時間態勢で早産などハイリスクの妊婦を受け入れる都立病院唯一の「総合周産期母子医療センター」に指定されている。
(共同通信、2008年10月27日)
****** 共同通信、2008年10月27日
「妻の死無駄にしないで」 妊婦の夫が会見
東京都立墨東病院(墨田区)を含む8病院に受け入れを断られた妊婦(36)が脳内出血で死亡した問題で、妊婦の夫(36)=都内在住=が27日、厚生労働省で記者会見し、「妻の死を無駄にしないでほしい。誰かを責めるとかではなく、妻が死をもって浮き彫りにした問題を、力を合わせて医師、病院、都と国で改善してほしい」と産科をめぐる救急医療の改善を訴えた。
また「当直医を責めないでほしい。医師たちは必死にやってくれた」と話し、当時の医師らの対応を前向きに評価していることを明らかにした。
今回の問題で遺族が公の場で発言するのは初めて。
夫は終始、背筋を真っすぐに伸ばし、机の下で両手を握りしめながら、懸命に妻の最期の様子や今の思いを語り続けた。
突然、妻が異変を訴えたのは4日夕方。2人でDVDを見ていたが、トイレからうめき声が聞こえた気がして、様子を見に行くと妻が嘔吐(おうと)していた。「頭が痛い」。救急車を呼んだ後も痛みを訴えた。
「妻は途中から目が開けられなくなったが、手を強く握ると握り返してきた。わたしが代われるなら代わってあげたかった…」。一瞬沈黙し、涙を浮かべながらその時の様子を振り返った。
赤ちゃんは無事に生まれたが、妻は3日後の7日に息を引き取った。「生と死が同時に起こって正直混乱している。妻が一番誕生を楽しみにしていたのに、息子の顔を見られずに逝ったことが悲しい」と心情を述べた。
(共同通信、2008年10月27日)
****** 産経新聞、2008年10月27日
【妊婦死亡】文科省も病院の調査開始
東京の妊婦死亡問題で、文部科学省の銭谷真美事務次官は27日の会見で、文科省としても受け入れを断った大学病院の聞き取り調査を始めたことを明らかにした。
厚生労働省が8病院の調査をしているが、文科省も所管する大学病院に対し24日から職員を派遣。夜間の勤務形態や、新生児の集中治療室の稼働状況などを確認している。銭谷次官は「情報収集の結果に基づいて、各省が連携して対応していきたい」と述べた。
(産経新聞、2008年10月27日)
****** 産経新聞、2008年10月27日
【妊婦死亡】「医療問題改善につながれば」 遺族が会見
東京都内で今月4日、脳内出血を起こした妊婦(36)が8病院に受け入れを拒否され死亡した問題で、妊婦の夫(36)=都内在住=が27日、厚生労働省で会見し、「妻の死を無駄にしないためにも、死によって浮き彫りになった医療問題などが改善されればいい」と述べた。
夫は「なぜ、文明や医療の発展した都会で、誰も助けてくれないのだろう」と気持ちを吐露。その上で、「かかわってくれたすべての医療関係者は、人として一生懸命やってくれた。責任追及したり、責める気はない」とも話した。
ただ、東京都立墨東病院や都が「受け入れ要請を受けた段階では脳内出血と分からなかった」と主張している点については、受け入れ要請した医院は「『尋常でない頭痛を訴えている』と伝えた」と反論した。
夫によると、体重1800グラムで生まれた男児は、現在2400グラムまでになり、健康という。7日には、病室ですでに脳死状態だった妻の腕に30分ほど抱かれたという。
この問題で、厚生労働省は27日、ハイリスク出産に対応できるよう、医師の配置見直しを検討することを決めた。
(産経新聞、2008年10月27日)
****** 産経新聞、2008年10月27日
【妊婦死亡】別れの間際、わが子胸に 夫、医師らの配慮に感謝
「(医療を)変えたのは母さんだよ」とわが子に伝えたい-。東京都立墨東病院を含む8病院に受け入れを断られた妊婦(36)が死亡した問題。27日に会見した妊婦の夫(36)は、時に言葉を詰まらせ、妻の死を無駄にせぬよう医療の改善を祈り懸命に語り続けた。
最後まで誰かを責めるような言葉はなく、むしろ、口にしたのは感謝の言葉。「医師や看護師は本当に良くしてくれた」。妻は息子を産むと、7日夜に息を引き取った。直前、病室に息子を運んでもらい妻の腕で抱かせてもらえた。親子水入らずの時間はわずか30分。しかし「温かい配慮をいただけた」と振り返る。
妻はベビー用品を用意したり「パパが帰ってきたよ」とおなかに語りかけたり、赤ちゃんを楽しみにしていた。「信頼できる、優しい人だった」。妻との思い出を語る時、少しだけ柔らかな表情になった。
(産経新聞、2008年10月27日)
****** 読売新聞、2008年10月27日
産科医6団体、2月に医師不足改善の要望書を東京都に提出
脳出血を起こした東京都内の妊婦(36)が都立墨東病院(墨田区)など8病院に受け入れを断られ、死亡した問題で、墨東病院周辺の墨田、江東、江戸川の3区にある医師会など地元産科医らでつくる6団体が今年2月、東京都に対し、産科医不足に対応するよう要望書を提出していたことがわかった。
舛添厚生労働相が27日、江戸川区医師会と懇談した際、明らかになった。
要望書は、都病院経営本部と墨東病院あてに提出され、同病院の常勤医が年々減少していることを指摘して、「都民の安心できる周産期体制を準備してほしい」と求めていた。江戸川区医師会の徳永文雄会長は「今回の問題は医師不足から起きた悲劇。要望書に対し、都からいまだに明確な回答がない」と訴えた。
懇談後、舛添厚労相は「どうすれば改善できるか、ERと周産期医療との連携がどうあるべきか検討したい」と述べた。
(読売新聞、2008年10月27日)
****** 読売新聞、2008年10月27日
「妻の死無駄にしないで」夫が会見…妊婦受け入れ拒否
脳出血を起こした東京都内の妊婦(36)が8病院に受け入れを拒否され、出産後に死亡した問題で、女性の夫の会社員(36)が27日夜、厚生労働省で記者会見し、「妻が死をもって浮き彫りにした問題を、医者、病院、都、国が力を合わせ改善してもらいたい。妻の死を無駄にしてほしくない」と、声を詰まらせながら訴えた。
夫によると、今月4日、嘔吐と頭痛を訴えた女性が最初に救急搬送された産婦人科医院で、かかりつけ医は電話で受け入れ先を探す際、「頭が痛い」という情報を伝えていたが、なかなか受け入れてもらえなかったという。その時の心境を夫は「医療の発達した東京で、死にそうに痛がっている人を助けてもらえないのかと無力感を感じた」と振り返った。
女性は、結婚8年で授かった赤ちゃんの誕生を心待ちにし、夫が帰宅すると、「パパ帰ってきたよ」とおなかの赤ちゃんに語りかけていたという。いったんは受け入れを拒否されたものの、女性が帝王切開で長男を出産した都立墨東病院(墨田区)では、入院3日後の7日昼、病院スタッフが病室に長男を運び、意識がない女性の腕に抱かせてくれ、親子水入らずの時を過ごした。女性は、その夜に亡くなった。夫は「医師や看護師には温かい配慮をしてもらった。だれも責める気はなく、裁判を起こすつもりもない。赤ちゃんを安心して産める社会にしてほしい」と話した。
(読売新聞、2008年10月27日)
****** 朝日新聞、2008年10月27日
2月に墨東病院体制改善要望 都に江戸川など3区医師会
脳出血を起こした東京都内の妊婦が8病院から受け入れを断られた後に死亡した問題で、最初に断った都立墨東病院(墨田区)の産科医不足について、地元の3医師会などが今年2月、文書で改善を求めていたことがわかった。
命の危険がある患者が出た場合に同病院に送る墨田、江東、江戸川の3区の医師会と産婦人科医会が、同病院と都病院経営本部あてに出したという。
文書では「難問の多い周産期医療だが、都民が安心できる体制を」と要望。その上で、「毎年(産科医が)減少している間になぜ補充をできなかったのか。書面で次回の会議までに(回答を)お願いしたい」としていた。
一方、舛添厚生労働相は27日午前、江戸川区医師会幹部と懇談し、「総合周産期母子医療センターを守っていくには、医師がいないといけない。地元の医師会の医師や病院、都とも協力して、前向きにやりたい」と述べた。
(朝日新聞、2008年10月27日)
****** 朝日新聞、2008年10月27日
「病院、都、国など力合わせ改善を」妊婦死亡の夫会見
脳出血を起こした妊婦が東京都内の8病院に受け入れを断られた後に死亡した問題で、都内の会社員の夫(36)が27日、厚生労働省で記者会見した。当時の状況を振り返り、「妻が死をもって浮き彫りにしたものを医者、病院、東京都、国が力を合わせて改善してほしい」と訴えた。
男性によると、妻が体調不良を訴えたのは今月4日の夕方だった。DVDを一緒にみていた妻がトイレに行ったが、なかなか戻らず、うめき声がしたため見に行ったところ、嘔吐(おうと)していたという。
かかりつけの五の橋産婦人科(東京都江東区)に電話し、医師の助言で救急車を呼んだ後、頭痛を訴え始めた。同産婦人科に運ばれ、胎児の検査とともに、妻も診察を受けたが、頭の痛みが止まらない。医師は受け入れてくれる病院を探すため、都立墨東病院(墨田区)などに電話をかけ始めた。
次々と断られた。男性は「やりきれない気持ちでいっぱいだった。なぜ文明が発達した都会で、こんなに痛がっているのに助けてくれる人がいないのか」と感じたという。再度の交渉で受け入れることになった墨東病院に着いたのは、異常を訴えてから約1時間半後だった。
男性は「誰も責める気はない。この件で当直医が傷ついて病院を辞めるようなことがあったら意味がない」と話した。
手術後、医師から妻が助かる可能性が極めて低いと説明を受け、帝王切開で無事に男の子が生まれたことを知らされた。「お母さんが安心して赤ちゃんを産めるような社会になってほしい」と声を振り絞った。
(朝日新聞、2008年10月27日)
****** 時事通信、2008年10月27日
「ハイリスク分娩の集約も」=地元医師会と意見交換-舛添厚労相
救急搬送された妊婦が東京都立墨東病院など8病院に受け入れを拒否され死亡した問題で、舛添要一厚生労働相は27日、地元医師会の1つである江戸川区医師会を訪れ、意見交換した。
終了後、厚労相は「周産期医療とER(救急治療室)の連携をどう改善するかが課題だ」と述べた上で、今回のケースのような「ハイリスク分娩(ぶんべん)」に対応可能な施設については「ある地域に再編、集約するなど、いろんなことを考える時期に来ている」との認識を示した。
(時事通信、2008年10月27日)
****** 時事通信、2008年10月27日
安心して産める社会に=「誰も責める気ない」-死亡妊婦の夫が会見
東京都内で8つの病院に救急搬送を断られた妊婦(36)が脳内出血で死亡した問題で、夫の会社員男性(36)が27日夜、厚生労働省で記者会見し、「妻が浮き彫りにしてくれた問題を、力を合わせて改善してほしい。安心して赤ちゃんを産める社会になることを願っている」と訴えた。
夫によると、妊婦特有の高血圧もなく健康だった妻の容体が変わったのは4日夕。掛かり付けの産科医院に着くころには頭痛が激しくなり、医師が搬送先を探している間中「痛い痛い」と言い続けていた。「こんなに医療が発展している東京でどうして受け入れてもらえないのか、やりきれない思いだった」。
約1時間後、都立墨東病院での受け入れが決定。救急車では「痛い」とも言わなくなり、「目を開けろ」と言ったら辛うじて開ける状態。「病院に着くころにはもう開けなかった」と振り返り、声を詰まらせた。
搬送要請で、医師は頭痛が尋常でない状況を伝えていたといい、「伝わらないはずがないと思うが、誰も責める気はない」と夫。最初に断った同病院の当直医について「傷ついて辞めるようなことになったら意味がない。絶対辞めないでほしい」と話した。
さらに脳死状態で3日間を過ごした妻が亡くなる日、保育器に入ったままの赤ちゃんを連れてきて妻の腕に抱かせてくれて、親子水入らずの短い時を過ごしたエピソードを披露。「墨東病院の医師も看護師も本当に良くしてくれた。彼らが傷つかないようにしてほしい」とした。
夫は、医師不足や搬送システムなど浮き彫りになった問題について「のど元過ぎれば忘れるのではなく、具体的な目標を持って改善に向かってほしい。何かが変われば『これを変えたのはおまえのお母さんだよ』と子供に言ってあげたい」と話した。
(時事通信、2008年10月27日)
****** 沖縄タイムス・社説、2008年10月26日
[妊婦受け入れ拒否]
救命優先の産科体制を
脳内出血の症状を示した東京都内の妊婦が、都立墨東病院(墨田区)など八カ所の病院に診療を断られ、出産して三日後に死亡した。
奈良県で昨年と一昨年、受け入れを拒否された妊婦が死亡したり死産したりしたケースがあった。なぜ、その教訓が生かされなかったのか。今回、受け入れを拒否した病院は、いずれも名だたる大病院である。
高度な医療技術が集中している都市部でも、救急医療に十分対応できないという深刻な現実を見せつけられた。
とりわけ、産科医療の切り札といわれる総合周産期母子医療センターに指定されている病院ですら、急患の受け入れを制限せざるを得ない状況に、多くの女性や産科医療関係者の受けた衝撃は大きい。
今回、妊婦のかかりつけ医は墨東病院に受け入れを依頼した際、「頭が痛いと訴え七転八倒している」などと切迫した状況を伝えたと主張。一方、病院側は「下痢や嘔吐の症状から脳内出血との認識はなかった」とし、言い分に食い違いをみせた。
一刻を争う状況の中で、微妙なニュアンスを含め状況を的確に伝えることは、言葉のやりとりだけでは難しいのかもしれない。
実際、医師が治療のかたわらで、急患搬送の手だてを講ずるのには多くの困難と負担を伴う。
しかし、救急医療では、患者の容体を迅速かつ的確に把握することが必要だ。医療機関だけでなく、自治体との連携も含め効果的な対策が求められる。
受け入れを拒否した病院を批判するだけでは現実は改善されない。
墨東病院が受け入れを断ったのは、産科医の当直が研修医一人だけで、対応が難しいと判断したからである。産科医不足は全国的な問題だ。
訴訟になるのを恐れ難しい症例を避けるケースもある。実際に急患を受け入れた場合、十分な対応ができるのか、重い責任を抱えるのは事実だ。二〇〇五年度の厚労省の調査では、総合周産期母子医療センターの約七割が、満床などを理由に地域病院からの母体搬送を断ったという。地域周産期母子医療センターとして認定された病院が、医師不足のため妊婦の緊急搬送受け入れを休止する事例もある。
医療現場からは「重症事例も増えスタッフの負担は大きい」「自分たちが倒れてしまう」など悲鳴にも似た叫びが聞こえる。
妊娠・出産というのは本来、新たな命を宿した幸福感に包まれるものだ。赤ちゃんの健やかな成長と可能性を信じているからこそ、母親は苦しい思いをしながらも一大事業をやり遂げる。
妊婦の受け入れ拒否は、現在、そういう立場にある女性に大きな不安を与えたに違いない。
産科医不足を解消するには、政治・行政が強いリーダーシップを発揮するしかない。当面の対策としては、産科医の待遇改善や女性産科医が子育てをしながら働けるような職場環境づくりが急務だ。
(沖縄タイムス・社説、2008年10月26日)
****** 共同通信、2008年10月26日
常勤医は4人と修正報告へ 岡山医療センター
東京の妊婦死亡問題を受けて厚生労働省が公表した全国の「総合周産期母子医療センター」の常勤の産科医数に関する調査結果について、国立病院機構岡山医療センター(岡山市)の青山興司院長は25日、「国の調査では3人となっているが、正しくは4人」と事実関係を明らかにした。
同センターは24日、共同通信の取材に、「当直は常勤と非常勤の医師に加え、地域の医師に協力を求め計7人態勢でこなしている」と説明したが、青山院長は「実際は常勤医4人に非常勤の医師4人を加え計8人で当直を回している。開業医に応援は頼んでおらず、他の医療機関からも緊急時を除いてはほとんど協力を求めていない」と話している。
(共同通信、2008年10月26日)
****** NHKニュース、2008年10月26日
搬送先探すシステム機能せず
脳内出血を起こした妊娠中の女性が東京都内の8つの病院に受け入れを断られたあと死亡した問題で、搬送先を探すシステムが機能しなかったことが明らかになりましたが、全国の3分の2の自治体でも、このシステムが十分機能していないことがわかりました。
この問題は、東京に住む36歳の妊娠中の女性が今月4日、脳内出血を起こし、都内の8つの病院から次々と受け入れを断られたあと、3日後に死亡したものです。搬送先を早く見つけられるよう全国の都道府県には、新生児の集中治療室のベッドの空き状況などを表示する「周産期医療情報システム」が整備されていますが、今回「空きがある」となっていた3つの病院は、満床などで受け入れられませんでした。こうしたシステムの問題が全国で起きていることが、お産前後の医療を担う拠点病院の協議会が去年9月、システムを整備していた42の都道府県を対象に行った調査でも裏付けられています。それによりますと「システムが機能している」と答えた自治体は12にとどまり、64%に当たる27の自治体が「十分機能していない」と答えました。機能していない理由を尋ねたところ、「情報が更新されない」が最も多く11、次いで「電話のほうが確実」が8、「ベッドがいつも満床でシステムの意味がない」が3で、運用がおろそかになり、システムへの信頼が失われていることがわかりました。救急医療に詳しい杏林大学医学部の島崎修次教授は「1日2回の更新ではリアルタイムといえないが、忙しい医師に頻繁に入力をさせるのは困難だ。こうした業務を行うコーディネーターを導入することなどが必要だ」と話しています。
(NHKニュース、2008年10月26日)