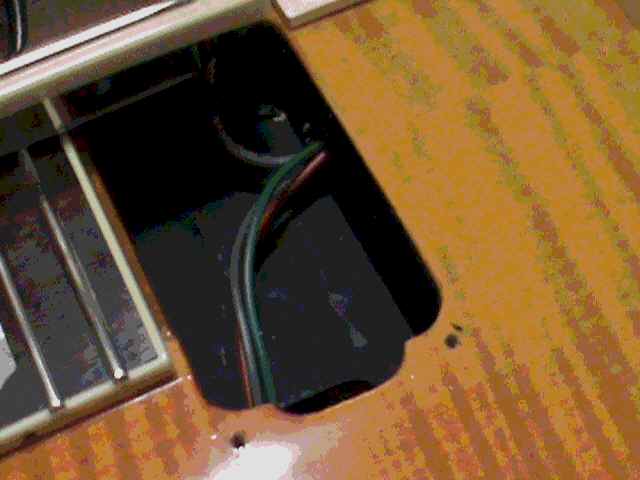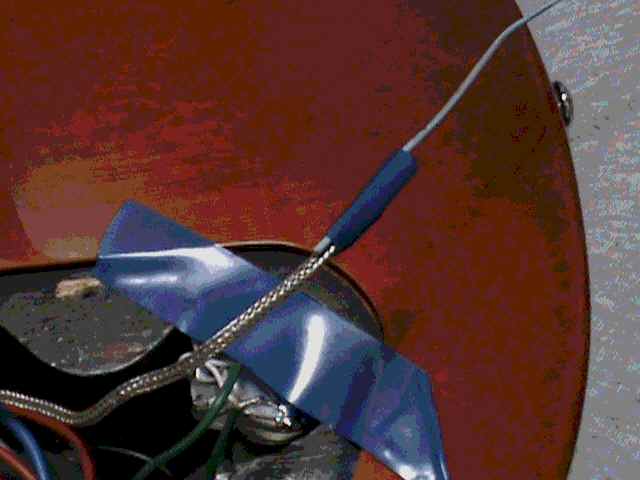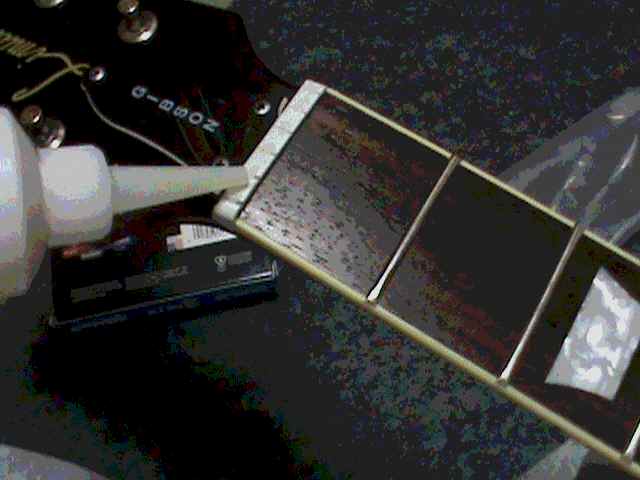リアピックアップも購入したのだ

交換ピックアップの大定番であるJBタイプなのだ
JBとはJeff Beckの略なのだ
ジェフベックがレスポールを使用していた頃に氏の要望を
取り入れて開発されたピックアップのコピーという位置づけなのだ
ダンカン社が開発者であるセス・ラバー氏の監修の元に綿密にワイアリングされているのだ
”迷ったらJB買っとけ・・”
というのはギター弾きにはお約束なのだ

”交換ピックアップ≒ハイパワーピックアップ・・”
と思っている人も多いようだが実は様々なのだ
むしろ非力を売りにしているような製品も少なくないのだ
非力なピックアップに何を求めるのか?
ピッキングのニュアンスに追従する繊細さや出音の感じなのだ
このJBモデルもかなり繊細なのだ
ハイパワーというわけではないが歪み系のエフェクト乗りも悪くない
前回、ご紹介したフロントは59モデルというフロント系の定番なのだ

ギブソンのPAF(ピックアップの名前)を忠実に再現したモデルなのだ
こちらも非力系なのだ
どちらも鳴らすことは非常に難しいピックアップなのだ
しかしながら、自在にコントロールできるようになれば目から鱗の感動が待っているのだ
つまりは定番とはいいながらもハードルが高いピックアップなのだ
ダンカン製の場合、この二つのピックアップを『基準』に他の製品の開発が行われていると言われているのだ
ハイパワーを売りにしているピックアップで刻んだリフは気持ちいいが・・・
テクが向上してくると飽きてしまうのだ
少なくとも私の場合はそうなのだ
素の音でもコンプレッサーを強くかけたような独特の音なのだ
これは他のメーカーにもいえるのだ
私のアイバニーズに搭載されているディマジオはどちらかというとそんな傾向が見られるのだ
秀逸なのはボリュームやトーンを絞った時に激的に音色を変化させる味付けなのだ
まぁ、このようにピックアップにも用途や個性があるという事なのだ
現状の音に満足しているならば、あえて交換する必要はない気がする
むしろ、バランスを考えれば現状維持が最良だと思うのだ
ピックアップの交換には『理由』が必要なのだ
私の場合にはネガな部分の補強という意味合いが強いのだ
私が購入したグラスのレスポールはリアはショボイながらもそこそこ使える音だった
しかしながら、フロントはモコモコとした音でまったく弾く気が起こらない
ポットの抵抗値を変更してみようかな?とも考えたのだが・・
元のクオリティを考えれば徒労に終わる気がしたのだ
そんな理由からフロントを先に交換したのだ
「いい音だね♪ 使えるギターになったぜ~!」
思った以上にボディの鳴りが良いのだ
トーカイのようなワンピースの高級マホガニーとは異なる
しかしながら陳腐でもないのだ
長年に渡り、安ギターを弾いてきた成果が表れたのだ
言葉では上手く表現できないが・・・
ボディや材の良し悪しが分かるようになってきたのだ
そんな流れからリアの購入に踏み切ったのだ
”踏み切る・・”
というほど高額な買い物ではないが・・・
読者の皆さんはボディが無いギターをご存じだろうか?
いわゆるトラベルギターというジャンルに分類されているのだ
ネックに弦が張ってあるようなギターなのだ
持ち運びには便利だがボディ鳴りは皆無なのだ
このようなギターにダンカンのようなピックアップを載せた図をイメージしていただきたい
まったくもってピックアップの良さが活きないのだ
先にも述べたようにピックアップの良さを引き出すのはボディ(ネックも含む)なのだ
『このギターは値段の割に良く鳴るなぁ・・』
という場合には自分の耳を信じてピックアップ交換にチャレンジしていただきたい
「ダメなギターだけどピックアップの交換でなんとかなるかな?」
という場合には潔く次のギターの購入を考えるべきだと思う
この辺りの判断は自分自身なのだ
ちなみに高級ギターに感覚が麻痺しているような友人や楽器店の店員さんに相談しても意味がない
「安ギターなんか捨てちゃえよ~ これにダンカンを積むの?」
「金をドブに捨てるみたいなもんだぜ~ お前、アホか・・?」
”高級ギター≒良いギター・・”
だと信じて疑わない人々の意見は参考にはならない
他人の意見も参考にならない
自分の感覚と耳にも自信がない・・
という場合には微妙なのだ
まぁ、ルックスが変わるだけでもモチベーションがアップする事もある
そんな場合にはルックス重視のジャンクをハンダの練習として取り付けても良いと思うのだ
もちろん、音質の向上はまったく見込めない
実は私も最初はルックス重視の『飾り的ギター』を目指していたのだ
秋葉原辺りのパーツショップでジャンクなピックアップはいくらでも手に入るのだ
メーカー製以外の製品を実物も見ないでネットで購入する勇気はない
「音が出ないんだけど・・交換ってできます?」
「お客さんの配線ミスじゃないですか・・?」
こんな悪いイメージが先行してしまうのだ
離島に住んでいるならばいざ知らず・・
自分の目で確認すべきだと思う
一時はネット購入にハマっていた私の友人達も最近では実際の買い物に移行し始めているらしい
「何かと問題(画像と実物のイメージが違うなど・・)があるんだよなぁ・・」
「多少は安いけど、実物を見ながら買い物したほうが楽しいし・・」
話が多少脱線してしまったが・・
実際に完成したギターの図をご覧いただきたい

リアだけにダンカンの文字が刻印されているのだ

ピックガードが微妙なのだ
金属のカバーがついている場合には迷わずピックガードを残すが・・
オープンタイプの場合には微妙なのだ
レスポールのカリスマであるスラッシュのモデルが参考になる

ガードを外した図なのだ

まぁ、どうでも良いのだが・・
色々と試しているのだ

エピフォンの時にはピックガードを捨ててしまったが今回は保管しているのだ

ジェフベックもレスポールを使っていた事は有名な話だが・・

オープンタイプのピックアップにピックガード付きというのがお約束のスタイルなのだ

これもなかなかカッコいいと思う
アリアもダンカンを積んでいるのだが今回のJBとは全く異なるピックアップなのだ

弾き比べてみると違いは歴然なのだ

かなり楽しいのだ

レスポールの弾き比べもなかなか奥深い

トーカイにはピックアップの交換だけでは到達できない極みを感じる
楽器店のお兄さんが良く言うセリフがある
「形は似ていますけど・・全く別物ですよ」
レギュラーラインのレスポールとカスタムショップのレスポールの比較なのだ
私も何度か試奏させてもらったことがある
材の構成などスペック的には大きな違いは感じられないが・・
何故だか実際の音の深みが異なるように感じられるのだ
ボディ材の重要性を痛感しているのだ
最近はすっかりレスポールにハマってしまいネット検索などでも
改造の参考にすべく色々なレスポールを調べているのだ
読者の皆さんはデュアンオールマンというギタリストをご存じだろうか?

若い世代の人にはあまり馴染みがないといえる
24歳という若さでこの世を去ってしまったのだ
ジミヘンも20代だった・・・・
才能ある人は短命なのだ
『いとしのレイラ』でのクラプトンとの共演がもっとも有名なギグだと思う
実はイントロのあの有名なリフはオールマンが作ったといわれているのだ
真実は分からないが・・・

オールマンの愛用のレスポールのコピーなのだ

カスタムショップ製なのだ
100万円近い値段なのだ

何本か年代の異なるレスポールを使用していたらしい
59年制のレスポールに一目ぼれをして所有のゴールドトップとマーシャルさらに追金で手に入れたという事だ
当時は現在のようにレスポールの価値が異常に高騰してはいなかったのだ
「俺のギターと交換しないか?」
というのは当時は良く見られた光景らしい
クラプトンが使っていたレスポールを気に入ったジョージハリスンが買い取ったというのも有名な話なのだ
”伝説のルーシー・・”
脱線してしまったが・・・
とりあえず、フロント&リアのピックアップ交換が完了したのだ
ピックアップのリニューアルの流れで細部にも拘ってみたのだ

ノーマルのトグルスイッチのノブの色が安っぽいので『アンバー』に交換してみたのだ

トーカイと同じ色にしてみた
ギブソンもカスタムショップ製に多く採用されているノブなのだ
どうでも良い部分だが・・高級感が増した気がするのだ
ボリューム&トーンのツマミもアンバーなのでイイ感じなのだ

形や色を変えるだけでもかなり印象が異なるのだ
色々とツマミを持っているので他のギターも気分で変更したりして遊んでいるのだ

ちなみにオープンタイプのピックアップに合わせてメタルノブという組み合わせも悪くない

まぁ、ルックスはそこそこイイ感じだが・・・
数字が見えないのは実戦向きではないようだ
メタルノブはワンボリューム&ワントーンのギター限定の仕様だといえる
余談だが・・
レスポールのピックアップ交換の流れで他のギターの『立ち位置』も見直しているのだ
アリアも変則チューニング用にカスタムしてみたのだ

以前はバネが3本だったのだがペグの動きに敏感過ぎるのだ
バネを5本にしたことでペグの動きに影響し難くなったのだ

使用感はかなり重いのだ
しばらく、この状態で使っていたのだが・・・
最終的には元に戻してしまったのだ
性格的に思った事は実践してみないと気が済まないのだ
これは昔から変わっていないのだ
元の状態といってもバネを一新したのだ

トレモロのバネも長年の使用で金属疲労を起こすようだ

以前はトレモロを使うたびに異音が発生していたのだ
何にでも言えるが・・
異音は何かの前兆なのだ
症状が重くなる前に対処することが大切なのだ
「連休辺りに『音源』をお届けできれば良いなぁ・・」と考えているのだ
あとは曲作りをする私のモチベーションだけなのだ
最近はギターのメンテだけで息切れ?してしまう事も多々あるのだ
年齢だろうか?
”良いギターと良い環境・・・”
条件は整っているのだが・・・
最近の私は楽器店のお兄さん同様、『コレクター』になりつつあるのだ
それはそれで良い気もするが・・・

交換ピックアップの大定番であるJBタイプなのだ
JBとはJeff Beckの略なのだ
ジェフベックがレスポールを使用していた頃に氏の要望を
取り入れて開発されたピックアップのコピーという位置づけなのだ
ダンカン社が開発者であるセス・ラバー氏の監修の元に綿密にワイアリングされているのだ
”迷ったらJB買っとけ・・”
というのはギター弾きにはお約束なのだ

”交換ピックアップ≒ハイパワーピックアップ・・”
と思っている人も多いようだが実は様々なのだ
むしろ非力を売りにしているような製品も少なくないのだ
非力なピックアップに何を求めるのか?
ピッキングのニュアンスに追従する繊細さや出音の感じなのだ
このJBモデルもかなり繊細なのだ
ハイパワーというわけではないが歪み系のエフェクト乗りも悪くない
前回、ご紹介したフロントは59モデルというフロント系の定番なのだ

ギブソンのPAF(ピックアップの名前)を忠実に再現したモデルなのだ
こちらも非力系なのだ
どちらも鳴らすことは非常に難しいピックアップなのだ
しかしながら、自在にコントロールできるようになれば目から鱗の感動が待っているのだ
つまりは定番とはいいながらもハードルが高いピックアップなのだ
ダンカン製の場合、この二つのピックアップを『基準』に他の製品の開発が行われていると言われているのだ
ハイパワーを売りにしているピックアップで刻んだリフは気持ちいいが・・・
テクが向上してくると飽きてしまうのだ
少なくとも私の場合はそうなのだ
素の音でもコンプレッサーを強くかけたような独特の音なのだ
これは他のメーカーにもいえるのだ
私のアイバニーズに搭載されているディマジオはどちらかというとそんな傾向が見られるのだ
秀逸なのはボリュームやトーンを絞った時に激的に音色を変化させる味付けなのだ
まぁ、このようにピックアップにも用途や個性があるという事なのだ
現状の音に満足しているならば、あえて交換する必要はない気がする
むしろ、バランスを考えれば現状維持が最良だと思うのだ
ピックアップの交換には『理由』が必要なのだ
私の場合にはネガな部分の補強という意味合いが強いのだ
私が購入したグラスのレスポールはリアはショボイながらもそこそこ使える音だった
しかしながら、フロントはモコモコとした音でまったく弾く気が起こらない
ポットの抵抗値を変更してみようかな?とも考えたのだが・・
元のクオリティを考えれば徒労に終わる気がしたのだ
そんな理由からフロントを先に交換したのだ
「いい音だね♪ 使えるギターになったぜ~!」
思った以上にボディの鳴りが良いのだ
トーカイのようなワンピースの高級マホガニーとは異なる
しかしながら陳腐でもないのだ
長年に渡り、安ギターを弾いてきた成果が表れたのだ
言葉では上手く表現できないが・・・
ボディや材の良し悪しが分かるようになってきたのだ
そんな流れからリアの購入に踏み切ったのだ
”踏み切る・・”
というほど高額な買い物ではないが・・・
読者の皆さんはボディが無いギターをご存じだろうか?
いわゆるトラベルギターというジャンルに分類されているのだ
ネックに弦が張ってあるようなギターなのだ
持ち運びには便利だがボディ鳴りは皆無なのだ
このようなギターにダンカンのようなピックアップを載せた図をイメージしていただきたい
まったくもってピックアップの良さが活きないのだ
先にも述べたようにピックアップの良さを引き出すのはボディ(ネックも含む)なのだ
『このギターは値段の割に良く鳴るなぁ・・』
という場合には自分の耳を信じてピックアップ交換にチャレンジしていただきたい
「ダメなギターだけどピックアップの交換でなんとかなるかな?」
という場合には潔く次のギターの購入を考えるべきだと思う
この辺りの判断は自分自身なのだ
ちなみに高級ギターに感覚が麻痺しているような友人や楽器店の店員さんに相談しても意味がない
「安ギターなんか捨てちゃえよ~ これにダンカンを積むの?」
「金をドブに捨てるみたいなもんだぜ~ お前、アホか・・?」
”高級ギター≒良いギター・・”
だと信じて疑わない人々の意見は参考にはならない
他人の意見も参考にならない
自分の感覚と耳にも自信がない・・
という場合には微妙なのだ
まぁ、ルックスが変わるだけでもモチベーションがアップする事もある
そんな場合にはルックス重視のジャンクをハンダの練習として取り付けても良いと思うのだ
もちろん、音質の向上はまったく見込めない
実は私も最初はルックス重視の『飾り的ギター』を目指していたのだ
秋葉原辺りのパーツショップでジャンクなピックアップはいくらでも手に入るのだ
メーカー製以外の製品を実物も見ないでネットで購入する勇気はない
「音が出ないんだけど・・交換ってできます?」
「お客さんの配線ミスじゃないですか・・?」
こんな悪いイメージが先行してしまうのだ
離島に住んでいるならばいざ知らず・・
自分の目で確認すべきだと思う
一時はネット購入にハマっていた私の友人達も最近では実際の買い物に移行し始めているらしい
「何かと問題(画像と実物のイメージが違うなど・・)があるんだよなぁ・・」
「多少は安いけど、実物を見ながら買い物したほうが楽しいし・・」
話が多少脱線してしまったが・・
実際に完成したギターの図をご覧いただきたい

リアだけにダンカンの文字が刻印されているのだ

ピックガードが微妙なのだ
金属のカバーがついている場合には迷わずピックガードを残すが・・
オープンタイプの場合には微妙なのだ
レスポールのカリスマであるスラッシュのモデルが参考になる

ガードを外した図なのだ

まぁ、どうでも良いのだが・・
色々と試しているのだ

エピフォンの時にはピックガードを捨ててしまったが今回は保管しているのだ

ジェフベックもレスポールを使っていた事は有名な話だが・・

オープンタイプのピックアップにピックガード付きというのがお約束のスタイルなのだ

これもなかなかカッコいいと思う
アリアもダンカンを積んでいるのだが今回のJBとは全く異なるピックアップなのだ

弾き比べてみると違いは歴然なのだ

かなり楽しいのだ


レスポールの弾き比べもなかなか奥深い

トーカイにはピックアップの交換だけでは到達できない極みを感じる
楽器店のお兄さんが良く言うセリフがある
「形は似ていますけど・・全く別物ですよ」
レギュラーラインのレスポールとカスタムショップのレスポールの比較なのだ
私も何度か試奏させてもらったことがある
材の構成などスペック的には大きな違いは感じられないが・・
何故だか実際の音の深みが異なるように感じられるのだ
ボディ材の重要性を痛感しているのだ
最近はすっかりレスポールにハマってしまいネット検索などでも
改造の参考にすべく色々なレスポールを調べているのだ
読者の皆さんはデュアンオールマンというギタリストをご存じだろうか?

若い世代の人にはあまり馴染みがないといえる
24歳という若さでこの世を去ってしまったのだ
ジミヘンも20代だった・・・・
才能ある人は短命なのだ
『いとしのレイラ』でのクラプトンとの共演がもっとも有名なギグだと思う
実はイントロのあの有名なリフはオールマンが作ったといわれているのだ
真実は分からないが・・・

オールマンの愛用のレスポールのコピーなのだ

カスタムショップ製なのだ
100万円近い値段なのだ

何本か年代の異なるレスポールを使用していたらしい
59年制のレスポールに一目ぼれをして所有のゴールドトップとマーシャルさらに追金で手に入れたという事だ
当時は現在のようにレスポールの価値が異常に高騰してはいなかったのだ
「俺のギターと交換しないか?」
というのは当時は良く見られた光景らしい
クラプトンが使っていたレスポールを気に入ったジョージハリスンが買い取ったというのも有名な話なのだ
”伝説のルーシー・・”
脱線してしまったが・・・
とりあえず、フロント&リアのピックアップ交換が完了したのだ
ピックアップのリニューアルの流れで細部にも拘ってみたのだ

ノーマルのトグルスイッチのノブの色が安っぽいので『アンバー』に交換してみたのだ

トーカイと同じ色にしてみた
ギブソンもカスタムショップ製に多く採用されているノブなのだ
どうでも良い部分だが・・高級感が増した気がするのだ
ボリューム&トーンのツマミもアンバーなのでイイ感じなのだ

形や色を変えるだけでもかなり印象が異なるのだ
色々とツマミを持っているので他のギターも気分で変更したりして遊んでいるのだ

ちなみにオープンタイプのピックアップに合わせてメタルノブという組み合わせも悪くない

まぁ、ルックスはそこそこイイ感じだが・・・
数字が見えないのは実戦向きではないようだ
メタルノブはワンボリューム&ワントーンのギター限定の仕様だといえる
余談だが・・
レスポールのピックアップ交換の流れで他のギターの『立ち位置』も見直しているのだ
アリアも変則チューニング用にカスタムしてみたのだ

以前はバネが3本だったのだがペグの動きに敏感過ぎるのだ
バネを5本にしたことでペグの動きに影響し難くなったのだ

使用感はかなり重いのだ

しばらく、この状態で使っていたのだが・・・
最終的には元に戻してしまったのだ
性格的に思った事は実践してみないと気が済まないのだ
これは昔から変わっていないのだ
元の状態といってもバネを一新したのだ

トレモロのバネも長年の使用で金属疲労を起こすようだ

以前はトレモロを使うたびに異音が発生していたのだ
何にでも言えるが・・
異音は何かの前兆なのだ
症状が重くなる前に対処することが大切なのだ
「連休辺りに『音源』をお届けできれば良いなぁ・・」と考えているのだ
あとは曲作りをする私のモチベーションだけなのだ

最近はギターのメンテだけで息切れ?してしまう事も多々あるのだ
年齢だろうか?
”良いギターと良い環境・・・”
条件は整っているのだが・・・
最近の私は楽器店のお兄さん同様、『コレクター』になりつつあるのだ
それはそれで良い気もするが・・・