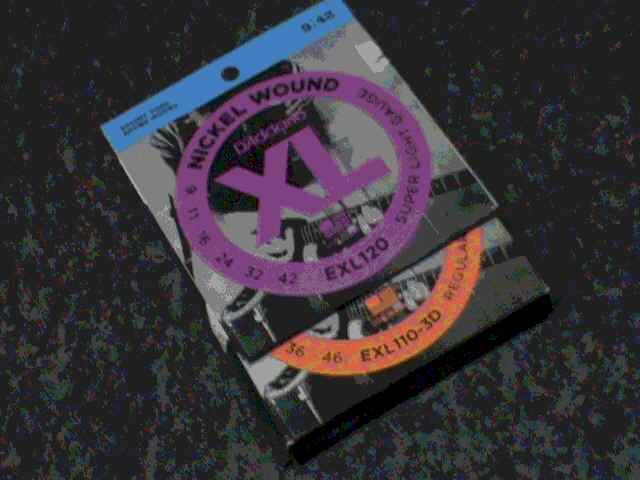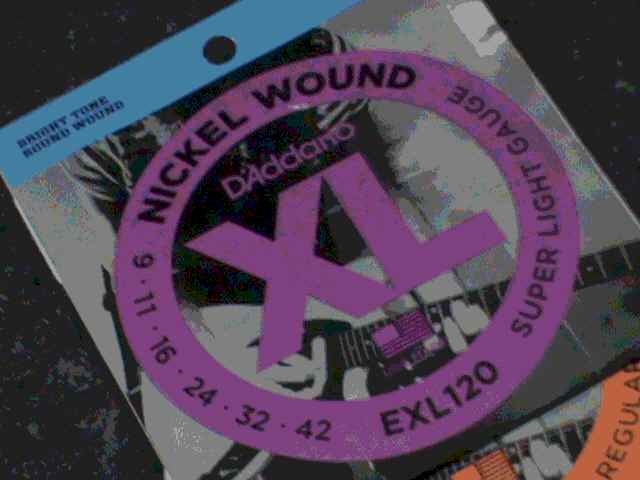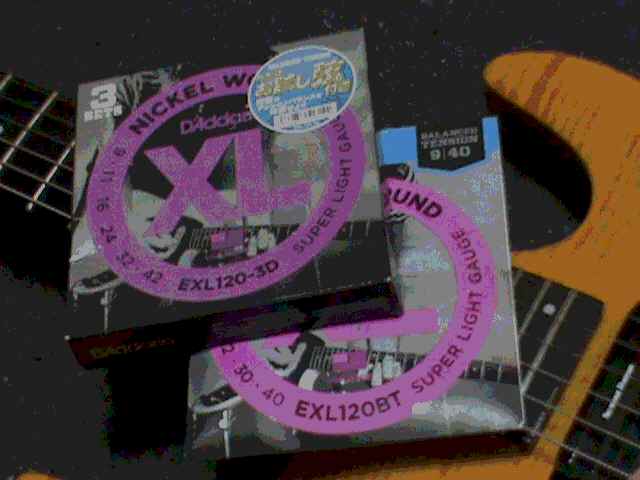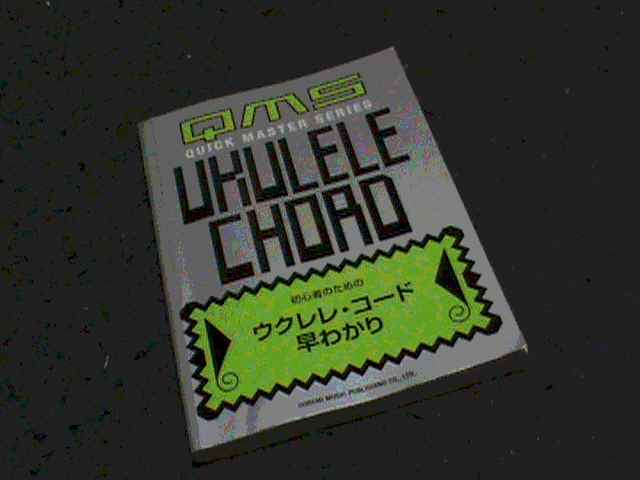最近は気になる商品を手当たり次第に買い漁っているのだ
無駄遣いは重々承知しているのだ
自分で試さなくては気が済まない性質なのだ
常連読者の方もご存じだと思う
世の中には上手がいるのもなのだ
いつもの楽器店のお兄さんが先に買って(使って)いる事が多いのだ
レジだけを打っているような何処かのヤル気無い店員さんとは違うのだ
非常に勉強熱心なのだ
「お客さんさんから質問された時に答えられないのって恥ずかしいですから・・」
楽器店の店員さんでも展示しているすべての商品を試せるわけではないのだ
もちろんお兄さんも何千点とある商品のすべてを試しているわけではないのだ
ニーズというか・・巷で人気がある商品が中心のようだ
さらに個人的に興味ある商品が其処に加わるという感じらしい
以前にブログでご紹介したと思うが・・・
遊び用として数ヶ月前にVOXのヘッドフォンアンプを購入したのだ
実は思ったほど出番がなかったのだ
自宅ではGT-100を中心にギターを弾いているし外では実機のアンプを鳴らしているのだ
簡易的に録音や練習をするならばBR-80が便利なのだ

値段の割にリアルな音色は認めるが私には不要な品だったのだ
実際に音色をお届けするにも非常に手間がかかるのだ
読者の皆さんも特に関心がないと思う
むしろ多機能&高音質なGT-100の音源に興味があると思うのだ
いつものように仕事帰りに楽器店に立ち寄ったのだ
上記のような話をしているとお兄さんがある商品を勧めてきたのだ
「キャビネットを接続したら面白いですよ~」
「ヘッドフォンとは違う感じですよ」

以前から興味があったので購入してみたのだ
『オモチャじゃないのかな?』
と心の中で思っていたのだ
楽器店のお兄さんが続けるのだ
「勿論、音量は出ないですよ でも、音色は捨てたもんじゃないですよ」
「僕も自宅練習で使っているんですよ 見た目も可愛いし・・」
まぁ、音が悪くてもインテリアに良いと考えたのだ

まさにマーシャルの段積みアンプの感じなのだ
キャビネットの質感も悪くない
キャビネットのインプットにミニアンプのジャックを接続するのだ

さらにキャビネットのケーブルをミニアンプのフォーンジャックに接続するのだ
後はキャビネット側にギターを差し込むだけなのだ

いたって構造は単純なのだがちょっと面白い電気の流れなのだ
読者の皆さんも頭を整理して少し考えていただきたい
単なるスピーカーではない事がお分かりいただけると思う
キャビネット単体では音は出ないのだ
音楽プレーヤーなどに接続するミニスピーカーとは区別したい
ミニアンプ側は単四電池一本なのだ
キャビネット側は9V電池一個なのだ
小さいが一応パワーアンプになっているのがミソなのだ
発売当初は種類も少なかったが最近はランナップも増えたのだ
非常に人気がある商品なのだ
ちなみに私はマーシャル風?のアンプを使っているのだ
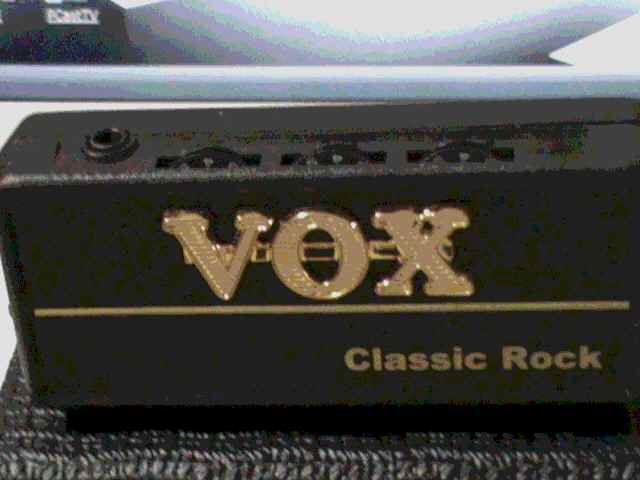
ゲイン、トーン、ボリュームの3個なのだ
ボリュームが実機のマスターに相当する役割を持っているのだ

実機のマーシャルの特徴に一つにあの独特のエッジ感がある
かなり忠実に再現されているのだ
ネットには文句を言う人も多いが・・
値段を考えればかなり優秀だといえるのだ
ちなみに興味ある方は参考にしていただきたい↓
『VOXミニアンプ』
実際に録音する方法は2通りなのだ
私の場合、マイクで収録する方法とBR-80のコンデンサーマイクを使う方法が考えられる

BR-80の内蔵マイクはかなり感度が良いのだ
良過ぎて困る事も多いのだ
ウクレレなどの録音の際に外部の音も拾ってしまうのだ
実機のアンプにマイクを向ける時にも角度や距離が重要なのだ
一度は耳にしたことがあると思う
BR-80で録音する場合にもキャビネットとの距離や角度でかなり結果が異なるのだ
「リアルだね~ 意外に面白いかも?」
「オケに混ぜたらどんな感じになるのかな?」
興味は尽きないのだ
ちなみに私のVOXアンプはマーシャルの素の音なのだ
ディレイもリバーブも付いていないのだ
味気ないと言えば味気ない・・のだ
BR-80を使えばリバーブを加えた音をモニター(実際に録音も)する事が可能なのだ
先がけになってしまうがその他のエフェクトをかけることも可能なのだ
モニターの際にはヘッドフォンを使う事になるのだ
「これじゃGT-100の時と一緒だなぁ・・」
そうなのだ
アンプの『空気感』を再現する事が可能にはなるが実際に聴く音はヘッドフォンなのだ
ちょっとした工夫で解決したのだ
先に述べたようにアンプとキャビネットの接続は少々特殊なのだ
VOXミニアンプの代替えとしてBR-80を利用するアイディアが浮かんだのだ
実際の接続がコチラなのだ

音の流れは一緒なのだ
BR-80がアンプヘッドの役割を担うのだ
当然ながらエフェクトの挿入も自在なのだ
ちなみにこの状態では録音はできないのだ
実際の音はどうか?
「伸びるね~♪ 音もクリアだし気持ちいいなぁ・・」
最高なのだ
キャビネットにギターを近づけると実機さながらにフィードバックするのだ
まさに小さなマーシャルなのだ
内蔵のドラムを同時に鳴らす事も可能なのだ
卓上の飾りとしてもかなり秀逸だと思う

ミニアンプ単体の購入(使用)よりもキャビネットとの接続がお薦めなのだ
実機さながらにキャビネットの方が安いのだ
同時に購入となると学生さんには少し高いと感じられるかも?
それでも小型アンプを購入するよりも安いのだ
まぁ、素直に小型アンプを購入すれば多彩な機能が使えるが・・・
すでにBR-80やその他の機材を色々と持っている私の場合にはベストバイの選択だったのだ
小型ながら十分にアンプの質感を再現している点には脱帽なのだ
プロのお兄さんが気にっている理由が分かったのだ
自宅でのヘッドフォン環境も捨て難いが・・
時にはアンプで弾きたくなる事もあるのだ
そんなニーズには最適だと思うのだ
オベーションのウクレレに引き続き良い買い物をしたと思っているのだ
満足度が高ければそれは無駄遣いではないのだ
学業に仕事にと精が出るのも趣味あってこそだと考えているのだ
勉強もダメ、仕事もダメ、趣味も無い・・・
というのが一番つまらない人生なのだ
読者の皆さんは如何だろうか?
ギターや音楽に興味が湧いてきたという方も多いのでは?
良い事だと思う
ダラダラとyoutubeの音楽サイトを徘徊?している人も多いと聞いている
他人のペナペナの演奏を聴いているくらいなら自分で演奏した方が何倍も有意義なのだ
ネットのレビューや酷評をダラダラと読んでいるくらいなら自分で試した方が早いのだ
何処の誰だか分からない人々意見に一喜一憂するよりも自分自身の感性を信じるべきなのだ
長くなりそうなのでこの辺で・・・
実際の音源などもご紹介する予定なのだ
私の音源を聴く前に買ってしまうのも手だと思う
如何だろうか?

かなり遊べるアイテムだと思う
無駄遣いは重々承知しているのだ

自分で試さなくては気が済まない性質なのだ
常連読者の方もご存じだと思う
世の中には上手がいるのもなのだ
いつもの楽器店のお兄さんが先に買って(使って)いる事が多いのだ
レジだけを打っているような何処かのヤル気無い店員さんとは違うのだ
非常に勉強熱心なのだ
「お客さんさんから質問された時に答えられないのって恥ずかしいですから・・」
楽器店の店員さんでも展示しているすべての商品を試せるわけではないのだ
もちろんお兄さんも何千点とある商品のすべてを試しているわけではないのだ
ニーズというか・・巷で人気がある商品が中心のようだ
さらに個人的に興味ある商品が其処に加わるという感じらしい
以前にブログでご紹介したと思うが・・・
遊び用として数ヶ月前にVOXのヘッドフォンアンプを購入したのだ
実は思ったほど出番がなかったのだ
自宅ではGT-100を中心にギターを弾いているし外では実機のアンプを鳴らしているのだ
簡易的に録音や練習をするならばBR-80が便利なのだ

値段の割にリアルな音色は認めるが私には不要な品だったのだ
実際に音色をお届けするにも非常に手間がかかるのだ
読者の皆さんも特に関心がないと思う
むしろ多機能&高音質なGT-100の音源に興味があると思うのだ
いつものように仕事帰りに楽器店に立ち寄ったのだ
上記のような話をしているとお兄さんがある商品を勧めてきたのだ
「キャビネットを接続したら面白いですよ~」
「ヘッドフォンとは違う感じですよ」

以前から興味があったので購入してみたのだ
『オモチャじゃないのかな?』
と心の中で思っていたのだ
楽器店のお兄さんが続けるのだ
「勿論、音量は出ないですよ でも、音色は捨てたもんじゃないですよ」
「僕も自宅練習で使っているんですよ 見た目も可愛いし・・」
まぁ、音が悪くてもインテリアに良いと考えたのだ

まさにマーシャルの段積みアンプの感じなのだ
キャビネットの質感も悪くない
キャビネットのインプットにミニアンプのジャックを接続するのだ

さらにキャビネットのケーブルをミニアンプのフォーンジャックに接続するのだ
後はキャビネット側にギターを差し込むだけなのだ

いたって構造は単純なのだがちょっと面白い電気の流れなのだ
読者の皆さんも頭を整理して少し考えていただきたい
単なるスピーカーではない事がお分かりいただけると思う
キャビネット単体では音は出ないのだ
音楽プレーヤーなどに接続するミニスピーカーとは区別したい
ミニアンプ側は単四電池一本なのだ
キャビネット側は9V電池一個なのだ
小さいが一応パワーアンプになっているのがミソなのだ
発売当初は種類も少なかったが最近はランナップも増えたのだ
非常に人気がある商品なのだ
ちなみに私はマーシャル風?のアンプを使っているのだ
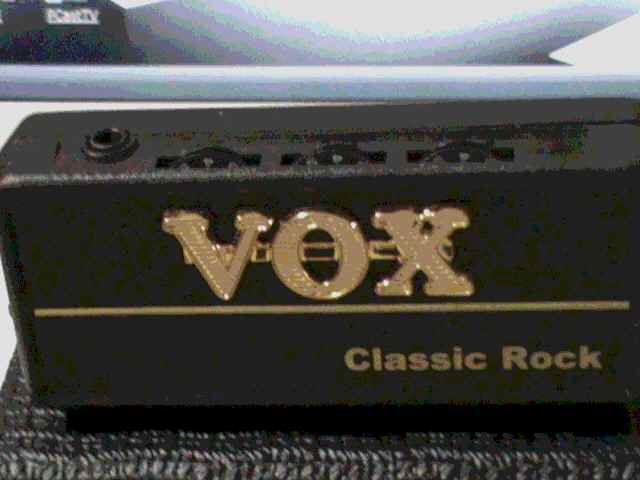
ゲイン、トーン、ボリュームの3個なのだ
ボリュームが実機のマスターに相当する役割を持っているのだ

実機のマーシャルの特徴に一つにあの独特のエッジ感がある
かなり忠実に再現されているのだ
ネットには文句を言う人も多いが・・
値段を考えればかなり優秀だといえるのだ
ちなみに興味ある方は参考にしていただきたい↓
『VOXミニアンプ』
実際に録音する方法は2通りなのだ
私の場合、マイクで収録する方法とBR-80のコンデンサーマイクを使う方法が考えられる

BR-80の内蔵マイクはかなり感度が良いのだ
良過ぎて困る事も多いのだ
ウクレレなどの録音の際に外部の音も拾ってしまうのだ
実機のアンプにマイクを向ける時にも角度や距離が重要なのだ
一度は耳にしたことがあると思う
BR-80で録音する場合にもキャビネットとの距離や角度でかなり結果が異なるのだ
「リアルだね~ 意外に面白いかも?」
「オケに混ぜたらどんな感じになるのかな?」
興味は尽きないのだ
ちなみに私のVOXアンプはマーシャルの素の音なのだ
ディレイもリバーブも付いていないのだ
味気ないと言えば味気ない・・のだ
BR-80を使えばリバーブを加えた音をモニター(実際に録音も)する事が可能なのだ
先がけになってしまうがその他のエフェクトをかけることも可能なのだ
モニターの際にはヘッドフォンを使う事になるのだ
「これじゃGT-100の時と一緒だなぁ・・」
そうなのだ
アンプの『空気感』を再現する事が可能にはなるが実際に聴く音はヘッドフォンなのだ
ちょっとした工夫で解決したのだ
先に述べたようにアンプとキャビネットの接続は少々特殊なのだ
VOXミニアンプの代替えとしてBR-80を利用するアイディアが浮かんだのだ
実際の接続がコチラなのだ

音の流れは一緒なのだ
BR-80がアンプヘッドの役割を担うのだ
当然ながらエフェクトの挿入も自在なのだ
ちなみにこの状態では録音はできないのだ
実際の音はどうか?
「伸びるね~♪ 音もクリアだし気持ちいいなぁ・・」
最高なのだ

キャビネットにギターを近づけると実機さながらにフィードバックするのだ
まさに小さなマーシャルなのだ
内蔵のドラムを同時に鳴らす事も可能なのだ
卓上の飾りとしてもかなり秀逸だと思う

ミニアンプ単体の購入(使用)よりもキャビネットとの接続がお薦めなのだ
実機さながらにキャビネットの方が安いのだ
同時に購入となると学生さんには少し高いと感じられるかも?
それでも小型アンプを購入するよりも安いのだ
まぁ、素直に小型アンプを購入すれば多彩な機能が使えるが・・・
すでにBR-80やその他の機材を色々と持っている私の場合にはベストバイの選択だったのだ
小型ながら十分にアンプの質感を再現している点には脱帽なのだ
プロのお兄さんが気にっている理由が分かったのだ
自宅でのヘッドフォン環境も捨て難いが・・
時にはアンプで弾きたくなる事もあるのだ
そんなニーズには最適だと思うのだ
オベーションのウクレレに引き続き良い買い物をしたと思っているのだ
満足度が高ければそれは無駄遣いではないのだ
学業に仕事にと精が出るのも趣味あってこそだと考えているのだ
勉強もダメ、仕事もダメ、趣味も無い・・・
というのが一番つまらない人生なのだ
読者の皆さんは如何だろうか?
ギターや音楽に興味が湧いてきたという方も多いのでは?
良い事だと思う

ダラダラとyoutubeの音楽サイトを徘徊?している人も多いと聞いている
他人のペナペナの演奏を聴いているくらいなら自分で演奏した方が何倍も有意義なのだ
ネットのレビューや酷評をダラダラと読んでいるくらいなら自分で試した方が早いのだ
何処の誰だか分からない人々意見に一喜一憂するよりも自分自身の感性を信じるべきなのだ
長くなりそうなのでこの辺で・・・

実際の音源などもご紹介する予定なのだ
私の音源を聴く前に買ってしまうのも手だと思う
如何だろうか?

かなり遊べるアイテムだと思う