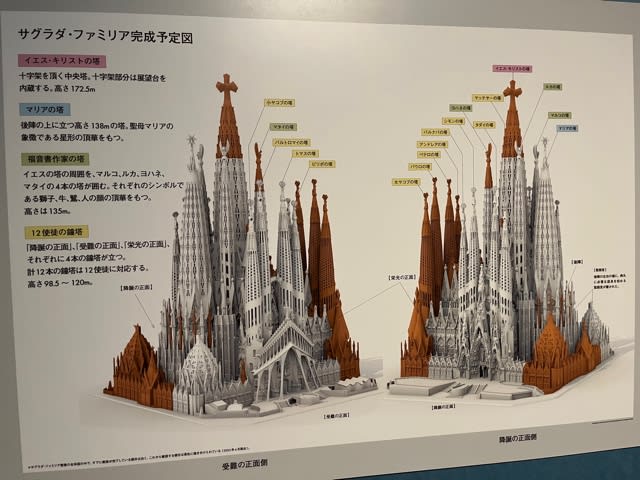東京都美術館にて、永遠の都ローマ展を鑑賞。
ローマ建国神話にまつわる牝狼が ロムルス、レムスの双子に乳を与える銅像「カピトリーノの牝狼」が最初に出迎える。
世界最古の美術館のひとつとして、1734年に一般公開が始まったカピトリーノ美術館の所蔵作品を中心とした展示。
時間の流れの中で雨風に耐えて残ってきたものとして、絵画よりも彫刻が多いのだろう。
目玉は、初来日となる「カピトリーノのヴィーナス」だ。
皇帝から教皇へ文化継承の担い手が変わっていく中で、市民が台頭していく流れも感じられる。
二千年続く街の重厚感を感じた。



ローマ建国神話にまつわる牝狼が ロムルス、レムスの双子に乳を与える銅像「カピトリーノの牝狼」が最初に出迎える。
世界最古の美術館のひとつとして、1734年に一般公開が始まったカピトリーノ美術館の所蔵作品を中心とした展示。
時間の流れの中で雨風に耐えて残ってきたものとして、絵画よりも彫刻が多いのだろう。
目玉は、初来日となる「カピトリーノのヴィーナス」だ。
皇帝から教皇へ文化継承の担い手が変わっていく中で、市民が台頭していく流れも感じられる。
二千年続く街の重厚感を感じた。