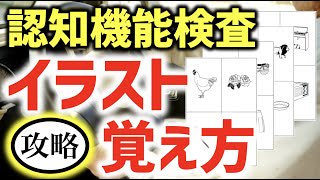2月13日、家の近くの鮫洲試験場で免許証の更新手続きに行ってきました。高齢者講習は、昨年受けているので、今回は認知機能検査の受検と更新手続きである。認知機能検査を受けるのは初めてであるが、検査自体に疑問もあり、実際に受けて見ての雑感を述べて見る。どういう検査が行われるか、あらかじめネットで情報を得ていて、模擬テストもやっていたが、実感としては、事前に模擬テストを行うことで変な記憶が残り返って混乱を招き、あまりやらないほうがよさそうである。テストはタブレットで行われ、大分イメージの違いがありあせった。1ページに4つのイラスト絵が描かれたものを見るが、それが4ページにわたっており、合計16の絵を見た後、時間をおいてから、その絵を思い出して何が描かれていたかを思い出し回答するものである。
タブレットは使ったこともないので、違和感もあり、問題の進め方の指示を間違え、やり直しをお願いしたが、却下され、パニック状態となった。一つ一つの絵をクリックしてから、説明を聞き、次に進む段取りのようであるが、間違って、絵をクリックすることなく、先に説明を聞いてしまい、間違っていることに途中で気づいた。はじめに絵の部分をクリックせよという指示はなく、パニクりながら先に進むことを強いられたので、本来の絵を記憶する余裕がなかった。最終的には、16の絵の内、ちゃんと回答できたのは、6個程度というさんざんな結果であった。家の模擬テストでは、大体13~14個は回答できていたので、不合格と思いきや、結果は合格であった。
認知機能検査の合格ラインは不明であるが、あれだけできなくても合格するとは相当低いと思われる。それに、検査は認知機能というより記憶力テストの印象が強い。どうやったらしっかり記憶できるかという記憶術の問題で、認知能力とは関係ないという印象を受けた。低い点でも合格させるということも変であり、要するに検査は記憶力能力の問題なので、認知との関連性は薄いという証である。
認知機能検査の後は、更新手続きで視力検査と写真撮影が行われた。高齢者は、事前に高齢者講習を受けているとのことで、当日の講習がないため、写真撮影後、免許証が出来上がるまで、1時間以上待たされる羽目となった。講習があれば、講習を受けている間に、免許証が出来上がるという段取りかも知れないが、高齢者にとっては、講習がないため、ただ待たされるだけである。待ち時間回避のため、講習のない高齢者と一般の人を区別して、免許証を作成してほしいものである。写真を撮った後、1時間以上もかかるのはいかにもアナログの免許証といえるが、3月24日から導入されるマイナ免許証では解決されるのであろうか?ひとまず、3年間有効の免許証が得られたので、一安心である。