産経新聞で曽野綾子氏のコラムを読んだ。
乱暴な梗概と承知して紹介すれば、氏は自然災害は「非常時を乗り切るための人間力回復の好機」と説き、自然災害がもたらす“正”の面にも目を向けることが大事と主張されている。氏が経験した「相当な学力を持つ若者が「自然水を沸騰殺菌して飲用する」ことが理解できない」ケースを紹介して、自然災害により停電や断水でインフラがダウンした場合に生き残れるのは「人間力」いわゆる”生活の知恵”と呼ばれるサバイバル術であり、自然災害はそれを磨くための好機としていることである。勿論、氏は自然災害を歓迎するものではなく、災害がもたらす人命・財産の毀損に心を痛めて、文明が果たす回復力に期待していることは云ううまでもない。昔々の幼少期、薪と竈で調理し、停電時はカンテラで応急照明を確保し、スイトンで空腹を満たすのが一般的であったが、いつしか電気炊飯器に変わり、LEDランタンに変わり、ランチに置き換わりと氏の云う人間力は、恥ずかしながら自分(70代)でも既に忘れかけているものと反省しているところである。もしも明日、氏の説く人間力が試されたとするならば、何とか”昔取った杵柄”と思い出すことができるかもしれないが、自分の子供には期待できないことだろう。それは人間力の体得と伝承を怠った我々世代の責任であるが、日本の復興と進歩にも一因があると思う。”治に居て乱を忘れず”の心構えは必要であることを改めて思い起こされた一文と感謝している。
昭和40年台までは、真珠湾作戦参加者やシブヤン海を3時間泳いだ帝国海軍の猛者が在職していた。その時に教えられたものの一つに”人命救助のために投げるロープには結びこぶを付けること”というのがあった。溺れかけた人間は体力の消耗が激しく、滑りやすいロープを掴んで体を支える力は残されていないために、手掛かりになる結びこぶが必要ということであった。その20年くらい後に1度だけ役立てることができ、先輩の教えは心して聞いておかなければならないことを痛感したことをも、懐かしく思い出した一文であった。














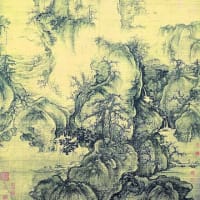





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます