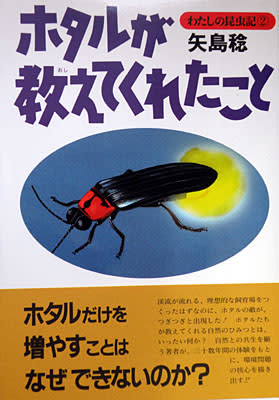今日も群馬は暑かった。前橋の最高気温は35.5℃、3日連続の猛暑日。
沼田は34.1℃、みなかみが32.1℃でしたので、川場村でも33℃くらまで上がったと思います。でも、川場村では少し日が傾くと、嘘のように過ごしやすくなります。
今日の川場村

ルリシジミ

アゲハモドキ

ジャコウアゲハ♀に擬態しています。
カマキリの幼虫

だいぶ大きくなってきました。


セマダラコガネ

オオシオカラトンボ♀

ホタルが棲む小川の横で見つけたオニヤンマの抜け殻

よく、こんなにきれいに殻を脱げるもんですねぇ
日本のトンボは1年に1世代のものと、1年に2世代を繰り返すものがほとんでですが、オニヤンマは羽化するまでに5年もかかります。オニヤンマの羽化がみられるということは、長期にわたって良好な環境が維持されている証拠です。
先日紹介したキアゲハの蛹

7月6日には、少し緑色がかっていましたが、翌日には周囲の色とまったく同じ色になりました。まだ羽化の気配はありません。
キアゲハが蛹から羽化までに要する積算温度はどれくらいなのかは、私にはよく分かりませんが、この蛹がある場所は、もろに夏の強い日差しが当たり、かなりの高温になっていますので、羽化までに、そう長い時間はかからないのではと思っています。それよりも温度の上がり過ぎが心配・・・。
こちらは7月4日に紹介したセグロアシナガバチの巣

働き蜂が現れました。
これからは少しは楽ができるね、女王様 (^^)
沼田は34.1℃、みなかみが32.1℃でしたので、川場村でも33℃くらまで上がったと思います。でも、川場村では少し日が傾くと、嘘のように過ごしやすくなります。
今日の川場村

ルリシジミ

アゲハモドキ

ジャコウアゲハ♀に擬態しています。
カマキリの幼虫

だいぶ大きくなってきました。


セマダラコガネ

オオシオカラトンボ♀

ホタルが棲む小川の横で見つけたオニヤンマの抜け殻

よく、こんなにきれいに殻を脱げるもんですねぇ
日本のトンボは1年に1世代のものと、1年に2世代を繰り返すものがほとんでですが、オニヤンマは羽化するまでに5年もかかります。オニヤンマの羽化がみられるということは、長期にわたって良好な環境が維持されている証拠です。
先日紹介したキアゲハの蛹

7月6日には、少し緑色がかっていましたが、翌日には周囲の色とまったく同じ色になりました。まだ羽化の気配はありません。
キアゲハが蛹から羽化までに要する積算温度はどれくらいなのかは、私にはよく分かりませんが、この蛹がある場所は、もろに夏の強い日差しが当たり、かなりの高温になっていますので、羽化までに、そう長い時間はかからないのではと思っています。それよりも温度の上がり過ぎが心配・・・。
こちらは7月4日に紹介したセグロアシナガバチの巣

働き蜂が現れました。
これからは少しは楽ができるね、女王様 (^^)