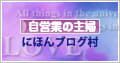プリンターを買わずにやっていけるか!?
というのを、ただ今挑戦しております。
必要なものはコンビニで印刷するんだっ
との思いでいましたが、
必要な時は手書きで乗り切っています。
まぁ手間がかかったり、
書いたものがゴチャゴチャになって読みにくくなったりはしますが、
あんな大きな(じゃまな?)ものがないうえ、
何度もヘッドクリーニングをして印刷状態のチェックはしなくていいし、
インク代もかからない!
これはいいことなのです。
3月18日、プリンターの修理ができず使えなくなった、
3月21日、15年間のインク代がオソロシイことになっていた、
という内容の記事を書きました。
プリンターの買い替えをせず、
買わないという選択をしたわけです。
「コンビニでハガキ印刷が出来るようになった」
というのは確認したので、
年賀状の裏面印刷はいいとして、宛名は手書きになるでしょうね…。
CDの盤面に印刷できないのはちょっと悲しいなー。
とりあえず少し頑張ってみて、
年賀状の時期を越えたときに本当にいるかどうか結論を出しましょう!
って感じ。
洋服はだいぶ整理したけど、
まだまだモノが多いワタシ。
こじんまりと暮らしたいと思っているのです。
うん、そうだ!
これからのワードは「こじんまり」
というのを、ただ今挑戦しております。
必要なものはコンビニで印刷するんだっ
との思いでいましたが、
必要な時は手書きで乗り切っています。
まぁ手間がかかったり、
書いたものがゴチャゴチャになって読みにくくなったりはしますが、
あんな大きな(じゃまな?)ものがないうえ、
何度もヘッドクリーニングをして印刷状態のチェックはしなくていいし、
インク代もかからない!
これはいいことなのです。
3月18日、プリンターの修理ができず使えなくなった、
3月21日、15年間のインク代がオソロシイことになっていた、
という内容の記事を書きました。
プリンターの買い替えをせず、
買わないという選択をしたわけです。
「コンビニでハガキ印刷が出来るようになった」
というのは確認したので、
年賀状の裏面印刷はいいとして、宛名は手書きになるでしょうね…。
CDの盤面に印刷できないのはちょっと悲しいなー。
とりあえず少し頑張ってみて、
年賀状の時期を越えたときに本当にいるかどうか結論を出しましょう!
って感じ。
洋服はだいぶ整理したけど、
まだまだモノが多いワタシ。
こじんまりと暮らしたいと思っているのです。
うん、そうだ!
これからのワードは「こじんまり」