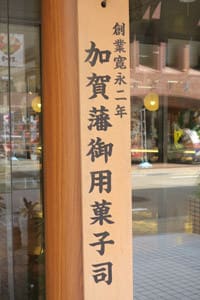金沢の観光スポットレポート その940(No.1349)
◇金沢城公園 石垣巡り‐1
2011年に石垣巡りを掲載したが、まいどさん勉強会や金沢城・兼六園研究会入会をきっかけとして、再度掘り下げてアップします。
■写真は金沢城石垣巡り地図(金沢城公園HPより)

〇金沢城概要
金沢城の歴史加賀一向一揆で支配権を握った本願寺が、天文15年(1546)に金沢御堂(尾山御坊)を建てた地に、天正8年(1580)、佐久間盛政が築城を開始、天正11年(1583)、加賀初代藩主前田利家が能登から入城し、本格的に城造りがなされました。
慶長7年(1602)に天守閣が落雷による火災により焼失し、その後は江戸幕府への遠慮から再建されませんでした。
金沢城は、金沢市の市街地に位置し、犀川と浅野川に挟まれた小立野台地の先端に立地する平山城である。規模は東西500m、南北760m、面積約30haである。
■写真は石川門

〇金沢城石垣の概要
金沢城の石垣は、技法や意匠の多様性に特色があり、石垣の博物館とも称される。「自然石積」「割石積み」「粗化工石積」「切石積」の石積み様式は、場の性格や周囲との調和にも配慮しながら、城郭整備の歴史と共に多彩な発展を遂げた。その結果、技法的にも意匠的にも、他に類を見ないほど、変化に富む石垣景観が出来上がった。
金沢城の現存する石垣は470面、総面積28,500㎡、うち切石積み面積が約3,400㎡、全体の12%と高い比率を占めることが金沢城の特徴の一つである。
また、金沢城の石垣は特色として以下の3点が上げられる。
1)石垣の保存状態が良好なこと。
2)石垣の技術書や修築の様子を詳しく伝える文献資料等が多く残されており、その質、量は他の城の例をみない。
3)文禄、慶長期以来、江戸期を通じて石垣修築が繰り返されたとい うこと。これは金沢城の現存石垣に近世のさまざまな段階の石 垣技術が内包されているということである。
<参考:北野博司氏「加州金沢城の石垣修築について」より>
■写真は三の丸広場

〇主な石積の技法大きく分けると3種類になる。(鶴丸休憩館前にあるモデル)
1)自然石積
この石垣はもっとも古いも古いもので、自然の石や粗割りしただけの石を用いて積む技法です。金沢城の初期の姿を伝える数少ない貴重なもので、場内では。東の丸北面石垣などに見られます。
■写真は自然石積

2)粗化工石積
割石を加工し、肩や大きさを揃えた石材(粗化工石)用いて積む技法で、櫓や長屋などの外周の石垣に見ることができます。二の丸北面石垣がその代表例で、加賀藩の石垣技術者、後藤彦三郎は「場内屈指の石垣」と称賛しています。石材の形や大きさ、加工の様子など、切石積みとの違いをご覧ください。
■写真は粗化工石積

3)切石積
切石積は、丁寧に加工した切石を隙間なく積む技法で、本丸への入り口など城の重要な部分の石垣に見ることがで来ます。城内各所の石垣は、それぞれ表面だけしか見られませんが、ここでは石垣の積み方や、その内部も見ることが出来ます。(以上展示案内看板より)
■写真は切石積
〇金沢城調査研究室発行のNo.3「金沢城を探る」の石積み分類では下記の通りとなっている。
1)自然石積 *東の丸北面

2)割石積 *本丸申酉櫓下

3)粗化工石積 *五十間長屋

4)切石積をさらに分類
①四方積(正方形石)*橋爪門続櫓

②布積(長方形石)*数寄屋敷

③布積(不整形石)*石川門

④布積(粗化工石)*二の丸北面

⑤乱積(不整形石)*土橋門

⑥金場取り残し積 *三十間長屋

〇その他の分類
1)鉢巻き石垣 *玉泉院丸庭園下

2)鉢巻き腰巻き石垣 *彦根城

*ほかにもいろいろな呼び方があるが、ここでは割愛します。
撮影日:2018.7
(つづく)