【有岡利幸著、法政大学出版局発行】
法政大学出版局が1968年にスタートした百科叢書「ものと人間の文化史」シリーズの168件目。著者有岡氏は1937年岡山県生まれ。56~93年大阪営林局で森林の育成・経営計画業務などに従事、その後、(財)水利科学研究所客員研究員などを務めた。著書に「森と人間の生活―箕面山野の歴史」「松と日本人」などのほか、同シリーズでも「松茸」「梅Ⅰ」「梅Ⅱ」「秋の七草」「春の七草」「檜」「桃」「柳」など多数執筆している。
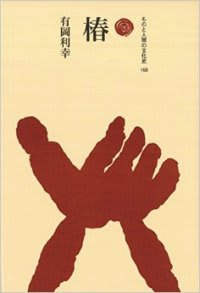
「記紀・万葉時代の椿」「近世初期に大流行した椿」「神仏をまつる社寺と椿」「近・現代の椿事情」など8つの章で構成する。日本原産のヤブツバキは学名が「カメリア・ジャポニカ」。椿は有用材として古くから様々な形で利用されてきた。約5000年前の縄文時代の鳥浜遺跡(福井県三方町)からは赤い漆塗りの櫛や石斧の柄などが出土している。樹種別の加工品の遺物件数では杉、樫、ユズリハに次いで多い。
わが国でツバキに対して椿の字を当てたのは万葉集が最初。坂門人足は「巨勢山のつらつら椿つらつらに……」と詠んだ。万葉集には椿のほか万葉仮名の都婆伎や海石榴などの表記も。椿油や種子は遣隋使や遣唐使によって中国にも運ばれた。ところが、その椿も平安時代の和歌や随筆、物語にほとんど登場しない。椿が再び注目を集めるのは茶道の茶花として。江戸時代には「寛永(1624~44年)の椿」など一時期園芸ブームも起きた。
しかし「明治維新で近代となると、椿は古いものだと見捨てられ、愛好者がほそぼそと楽しむにすぎなくなった。この傾向は昭和初期の終戦直後まで続いた」。一方、江戸時代シーボルトらによってヨーロッパに紹介された椿は「冬のバラ」としてもてはやされ、熱狂的な栽培ブームが巻き起きた。そんな世相を反映し小デュマの小説「椿姫」が生まれ、ヴェルディによってオペラ化された。米国で全国組織のツバキ協会が発足したのは1945年。欧米での流行に刺激されて、本家日本で日本ツバキ協会が創立されたのは8年後の1953年だった。
海石榴をツバキと読むのは「遣唐使によって中国に渡ったツバキがかの地でこう記されていたからで、中国では海をわたってきた石榴に似た実をつける樹という意味で海の字が頭についた」。古代、三輪山麓にあった市場「海石榴市(つばいち)」の読みは「ツバキイチがツバイチに転訛したもの」。その名の由来は「三輪山にたくさん生育している海石榴や周辺の山地に生育しているツバキの種子を、あるいは種子をしぼったツバキや、椿の木を燃やした灰を商品としていたことに因んだものと考えられる」という。本書は椿の品種や全国各地の椿にまつわる昔話・民俗、ゆかりの神社なども詳細に紹介している。
















