昨年12月に大型書店で、円城塔(えんじょうとう)さんが書いた小説「これはペンです」の単行本(新潮社、2011年9月30日発行)を購入しました。円城さんの小説は、これまで読んだことがなかったのですが、新聞の書評などで「これはペンです」が取り上げられていたことが頭の片隅にあったようで、購入しました。
円城さんは、物理学などに基づいた難解な表現・内容を駆使することで知られている理系ご出身の小説家です。東北大学の理学部物理学科を卒業し、東京大学大学院総合文化研究科博士課程を修了した後に、ポストドクター研究員として研究者生活に入りました。その後は企業に就職しWebサイトのエンジニアになったうえに、小説家も兼業されている経歴の持ち主です。
単行本「これはペンです」は、中編小説の「これはペンです」と「良い夜を持っている」の2編で構成されています。この2編の内容は関連した物語です。
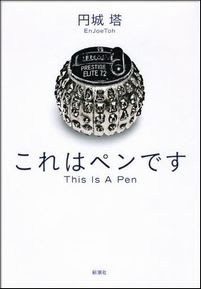
小説「これはペンです」は、文章を自動的に生成する装置を開発した叔父から送られてくる手紙を受け取って読む姪の話です。叔父から送られてくる手紙は、その文章が自動生成されたものかもしれないのです。“叔父”とは文章自動生成装置そのものかもしれないのです。
SF作家の瀬名秀明のSF小説「デカルトの密室」(新潮社発行)の設定に似ていると感じました。

「デカルトの密室」では、密室の壁の向こうから伝えられる伝達文は、人工知能を持つロボットが出しているのかもしれないという設定です。人工知能という高度な機械と人間の違いは何か、人工知能は心を持つのかを問う内容でした。
「これはペンです」では、手紙の送り主の叔父は、米国に渡って文章自動生成装置を開発し、学術論文を自動的に作成する仕掛けの「疑似論文生成プログラム」を開発します。その自動生成した学術論文を、学術誌に投稿し、その内容が認められて学術誌に掲載されます。これを事業化し、博士号が欲しい人に、文章自動生成装置がつくった学術論文を売る商売で成功し、財産を築きます。米国では、学位販売事業の“ディプロマ・ミル”というインチキ博士号を売る会社が実際にあります。このへんは、円城さんが大学院の博士課程に在学した時やポストドクター研究員で感じたことなのかもしてません。
小説「これはペンです」は、文学とは何か、書く作業とは何かを根源から問う小説という評価もあります。この「これはペンです」は昨年度の芥川賞候補になりましたが、否定的な評価が多かったとのことです。
物理的あるいは科学的な知識がないと読みにくい個所が多く、一般の方にとってはあまり読みやすい文章ではありません。何となく読み飛ばして読み進んでいくという感じです。でも、何か心に残るような文章が散りばめられているとも感じます、とても不思議な文章・内容の小説です。円城さんは2006年に小説「オブ・ザ・ベースボール」で第104回文學界新人賞受賞を受賞して以来、精力的に根源的な内容の小説を書き続けています。
円城さんは、物理学などに基づいた難解な表現・内容を駆使することで知られている理系ご出身の小説家です。東北大学の理学部物理学科を卒業し、東京大学大学院総合文化研究科博士課程を修了した後に、ポストドクター研究員として研究者生活に入りました。その後は企業に就職しWebサイトのエンジニアになったうえに、小説家も兼業されている経歴の持ち主です。
単行本「これはペンです」は、中編小説の「これはペンです」と「良い夜を持っている」の2編で構成されています。この2編の内容は関連した物語です。
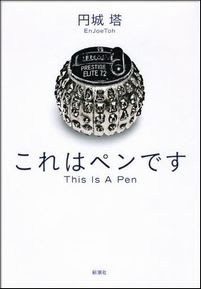
小説「これはペンです」は、文章を自動的に生成する装置を開発した叔父から送られてくる手紙を受け取って読む姪の話です。叔父から送られてくる手紙は、その文章が自動生成されたものかもしれないのです。“叔父”とは文章自動生成装置そのものかもしれないのです。
SF作家の瀬名秀明のSF小説「デカルトの密室」(新潮社発行)の設定に似ていると感じました。

「デカルトの密室」では、密室の壁の向こうから伝えられる伝達文は、人工知能を持つロボットが出しているのかもしれないという設定です。人工知能という高度な機械と人間の違いは何か、人工知能は心を持つのかを問う内容でした。
「これはペンです」では、手紙の送り主の叔父は、米国に渡って文章自動生成装置を開発し、学術論文を自動的に作成する仕掛けの「疑似論文生成プログラム」を開発します。その自動生成した学術論文を、学術誌に投稿し、その内容が認められて学術誌に掲載されます。これを事業化し、博士号が欲しい人に、文章自動生成装置がつくった学術論文を売る商売で成功し、財産を築きます。米国では、学位販売事業の“ディプロマ・ミル”というインチキ博士号を売る会社が実際にあります。このへんは、円城さんが大学院の博士課程に在学した時やポストドクター研究員で感じたことなのかもしてません。
小説「これはペンです」は、文学とは何か、書く作業とは何かを根源から問う小説という評価もあります。この「これはペンです」は昨年度の芥川賞候補になりましたが、否定的な評価が多かったとのことです。
物理的あるいは科学的な知識がないと読みにくい個所が多く、一般の方にとってはあまり読みやすい文章ではありません。何となく読み飛ばして読み進んでいくという感じです。でも、何か心に残るような文章が散りばめられているとも感じます、とても不思議な文章・内容の小説です。円城さんは2006年に小説「オブ・ザ・ベースボール」で第104回文學界新人賞受賞を受賞して以来、精力的に根源的な内容の小説を書き続けています。









