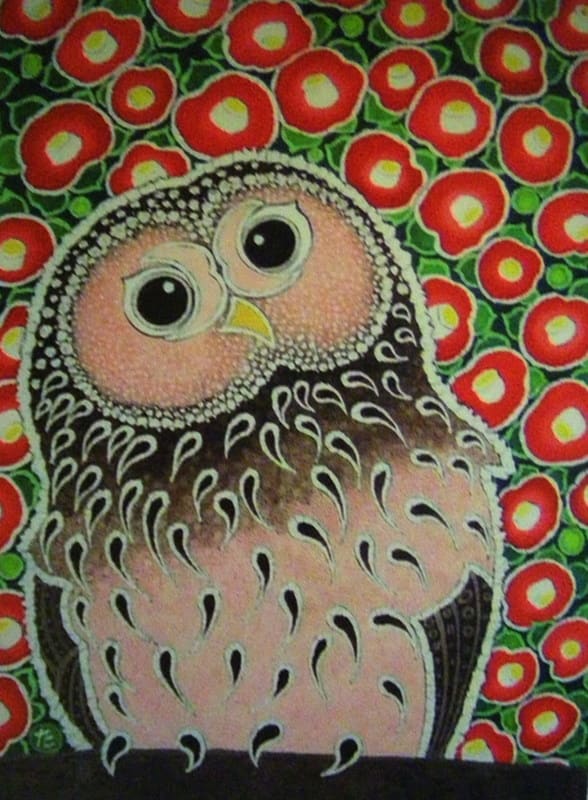17日(月)夜はシズオカ文化クラブの定例会で、静岡とゆかりの深い今川氏について勉強しました。講師は民俗学者で静岡産業大学教授の中村羊一郎先生。有名武将の戦歴をたどる歴史学というよりも、民俗学の視点から、地域土着の民の生き方を通して戦国時代の実情を読み解く大変興味深い内容でした。
講座の前に、葵区常磐町にある宝台院の見学会がありました。歴史ファンな らおなじみ、徳川家康の側室で2代将軍秀忠の生母・お愛の方(西郷局)の菩提寺。寺はもともと浄土宗「龍泉寺」という名で鎌倉時代に現在の静岡市葵区柚木あたりに建てられ、家康が駿府入りをして間もなく糟糠の妻だったお愛の方が37歳で亡くなると、この寺に葬られました。
らおなじみ、徳川家康の側室で2代将軍秀忠の生母・お愛の方(西郷局)の菩提寺。寺はもともと浄土宗「龍泉寺」という名で鎌倉時代に現在の静岡市葵区柚木あたりに建てられ、家康が駿府入りをして間もなく糟糠の妻だったお愛の方が37歳で亡くなると、この寺に葬られました。
息子秀忠は、母の菩提寺としてふさわしい寺にしようと、慶長9年に紺屋町に移し、寛永5年に常磐町へ大伽藍を建てました。このとき、お愛の方へ“宝台院殿一品大夫人”の謚号が送られたことから、宝台院と呼ぶようになったそうです。
当時の大伽藍は、二条城と同じ大工集団の手による傑出した建造物で、江戸増上寺とならぶ徳川家当用菩提寺としての格式があり、最後の将軍慶喜が駿府へ蟄居した際、ここで1年間謹慎生活を送りました。その後移り住んだ旧代官屋敷(現在の浮月楼)は寺のすぐ隣に位置していたといいますから、宝台院がいかに大きかったかがわかります。なんでも常磐町に建てられた当時は9700余坪あったとか。常磐町のとなり町・西門町は、その名の通り、宝台院の西門があった場所でした。
昭和初期までは静岡を代表する国宝級の名刹として、また初詣やお祭り等で庶民にも大いに親しまれていたそうですが、昭和5年の静岡大火でほとんどが焼けてしまい、復興した諸堂も昭和20年の静岡空襲で焼失。二条城に匹敵する国宝級大伽藍の面影は、古い写真の中でしか見ることができなくなりました。
 現在の鉄筋3階建ての宝台院は、昭和45年に建てられたもの。2階の本堂には、快慶作の白本尊阿弥陀如来像が安置されています。金箔の裏に白い樹粉が塗られてあったことから“白本尊”と呼ばれるようになったそうで、増上寺には煤色の“黒本尊”が祀られています。なんでもこの白本尊の耳の後ろには矢の傷が残っていて、戦乱のさ中、家康公の身代わりになったということで重宝されているそうです。
現在の鉄筋3階建ての宝台院は、昭和45年に建てられたもの。2階の本堂には、快慶作の白本尊阿弥陀如来像が安置されています。金箔の裏に白い樹粉が塗られてあったことから“白本尊”と呼ばれるようになったそうで、増上寺には煤色の“黒本尊”が祀られています。なんでもこの白本尊の耳の後ろには矢の傷が残っていて、戦乱のさ中、家康公の身代わりになったということで重宝されているそうです。
3階は宝物館。家康公の真筆御影像、家康公が父から譲り受けた刀剣、手習いの書、三代将軍家光の絵画や書など、博物館蔵レベルのお宝がズラリと並んでいます。静岡市街地にあって拝観料200円を払えばいつでも見られるのに、じっくり見学するのは初めて・・・。歴史好きを自認する身としては、ちょっと恥ずかしかったです。
来年のNHK大河ドラマは確か秀忠夫人お江が主人公のはずですから、少しはクローズアップされるのかな?
宝台院の境内の片隅に、キリシタン灯篭があります。秀吉の朝鮮侵攻の折、小西行長が朝鮮半島から拉致し、のちに家康公のお気に入り侍女となったジュリアおたあが建てたもの。キリシタンだった彼女は、信仰に殉じて島流しとなり、伊豆神津島で亡くなるのですが、徳川の正当な菩提寺である宝台院にキリシタン灯篭が残っている理由はよくわからないそうです。
…なんだかダヴィンチコードみたいな歴史推理サスペンスが書けそうですね!
長くなったので、中村先生の講演は次回へ。