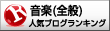♪お気に入り映画(その20)
■ヒトラー ~最期の12日間~ (Der Untergang)
■2004年
■ドイツ オーストリア イタリア 共同制作
■監督…オリヴァー・ヒルシュビーゲル
■音楽…ステファン・ツァハリアス
■出演
☆ブルーノ・ガンツ(アドルフ・ヒトラー)
☆ユリアーネ・ケーラー(エヴァ・ブラウン)
☆アレクサンドラ・マリア・ラーラ(トラウドゥル・ユンゲ)
☆トーマス・クレッチマン(オットー・フェーゲラインSS中将)
☆ウルリッヒ・マテス(ヨーゼフ・ゲッベルス宣伝相)
☆コリンナ・ハルフォーフ(マグダ・ゲッベルス夫人)
☆アレキサンダー・ヘルド(アーネスト・シェンク博士)
☆ハイノ・フェルヒ(アルベルト・シュペーア軍需相)
☆ウルリッヒ・ネーテン(ハインリヒ・ヒムラーSS長官)
☆アンドレ・ヘンニッケ(ヴィルヘルム・モーンケ少将)
☆ゲッツ・オットー(オットー・ギュンシェSS将校) etc・・・
155分があっという間に感じられた。
ナチス・ドイツの独裁者として悪名高い、アドルフ・ヒトラーを主人公とした映画である。原題の「Der Untergang」は「没落」という意味だそうだ。
ドイツ語を話す俳優がヒトラーを本格的に演じたのはこの作品が初めてだということだ。
ヨアヒム・フェストの『ダウンフォール/ヒトラーの地下要塞における第三帝国最期の日々』と、トラウドゥル・ユンゲの回想録『最後の時間まで/ヒトラー最後の秘書』が原作である。
映画は、ヒトラーの56回目の誕生日である1945年4月20日から、彼の後継者であるゲッベルス宣伝相が自殺した5月1日までの12日間を描いている。
ぼくはこれまでに、ジョン・トーランドやコーネリアス・ライアンらが書いたヒトラー関連の本を読んでいるが、それらの本に書かれている史実やヒトラーの人物像などと、映画で描かれていることとのズレはあまりなかったと思う。
スターリンやポル・ポトらと並んで、つねに20世紀最悪の政治家のひとりにあげられるヒトラーの素顔を、側近たち、愛人のエヴァ・ブラウン、秘書のトラウドゥル・ユンゲらとの関わりを通じて、どちらかというと淡々と描いているようだ。
この時期のヒトラーはたいへん健康を害していたうえ、侍医のモレル博士には「薬と称した毒物」を服用させられていたりしたので、精神的にも正常とは言い難い状態だったそうである。軍人たちに対してはいきなりヒステリックに怒鳴り散らすなど、感情の起伏がとても激しかったそうだ。しかし、女性や子供たちには優しく紳士的な態度を崩さなかったという。
しかし、そういう人間味のある面があるからといって、それはヒトラーに対する免罪符にはならない。この作品ではあくまでも誇張を排して、自分の作り上げた第三帝国の最期に直面したありのままのヒトラーを描こうとしているのだと思う。

軍事的、戦史的なことはこの作品の重要な主題ではない。
歴史上の出来事を取り上げているため、ヴァイトリング、モーンケ、ヴェンク、シュタイナーなどの将軍や、シュペーア、ヒムラー、ゲッベルス、ゲーリングなどのナチスの幹部など、実在した人物の名が多数出てきて混乱しやすい。そのあたりの知識を少しでも仕入れてからこの作品を観ると、より分かりやすいと思う。
また、ヒトラーは軍事的には素人だったことに加え、側近のヨードル大将やカイテル元帥の偏狭な態度が戦況を悪化させたこと、ナチスの幹部間には絶えず権力争いと責任のなすり合いが生じていたこと、国防軍は比較的ナチズムに毒されていなかったため、陰ではヒトラーを伍長呼ばわり(ヒトラーの軍人としての階級は伍長クラスどまり)して軽んじる風潮が一部であったことなどを知ったうえで見てゆくと、この映画がいっそう興味深く思えるかもしれない。
ヒトラーは、あくまで戦い抜くか、さもなければ国民もろとも死を選ぶことを頑強に主張しており、彼のベルリン地下要塞は狂信的なナチズムと、ナチズムに対する投げやりな服従に満ちていた。東西両面から押し寄せてくる敵や「敗戦」などの、負の現実から目をそらそうとしているかのような空気が漂っている。しかし、ヒトラーの死の直後、部下たちはいっせいにタバコに火をつける。この場面は、ヒトラーの自殺で要塞内がヒトラーの呪縛から解放されたことを暗示しているようだ(ヒトラーは禁酒・菜食主義者で、タバコも嫌っていた)。
そして、最後までヒトラーに忠節を尽くしていたゲッベルス夫妻の自殺で、実質的にヒトラーの「第三帝国」は終焉を迎えるのである。
なんらかの思想を通じて歴史を振り返るのはとても危険なことだと思う。歴史はありのままに歴史として見なければならない。この映画も、そういう目で見るべき類のものだろう。
ただ、映画の最後に、トラウドゥル・ユンゲがインタビューに答えてこう語る場面が出てくる。
「私は『自分は何も知らなかった(註:ナチス・ドイツの侵略や、ユダヤ人に対する虐殺などのこと)。だから自分に非はない』と考えていました。でもある日(中略)気づきました。『若かった』というのは言い訳にはならない。ちゃんと目を開いてさえいれば真実に気づけたのだ、と」
この映画を観たあとで、それぞれがヒトラーの善悪や、戦争の是非や、人間の尊厳などについて思いを巡らすことだろう。しかし、誤った前提で考えると正しい答えは出てこない。そう、ユンゲの言葉を借りるなら、「ちゃんと目を開いて」見ることが大事なのだと思う。
人気blogランキングへ←クリックして下さいね
■ヒトラー ~最期の12日間~ (Der Untergang)
■2004年
■ドイツ オーストリア イタリア 共同制作
■監督…オリヴァー・ヒルシュビーゲル
■音楽…ステファン・ツァハリアス
■出演
☆ブルーノ・ガンツ(アドルフ・ヒトラー)
☆ユリアーネ・ケーラー(エヴァ・ブラウン)
☆アレクサンドラ・マリア・ラーラ(トラウドゥル・ユンゲ)
☆トーマス・クレッチマン(オットー・フェーゲラインSS中将)
☆ウルリッヒ・マテス(ヨーゼフ・ゲッベルス宣伝相)
☆コリンナ・ハルフォーフ(マグダ・ゲッベルス夫人)
☆アレキサンダー・ヘルド(アーネスト・シェンク博士)
☆ハイノ・フェルヒ(アルベルト・シュペーア軍需相)
☆ウルリッヒ・ネーテン(ハインリヒ・ヒムラーSS長官)
☆アンドレ・ヘンニッケ(ヴィルヘルム・モーンケ少将)
☆ゲッツ・オットー(オットー・ギュンシェSS将校) etc・・・
155分があっという間に感じられた。
ナチス・ドイツの独裁者として悪名高い、アドルフ・ヒトラーを主人公とした映画である。原題の「Der Untergang」は「没落」という意味だそうだ。
ドイツ語を話す俳優がヒトラーを本格的に演じたのはこの作品が初めてだということだ。
ヨアヒム・フェストの『ダウンフォール/ヒトラーの地下要塞における第三帝国最期の日々』と、トラウドゥル・ユンゲの回想録『最後の時間まで/ヒトラー最後の秘書』が原作である。
映画は、ヒトラーの56回目の誕生日である1945年4月20日から、彼の後継者であるゲッベルス宣伝相が自殺した5月1日までの12日間を描いている。
ぼくはこれまでに、ジョン・トーランドやコーネリアス・ライアンらが書いたヒトラー関連の本を読んでいるが、それらの本に書かれている史実やヒトラーの人物像などと、映画で描かれていることとのズレはあまりなかったと思う。
スターリンやポル・ポトらと並んで、つねに20世紀最悪の政治家のひとりにあげられるヒトラーの素顔を、側近たち、愛人のエヴァ・ブラウン、秘書のトラウドゥル・ユンゲらとの関わりを通じて、どちらかというと淡々と描いているようだ。
この時期のヒトラーはたいへん健康を害していたうえ、侍医のモレル博士には「薬と称した毒物」を服用させられていたりしたので、精神的にも正常とは言い難い状態だったそうである。軍人たちに対してはいきなりヒステリックに怒鳴り散らすなど、感情の起伏がとても激しかったそうだ。しかし、女性や子供たちには優しく紳士的な態度を崩さなかったという。
しかし、そういう人間味のある面があるからといって、それはヒトラーに対する免罪符にはならない。この作品ではあくまでも誇張を排して、自分の作り上げた第三帝国の最期に直面したありのままのヒトラーを描こうとしているのだと思う。

軍事的、戦史的なことはこの作品の重要な主題ではない。
歴史上の出来事を取り上げているため、ヴァイトリング、モーンケ、ヴェンク、シュタイナーなどの将軍や、シュペーア、ヒムラー、ゲッベルス、ゲーリングなどのナチスの幹部など、実在した人物の名が多数出てきて混乱しやすい。そのあたりの知識を少しでも仕入れてからこの作品を観ると、より分かりやすいと思う。
また、ヒトラーは軍事的には素人だったことに加え、側近のヨードル大将やカイテル元帥の偏狭な態度が戦況を悪化させたこと、ナチスの幹部間には絶えず権力争いと責任のなすり合いが生じていたこと、国防軍は比較的ナチズムに毒されていなかったため、陰ではヒトラーを伍長呼ばわり(ヒトラーの軍人としての階級は伍長クラスどまり)して軽んじる風潮が一部であったことなどを知ったうえで見てゆくと、この映画がいっそう興味深く思えるかもしれない。
ヒトラーは、あくまで戦い抜くか、さもなければ国民もろとも死を選ぶことを頑強に主張しており、彼のベルリン地下要塞は狂信的なナチズムと、ナチズムに対する投げやりな服従に満ちていた。東西両面から押し寄せてくる敵や「敗戦」などの、負の現実から目をそらそうとしているかのような空気が漂っている。しかし、ヒトラーの死の直後、部下たちはいっせいにタバコに火をつける。この場面は、ヒトラーの自殺で要塞内がヒトラーの呪縛から解放されたことを暗示しているようだ(ヒトラーは禁酒・菜食主義者で、タバコも嫌っていた)。
そして、最後までヒトラーに忠節を尽くしていたゲッベルス夫妻の自殺で、実質的にヒトラーの「第三帝国」は終焉を迎えるのである。
なんらかの思想を通じて歴史を振り返るのはとても危険なことだと思う。歴史はありのままに歴史として見なければならない。この映画も、そういう目で見るべき類のものだろう。
ただ、映画の最後に、トラウドゥル・ユンゲがインタビューに答えてこう語る場面が出てくる。
「私は『自分は何も知らなかった(註:ナチス・ドイツの侵略や、ユダヤ人に対する虐殺などのこと)。だから自分に非はない』と考えていました。でもある日(中略)気づきました。『若かった』というのは言い訳にはならない。ちゃんと目を開いてさえいれば真実に気づけたのだ、と」
この映画を観たあとで、それぞれがヒトラーの善悪や、戦争の是非や、人間の尊厳などについて思いを巡らすことだろう。しかし、誤った前提で考えると正しい答えは出てこない。そう、ユンゲの言葉を借りるなら、「ちゃんと目を開いて」見ることが大事なのだと思う。
人気blogランキングへ←クリックして下さいね