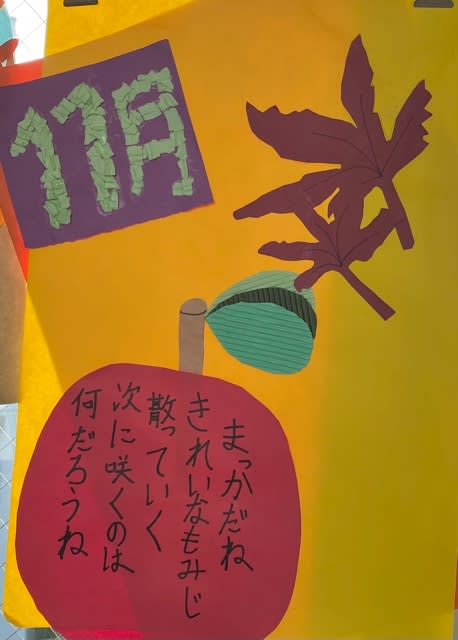毎日新聞10月24日号に、大学3年生の女子学生が書いた「価値を決めるのは自分」という記事がのっていました。全文を引用させてもらいます。
*********************
「価値を決めるのは自分」
不登校になったのは中学2年生のころ。
きっかけは「これだ」といえるものはない。クラスになじめない気分だった。男の子にからかわれた。友人とケンカした。それだけだ。
それまではなんとも思わなかったことが急につらくなった。教室移動で話す人がいなくてさみしい。私のことをみんながきらっている気がする。お弁当のご飯をかむと、ゴムのように思えた。まったくもっておいしくなかった。
そして、朝家を出る瞬間におなかが痛くなった。
学校に行くのをやめた。母には「おなかが痛い」とうそをついた。それが続くと、母は心配した。
私が「腹痛」だけでなく「熱っぽい」と言ったので、熱中症でないかと心配したこともある。
そのうちに「何かあったの」と聞くようになったが、自分で原因と思えるものがなかったので、話すことができなかった。
母はおそらく、私が病気でないことに気がついていた。でも、私は「何もない、おなかが痛い」とだけ言って突き放した。ひどいことをしたと思う。
友人からメールも来た。でも、学校に行っていないこと後ろめたくて返信できなかった。
かなりきつい内容のメールがきたこともある。つらくて、悲しかった。私の心は凍った。
私は家から出なくなった。出かけても、同い年くらいの人を見かけると、私のことを悪く言っているように感じて顔をあげられなかった。誰かに会うことが怖くて真夏でもマスクをした。雨でもないのに傘を差したこともある。
顔を見られたくなくてビクビクしていた。こんなおかしな格好をしないと出かけられない自分が情けなくて、涙が止まらなかった。
とにかく寝ていた。涙が止まらず、テレビを見ることと本を読むことに集中した。一生分の涙を流したと思う。寝ても、夢を見て泣いて、目がカピカピだった。
「明日は行こう、勉強が遅れてしまうから」とずっと思っていた。塾には同じ中学校の子が1人しかいなかったので、勉強の遅れが気になって行った。学校の最寄り駅には近づくことすらできず、学校の人があまり使わない駅を使った。
母からは「そんなに隠れるように生きなくてもいいじゃない」と何度も言われた。あきれたような感じのこともあったけれど、母も焦っていたと思う。「私の育て方が悪かったのかもしれない」とつらかったと思う。
でも私は当時、過敏になっていて、母のブーツの足音さえ気になって怒ったこともあった。私も母も、互いにつらくて仕方がなかった。
中学2年生の2学期から神戸市の適応指導教室に通うようになった。居心地はよかった。通っている子とも仲良くなり、今でも連絡を取っている。
不登校を何回も繰り返した。でも、このまま家にいて将来どうするんだろう。勉強したい。
そういう思いも強くなって、大学に進んだ。学校にちゃんと行けるようになったのは大学に入ってからだ。
高校までは「学校に行く、行かない」が、いつも話題の中心で、会話に出なくても頭のどこかで学校のことを意識していた。
ところが大学の友人が、休んでユニバーサル・スタジオ・ジャパンに遊びに行っているのを知った。許されるんだと思えた頃から、気持ちが楽になった。学校を休むことを気にする人なんて、そんなにいないのだろうと思えた。
小学校の時、担任の先生が「学校に来ていないのに遊びに行くのはルール違反だ」と言っていたことを私はずっと引きずっていて、不登校は〝犯罪″ぐらいに思っている時期もあったので、その発見は大きかった気がする。
単位をとれれば、あとは自分で調整していいんだと思えた。大学で私は、出席をとる授業は休んだことが1回しかない。不登校時代とは正反対の生活になった。
コロナ禍で、「学校に行きたい」というこどもばかりが取り上げられていたことに違和感を持った。私は決してそうではなかったので。
夏でも外出時にマスクをすることは、少し前までは「おかしいこと」だった。この夏はマスクをすることが当たり前だった。
不登校のころ「どうしていつもマスクをして隠れるように生きるの?」と言われていたのに、「なるべく出かけないように」「出かける時は必ずマスクをしなさい」が世間の声となった。
人の価値観は、状況によって驚くほどに変わる。私は無責任なものに振り回されていたのでは、と不登校のころを振り返って思う。
不登校だったことを話せるようになったのは、大学入試のころからだ。「それが個性だし、アピールポイントにもなるんだよ」と塾の先生に言われたことがきっかけだ。
自分自身が「不登校」というマイノリティになっていたからこそ、世の中でつらい思いをしている人を少しでも救いたいという気持ちも芽生えた。
コロナ禍になる前、小学校の時のタイムカプセルを掘り起こした。長く会っていなかった友人に会った。不登校だったことについて言われたらどうしようと、少し気が重かった。だが、それは話題に出ることもなく、小学校の時の話や、大学の話で盛り上がった。
不登校だった時は、学校という社会しか見えていなかった。しかし今は違う。アルバイトやサークル。私の世界はいつしか広がっていた。
つらくてしんどくて泣きながら眠った日々のことも、今となっては必要な時間だったと思うようになった。
不登校だったころ、あの人がいなければ、と思ったこともある。でも、そう思えば思うほどつらくなった。
今、誰かを責めるつもりはまったくない。なぜなら、誰もがストレスを抱え、誰もが人を傷つけてしまうことはあると思うから。
いま、かつての私のように学校に行くのがつらい人もいるだろう。その気持ちを無理に変える必要はないと思う。
つらい時は「つらい」と言葉にしてもいい。私は泣くことでしか表現できなかった。何がつらいかわからず、言葉で表現できなかった。でも「何があったか」だけでも言葉にしていたら、楽になれていたのではと思う。
人の価値観は変わる。学校のあり方も変化する。そんな変化する社会でどう生きていくのか。不登校だったことを強みにするのも、弱みにするのも、私なのだ。価値を決めるのは、たった一人、自分だけだ。
*********************
彼女の書いた「価値を決めるのは自分」を読んで、私は次のような感想をもちました。
ご本人にとって、不登校だったころに、「なぜ、学校にいかないの」と誰かから聞かれても当時はきっと答えることができなかっただろうと思います。
そこまでの気持ちの整理はついておらず、ただ学校行けないことがつらくて、それがつらく悲しいことであり、それが彼女のすべてだったのです。
長い、長い道のりをくぐりぬけ、大学生になって、あたかも第三者が客観的に自分を見つめることができるようになったとき、つらいとか悲しいという感情から離れ、人は自分をふりかえることができます。
そのように自分を見つめることができるようになると、彼女は「今となっては(自分に)必要な時間だった」と思うようになったとまで書いています。
自分を客観的に見つめることができるようになることが、思春期の人がたどりつく、「おとなへの成長」だと、私は常々考えています。
また、彼女は学校の先生という存在についても書いています。
小学校の担任の先生が「学校に来ていないのに遊びに行くのはルール違反だ」と言っていた言葉を、彼女はずっと引きずることになりました。
小さな子どもにとって、先生の言葉はたいへん大きな意味を持つこともあります。教員は、この事実をあらためて再認識して、ものごとの見方や価値観について、偏った伝え方をしないようにしてほしいと思います。
一方で、先生の言葉は、子どもの気持ちを180度変えることもできることもあります。
塾の先生が不登校について「それが個性だし、アピールポイントにもなるんだよ」と塾の先生に言われたことは、「そう思えばいいのだ」と、ものの見方を大きく転換させることになりました。
私も、先生という存在の大きさを、マイナス面でもプラス面でも再認識した次第です。
彼女はとくに変わった中学生ではありませんでした。最近の中学生が多かれ少なかれ経験する学校生活を送っています。
彼女が抱いた感情や気持ちは、程度の違いはあれ、他の中学生も感じます。
その意味で、不登校になるのは、けっして特別なケースではないのです。
どの子も人間関係等でストレスのたまる世の中・社会・学校のなかで生きているからです。
学校の先生は、学校に来にくい子、不登校の子の「つらい」とか「苦しい」、「悲しい」という気持ちに寄り添い、その子たちを支える存在になってほしいと、彼女の手記を読んで思います。