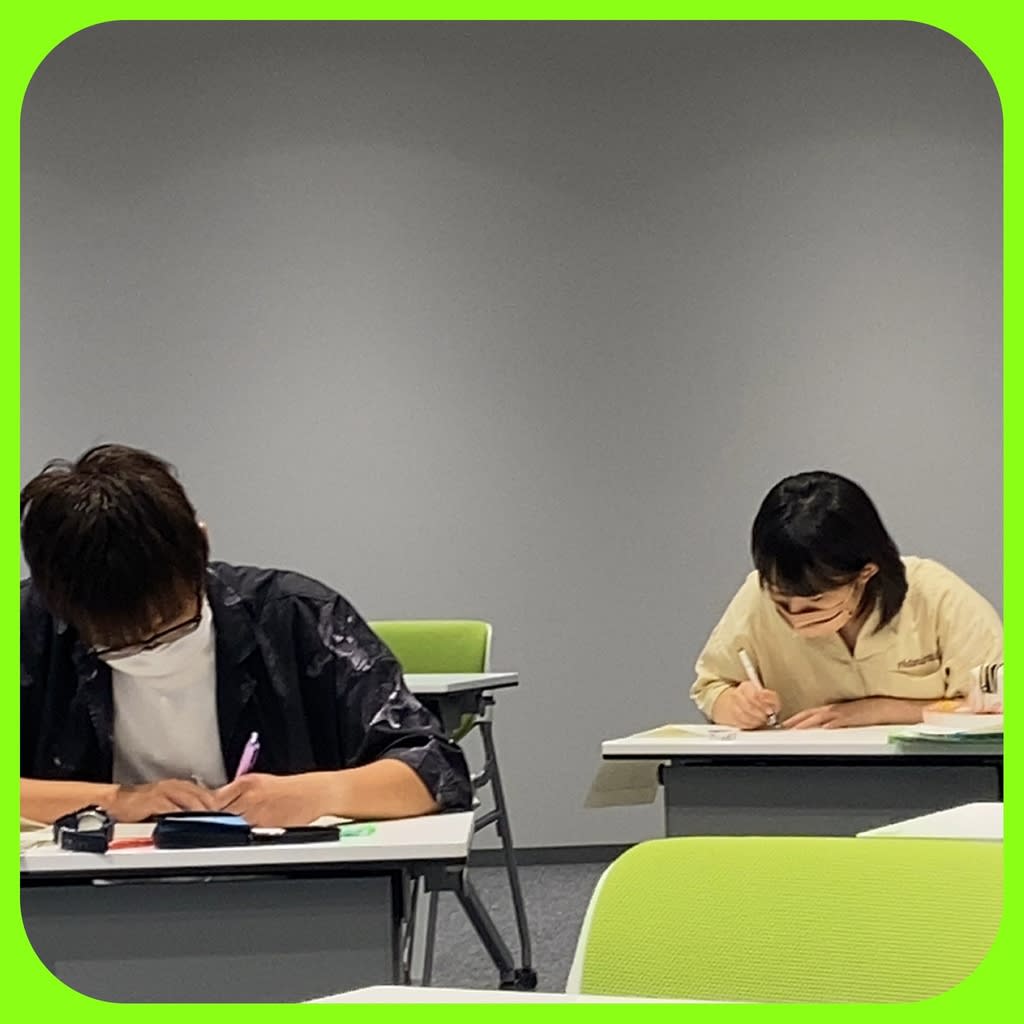2021年に国が6歳未満の子どもをもつ共働きの夫婦の家事・育児時間を調査しました。
夫は1時間57分/日で妻6時間32分/日でした。
この結果を見ると日本では家事・育児は依然として女性が担っていることがわかります。
内閣は2022年に「スタートアップ育成5カ年計画」をまとめました。
新しく起業したベンチャー起業には10兆円の年間投資を与えると発表しました。
ところが、起業の新設率はアメリカ・ヨーロッパでは1年に10%、中国で20%ですが、日本は5%です。
つまり日本では新興の企業がなかなか生まれないのです。
日本は起業が身近でなく、日本の経済が低迷しているにも関係します。
起業するには事業計画を作り、収支を試算したりしてとても準備に時間がかかるのでたいへんです。そして起業できても経営に大きな負担がかかります。
そこへ日本で女性が起業をするとなると、家事育児をおもに女性が担っている現状が重なり、女性の起業は限りなく厳しくなります。
2021年に国内で新しく上場した企業のうち、女性が経営トップなのはわずか2%しかありません。
諸外国と比べて、圧倒的に低いですが、いまや女性を経営トップにしない企業は世界では通用しなくなっています。
そもそも、起業に向けた意識の低さも影響してきます。起業に関心のないという人が5割を超え、男女とも低いのです。
女性のほうも「私なんて・・・」と卑下する人が多いのが現状です。
起業家には性別に関係なく、家事代行や秘書サービスをつけるとかして、起業家の負担を減らし、起業家一人にリスクを負わさないようなサポートをしないと、起業したいという人は増えないでしょう。
1950年代に起きた朝鮮戦争の結果、韓国は荒廃した国土になりました。
その当時、市場経済主義および民主主義を求める韓国にとって、日本は戦後復興から立ち上がる兆しがある国で、日本経済を学ぼうという対象でした。
韓国の企業は、その頃日本の技術者を工場に招き、そのノウハウを身につけようとしたのでした。
そしてサムスン電子は、日本の三洋電機の助けを受け、電子産業に進出することができました。
その後、サムスンは、現在スマートフォンでは、アメリカのアップル社と世界1,2位を争っています。そして、半導体メモリーでは世界1です。
電子・電機産業だけではありません。
音楽でも1990年代のはじめに韓国式ロックやヒップホップを流行させ、K-POPの独特な位置を築きました。
過去の日本が韓国に対して行ったの負の歴史から、「日本が嫌い」という韓国人がいますが、幸いにも日本人との交流を楽しみに待っている韓国人はいます。
2023年に日本を訪れた韓国人は600万から700万だったと言われています。
いま、コスメやフード、そして音楽で日本と韓国はいい刺激を与え合っています。
今後、日本と韓国は地理的に一番近い隣の国として経済圏を構成し、共存共栄をしていく未来像が見えています。
珠洲市もまわりました。珠洲ではバスに乗って景色を見ていると、夏祭りに使う「キリコ」が見えました。添乗員さんが説明してくださいました。
たいへん勇壮な祭、100人ほどの若い人が大きなキリコを担ぎ、海の中を乱舞する祭だそうです。
聞き及ぶところでは、今回の能登半島地震で保管してあったキリコが大きく破損したり津波で流されてしまったそうです。
夏祭りでもうキリコは出せないと、地元も関係者は言っています。
また、輪島の朝市もまわりました。たくさんの人で賑わっていて、とくに伝統産業の輪島塗は目をひきました。
今回の地震で、壊滅的な被害を受けたと聞きます。

デザインや原木の土台づくり、漆塗りを施す工房や店舗が被災しました。300ほどの事業所はほぼすべて被災しました。分業制なので、再開のめどは立たないそうです。
漆塗りの産業自体が存続の危機に瀕しています。

旧ツィッター(現X)を匿名やニックネームで利用している人の割合。
日本 約75%
アメリカ、イギリス、フランス、韓国、シンガポール 3割~4割台
突出して日本が多くなっています。
なぜ日本では実名のアカウントをつかう人が少ないのでしょうか。
それは、個人と周りの関係が自由でなく、窮屈なものだからと考えられます。
「こんなことを言っている(書いている)」と揶揄されやすく、非難されやすい、叩かれるという日本社会の特徴をあらわしているのです。
しかし、一方で日本では絆や団結という言葉がもてはやされます。災害が起きたときにはなおさらです。
わたしはその価値を否定するものではないのですが、これは、絆や団結がもつ負の側面である、人を縛ろうとする同調圧力が働くという点が、あまりにも絆や団結を強調することで見えなくなってしまう。
そのことには気をつけておきたいものです。
今の日本では、多様性(ダイバシティ)や包摂(インクルージョン)の取り組みが、以前よりも進んできました。
それらは学校教育の中では、人権教育で、とくに大阪では集団づくりの分厚い取り組みとして、実践されてきました。
「ちがいを豊かさに」という多文化共生教育で外国につながる児童生徒を集団に据えた在日外国人教育教育。
障害のある子とない子がともに同じクラスで学習したり生活を送る障害児教育。
男女が対等な立場で共に生きる男女共生教育・ジェンダー平等教育。
被差別地域の児童生徒への学力保障・進路保障を核とした集団づくり。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
などの、分厚い教育実践があります。
少数派(マイノリティ)の抱える人権課題は、多数派(マジョリティ)が生みだしている。
平たく言えば、差別される人がいるのは、差別する側の問題であるという考え方が人権教育推進の基本的な考えです。
さて、マイノリティについて、社会の意識も変化が出てきています。
たとえば、東京パラリンピック以降、企業が選手を広告に起用することが増えてきました。
SDGsを進める企業からの投資も増えてきました。
SDGsのシンボルであるピン・バッジをスーツの襟元につけたビジネスマンをよく見かけるように、「我が社はSDGsを推進する企業です」という打ち出しも盛んです。
そのような企業の取り組みは、今の企業活動のあり方が社会貢献が評価されるという時代背景を受けています。
企業としてのイメージアップにもつながります。
一方で、ダイバシティやインクルージョンのかけ声が響く中で、社員の中には「やらされ感」をもつ人も増えているのが現実ではないでしょうか。
「上司に命じられたから」という理由で、本意ではないが取り組みに加わっている人もいるようにわたしは思います。
以上のことより、日本社会でのマイノリティ尊重をめぐる意識は、前進と後退を繰り返しているのです。
その繰り返しの中で、「ゆらぎ」も出てきています。
国会議員の問題発言、ヘイトスピーチ、インターネットへの人権侵害書き込み、パワハラ、セクハラなどは、そのゆらぎの表出と考えることもできます。
そもそも「わたしはマイノリティ」「わたしはマジョリティ」のように、きっちり区分できるものではないのです。
「わたしは学校の成績がよくないから、学力マイノリティ」「わたしは勉強ができるからマジョリティ」と仮にしたとします。
でも、勉強ができても運動が苦手な場合もあります。その人は「運動マイノリティ」と感じるかも知れません。その逆もあります。
エレベーターを使わないと電車に乗れない車いすの人なら障害者というマイノリティ。でも車いすを使っていなくても、階段を上り下りするのがたいへんな高齢者もいます。
ですから、どんな人もマイノリティであったり、マジョリティであったりするのです。
わたしたちにとって本当に必要なのは、マジョリティの立場ととマイノリティの立場の両方で、どちらかだと「平面」としかみえなかった世界が立体的にみえてきます。
そこから新しい人間関係がうまれることを知ること、つながりが生まれることでないかと思うのです。