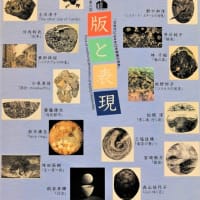今月5日。ひさびさに習志野市の谷津干潟にの渡りのシギ・チドリ類を観察しに出かけた。毎年、ゴールデンウィーク前後は繁殖地へと向かう水鳥のシギ・チドリ類が日本列島の干潟や水田などに立ち寄っていく時期にあたり観察のベスト・シーズンとなっている。この時期に1-2回は谷津干潟を訪れるのが僕自身の年間行事ともなっている。
僕が野鳥観察を始めたのは今から〇十年前、高校二年の冬に東京湾岸の干潟に友人に誘われて冬鳥のカモ類や猛禽類を観察に行ったのがきっかけである。当時はまだ『バード・ウォッチング』という外来語が耳慣れず、市民権をようやく持ち始めるところだった。ただ、この延々と広がる埋立地に泥を運ぶサンドパイプが伸び、大型ダンプカーが砂埃をたてて走り回っていたのをよく憶えている。そして、大規模な自然破壊の象徴でもあるこの地から野鳥観察を始めたことが、その後の僕の自然観を決定してしまったと言っても過言ではない。高度経済成長の真っただ中にあって、かつて渡り鳥の一大中継地として世界中の鳥類学者の注目を集めていた東京湾周辺の水辺は、「開発」の名のもと、見るも無残に破壊されていた。それでも野鳥たちはその片隅に残された水辺環境で生き続けていたのである。初めて望遠鏡越しに観た水鳥たちの美しさの虜となり、以来、ずっと通い続けることになって今日まできている。
この日は『大潮』。予報では谷津干潟は昼ごろ干潮で午後から夕方に向かって満潮となっている。干潮時に干潟全体に分散していたシギ・チドリ類は潮が満ちてくると近い距離に集まってくる。つまり、ちょうど良い観察日和ということである。昼ごろに干潟の北側に到着するといつものように時計回りに周遊路を歩き始める。双眼鏡で干潟全体をを観まわすがシギ・チドリの姿は少ない。ダイゼン、キアシシギ、チュウシャクシギが少し観られただけ。「今日は欲をかかずにノンビリと観ることにしよう」。日陰のベンチで持ってきた昼食をすませ東岸から南岸に向かってさらに歩いて行く。午後二時過ぎ、ダイゼンとキョウジョシギの60羽ほどの混群が飛んできた。東岸の干潟にはハマシギとメダイチドリの小群が近い距離で観られた。潮が満ち始めるまで、まだ時間がある。観察センターの先の淡水池を覗いて来ることにしよう。
淡水池ではたいした収穫はなかった。時間となったので南岸の四阿にもどる。干潟の中央に真っ赤な夏羽となったトウネン11羽とチュウシャクシギが31羽観られた。今日はチュウシャクシギをよく観る。四阿に集まって来ていた鳥屋さんの中にここでよくお会いするK氏を見つけた。挨拶も早々、鳥情報をお聞きすると「昨日は夏羽のオオソリハシシギ数十羽が目の前に並んだんだけど、今日は1羽も見ない」とのこと。まぁ、そーゆーことはよくあるんだよね。タカの仲間でも出現したのかなぁ。しばらく雑談をしていると水路からグングンと潮が上がってきたので、最後にシギ・チドリが集まる東岸のポイントに向かう。
東岸のポイントに集まってくるシギ・チドリを望遠鏡で観察していると、後ろからここで長く野鳥のカウント調査を続けているベテラン・バーダーのI氏と鳥類図鑑画家のT氏夫妻がやってきた。ひさびさの再会で鳥談議に話がはずんだ。いつの間にか日入りの時間も近づいていた。今日はこの辺でタイム・オーバーとなったのでみなさんに挨拶して帰路に着いた。最後に残された夕暮れの干潟ではシギ・チドリ類の哀調をおびた声が響き渡っていた。画像はトップが満潮時に集まってきたシギ・チドリ類。下が向かって左から北側から見た谷津干潟、チュウシャクシギ、メダイチドリ。