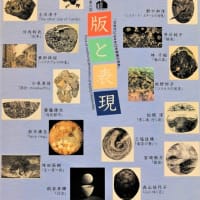梅雨明け以来、酷暑が続く毎日だ。先月中旬のことである。美術家で友人のF氏と千葉県の北東部に自然観察に出かけた。F氏とは野鳥を通じて知り合ったのだが、昆虫や天体にも造詣が深く話をしていて楽しい。F氏の愛車で移動する道すがら興味深い話をたくさん聞くことができた。
最初に訪れたのはF氏ご推薦のトンボ観察スポットでH町のH沼という場所。現地に到着すると、バス・フィッシングの人や昆虫採集の親子連れなどが忙しなく動き回っていた。さっそく車を止めて、はやる気持ちを抑えつつ、観察用具やカメラを担いで繰り出した。頭上を見覚えのあるトンボが群れで飛んでいる。「チョウトンボだ!最近、農薬散布の影響か近所の印旛沼周辺でも少なくなったなぁ…」 紫、青、緑と光の方向によって微妙に色彩が変化する金属光沢の美しい羽をキラキラと輝かせて飛び回っていた。幸先が良い。始めにF氏が『秘密の水路』を案内してくれた。「ここは全国的にも数少ないイトトンボ科のオオセスジイトトンボ(Paracercion plagiosum)とオオモノサシトンボ(Copera tokyoensis Asashima,1948) の貴重な生息地なんだよ」と、F氏。僕はトンボの中でもイトトンボは似ている種類が多く同定が難しいので苦手としているグループだ。
F氏は野鳥を観察するときでもかなりジックリと見る方だが、今回も水面をジーッと静かに見つめている。「いたよ!オオセスジイトトンボの雌雄が交尾をしている、とても近い」指を指してもらったがヨシや浮草に紛れてなかなか見つけることができない。ようやく周囲の目印を教えてもらって見ることができた。繊細なトンボである。♂は明るいブルー、♀はイエローグリーンとなかなか美しい体色をしている。1カップルを見つけると環境に目が慣れ昆虫の目線になってくるせいか次々に見つかってくる。結構数がいる。そーっと近づいて夢中でカメラのシャッターを押した。次はオオモノサシトンボである。こちらもしばらくして見つかった。体色に黒が多いせいかなかなか渋い装いのトンボだ。一頭、じっとしていて逃げない個体がいたのでじっくりと撮影することができた。
木陰で昼食を済ませてから再びF氏の案内で今度はブッシュを掻き分けてミドリシジミの観察ポイントに移動するが、時期が早いのか、時間帯なのか見つけることができなかった。あきらめて沼の奥地を探検することにする。釣り人がつけた狭い道をたどりながら沼沿いに移動するのだが、ここは周囲が林に囲まれその中を小沼がいくつも連続していて散策しているだけでも楽しい。上記の他にショウジョウトンボ、コシアキトンボ、クロイトトンボ、ノシメトンボ、ウスバキトンボ、ギンヤンマ、コフキトンボ、などこの地域の普通種のトンボやその他、昆虫、クモなどを数多く観察できた。ここはまさに『トンボ王国』である。元来た道を車までもどるが引き上げるにはまだ早い。このあと、九十九里方面に移動し海岸の砂丘地帯にあるコアジサシとシロチドリのコロニーを観察、さらに移動しつつゴールは北印旛沼でサンカノゴイ、ヨシゴイなどヨシ原のサギ類を観察して帰路に着いた。梅雨の晴れ間、ひさびさにゆったりと自然を堪能する時間を持つことができた。案内をしてくれたF氏に感謝。画像はトップがオオイトトンボの交尾。下がオオモノサシトンボ、チョウトンボとH沼風景。