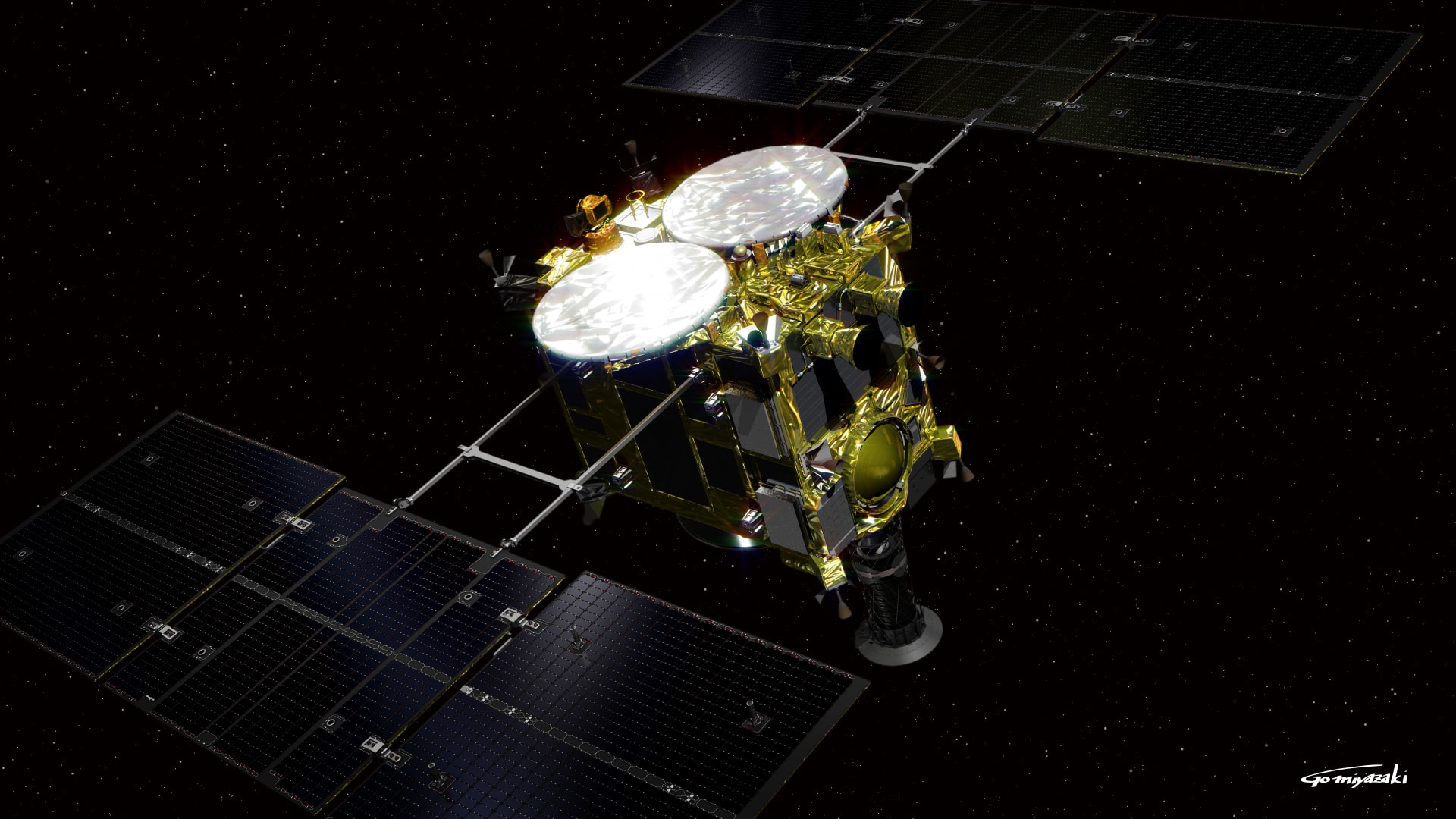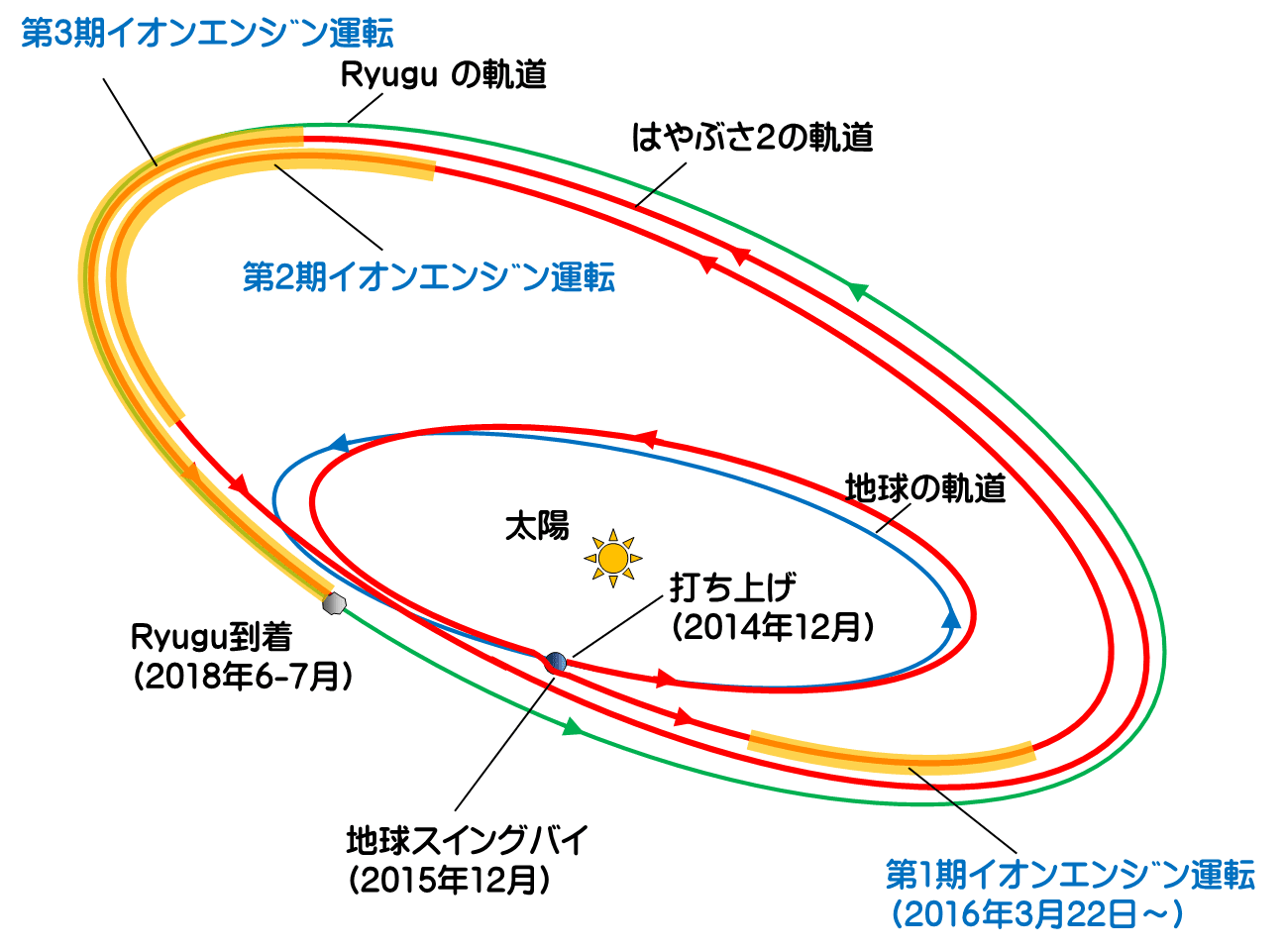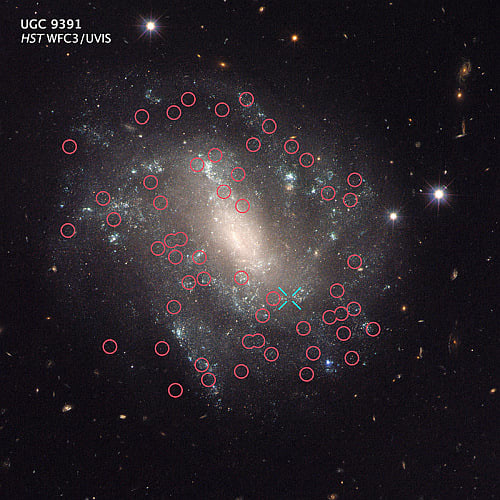再使用可能なロケット開発でしのぎを削る、
イーロン・マスク氏が率いるスペースX社と、
ジェフ・ベゾス氏が率いるブルー・オリジン社。
そのブルー・オリジン社が、
次回、興味深いテストを行うんですねー
それは、着陸中の宇宙船を意図的にクラッシュさせること。
有人飛行を見据えた安全性能の確認になるそうです。

安全装置
このテストでは、
宇宙船“ニュー・シェパード”に搭載されたパラシュートに不具合を発生させます。
もちろん宇宙船は、
パラシュートのトラブルの際にも生還する必要があります。
なのでトラブル発生時に備えて、
いくつかのフェールセーフ機能(安全装置)を搭載することになります。
ブルー・オリジン社は、
2018年には民間企業による宇宙飛行を目指しているので、
フェールセーフ機能は必須の仕組みになるんですねー

どんな仕組み?
まず、次回のテストで想定するのは、
1つのメインパラシュートが動作しなかったケースになります。
このトラブルが発生すると、地上にかなり近づいた時点で、
カプセルに搭載された“レトロ・ロケット”と呼ばれる3つの小型エンジンが点火、
カプセルを押し上げようとします。
さらに、カプセルにはショック吸収機構が搭載されていて、
地面との衝突の衝撃を和らげます。
また、乗員にも負荷がかからないよう
シートもショックを和らげるようなデザインになっているんだとか。
ブルー・オリジン社の計画では、
“ニュー・シェパード”は地上約100キロの高度まで打ち上げられ、
乗員は数分間の無重力体験を楽しむことができます。
そのような素晴らしい宇宙旅行が悪夢に変わらないためにも、
今回のようなバックアップのフェールセーフ機能は必須なんですねー
このテストは月末までに行われる予定で、打ち上げられる“ニュー・シェパード”は、
これまでに3回再利用に成功したものを利用するそうです。
こちらの記事もどうぞ
有人宇宙船“ドラゴン2”が、打ち上げ中断システムの試験に成功!
ドラゴン有人宇宙船、緊急脱出パラシュート試験を実施