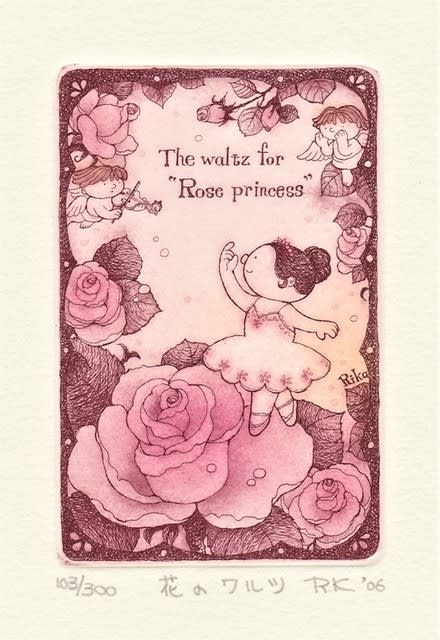あじさいの季節はあじさいの絵を。
遅くなりましたが、朝ドラ「エール」第11週「かぞくのうた」感想です。
冒頭に映る雪化粧の山は磐梯山なのでしょうか?福島といえば磐梯山しか知らず。。。
裕一は妻の音ちゃんの勧めもあり、赤ん坊の「華ちゃん」を連れて故郷に帰ります。さすが音ちゃんの娘、可愛い。めんこい。
それもこれも、福島の藤堂先生に小学校校歌作曲の依頼を受けたからでした。同時にお母さんのまささんからも、実家に寄るよう手紙が来ます。
ほとんど駆け落ち同然で故郷を振り捨て上京して、いまさらどんな顔をして帰省すればいいのやら。。。しかし「船頭かわいや」の大ヒットのおかげで、裕一の名声は故郷にもとどろいていたようです。
音ちゃんと並んで仕事室で校歌を作る裕一が、華ちゃんにデレデレの情けない(笑)姿より印象的でした。以前はあまり一緒に音楽を作る場面がなかったのに、音楽夫婦として一歩前進。「僕が作曲した歌を君が歌う」うらやましー。
音ちゃんは子供を産んでから、なにか落ち着いてきましたね。前みたいにカッとなって感情のままに突っ走るのではなく、忍耐力がついた?子育ては親をも成長させるのかな。
ダンナの実家で、お姑さんと和解しかいがいしく内助の功を発揮する音ちゃん。たすきがけも素早く、福島の味噌汁にもいち早く順応。出来たヨメじゃ。田舎の宴会ってさー。女はお酒の燗仕事ばっかで腹立つのよね(笑)。
しかし昔は布オムツだから、毎日の洗濯が重労働だったろうな。お産の時のシーンで、裕一のワイシャツを干してる下に木のタライと洗濯板が。
クリーニング屋さんってないはず。。。(母の証言では、都会にはあった、と。高かったそう)。
裕一さん、毎日バリッとしたスーツ姿で出勤してるから、あのシャツ、洗濯板でゴシゴシやって、アイロンあてて…アイロンは炭を入れるタイプでしょうか。それとも電灯からコード引っ張ってくるヤツでしょうか(サザエさんで見たよ)。襟は糊しないとピン!としないし。そしてプラスオムツかー。はー。たいへん。
裕一さん、オムツ交換は手伝ってるようですが、甘いわ。お風呂も入れて、たまには離乳食も作ろう(笑)。
福島での校歌お披露目の会で、あの川俣銀行の昌子さんと結婚した藤堂先生と再会。
「人よりほんの少し努力するのが苦しくなくて、ほんの少し楽に出来るもの、それを見つけたらしがみつけ」という、藤堂先生の教えを裕一は守り抜き、故郷に錦を飾ることが出来ました。といってもまだ故郷出て3年ぐらいじゃないのかな。
史実では古関さんは「5年間ヒットが出なかった」そうなので、ドラマでは少し短縮。それでも20代半ばで結果を出せたのだから、芸術家の成功としては超早いです。
実家ではあの蓄音機で三郎父さんがレコードをかけ、華かやに祝賀パーティ。喜多一はもう閉店してて、かつての番頭さんもお祝いの座に来てくれました。あの、裕一に啖呵を切った丁稚どんはどうしたのだろう。「ブッブッブッブッ」とバス・ハーモニカを吹いていた元・いじめっ子の学友の姿も。
私はこの「故郷に錦を飾る」場面が、見たくてたまらなかったので、感慨ひとしおです。恩師に恩返しを出来たのが嬉しいのです。
川俣銀行の愉快な仲間たち、は今はもう信用組合に転職していました。茂兵衛おじさんの銀行も人手に渡ったということ。
自分の身勝手な行動が親族のみならず多方面に影響を及ぼしていたことを知り、暗い表情になる裕一。そこへ帰ってきた弟の浩二に声をかけるも、以前にも増してきつくあたられます。
BSプレミアムで土曜に1週間分を再放送してるのですが、続けて見ると、裕一の福島での心情変化がよく解ります。
華やかな凱旋ではじめはピカピカに輝いていた顔が、弟との軋轢で曇り、週末には死相が出てるかのような憔悴っぷり。
それもそのはず、三郎父さんは、胃ガンを宣告されていたのでした。
母と弟はお金を工面しながらも、本人には知らせまいと必死にがんばってきたのです。
そこへ、何も知らない兄が、可愛い嫁と子供と仕事の成功をともなってノコノコ帰ってきたら、弟としては苛立ちしかないでしょう。お前が好き勝手やってるうちに、実家はどれだけ苦労した思てんねん!てなもんでしょう。
裕一はお金を渡そうとして、なおさら反発を食らってしまう(あれは、お母さんが寝る前にでもコソッと渡しましょう。浩二のプライドを考えよう)。
私も、自分と姉との確執を重ねて見てて、浩二の苦しみが痛いほど刺さりました。親ってなぜか「放蕩息子」のほうを可愛がる。
浩二からしたら、長男なのに義務を果たさず家を捨ててる裕一を、両親が可愛がる姿が腹立たしい。
真面目に実家に貢献してる自分が、あまり褒められない。
でも、親からすれば、真面目な子は手元に居て「心配がない」ので、ある意味気を使わない。放置する。
放蕩してる子は離れて生きているから、泣いたりしていないか、路頭に迷っていないか、心配でたまらない。
三郎父の臨終の床で浩二は、「父さんと兄さんが音楽の話してるとき、俺は入っていけなくて悲しかった」とつぶやきます。
しかし、父は「裕一とは音楽の話しか接点が無かった。でも、俺とお前は別に何もなくても、本音で言い合えた」と返します。
親は子を両方とも愛していて、ただ接し方が違っただけだ、と。
これが意外な答えで、三郎さん、もっと早く(元気なうちに)浩二に言ってあげればよかったのに。。。
と思えども、人生ってこんなものかな。
まだ、古山家は「間に合った」から良いのです。ちゃんと心の澱を溶かして終われたのですから。
家督を譲る話、長男である裕一に謝る姿、浩二に「裕一に了解はとってあるから全財産をお前に」と告げる姿。
父の最後の威厳と優しさを、唐沢寿明氏、さすがの年の功演技で魅せます。
思えば、高価な蓄音機とレコード・譜面を与えて、得意(音楽)を伸ばし不得意(運動・勉強)は大目に見てくれた三郎父。
商売の才は無く上手くは生きられなかったけど、最大限の応援をしてくれた父を失い、でも自分の子供は生まれた。
「親を失ったが自分は親になった」瞬間が、「子供時代の終わり」なのですね。
一人で奏でる裕一の悲しい音色のハーモニカ。
親友が去ったとき、祖母に裏切られた時、いつも、悲しい気持ちは、言葉でなく音楽で吐露する裕一。
あんなに怖かった茂兵衛おじさんは、引退?して趣味三昧の日々のようで、なんと裕一たちを祝ってくれました。
奥さんはまだ寝たきりなのか、お祖母さんはどうなったんかな。でも、最大の難関はおじさんだったので、クリア出来て良かった良かった。
もうひとつの難関、弟の浩二とも、これからは上手くいきそうです。
この週は「裕一が故郷に残してきた宿題を片付ける」テーマと同時に、「弟の氷解」が進行しましたが、農協に転職した浩二の営業マンっぷりが初々しくて良かった(笑)。公務員に中途転職出来たということは、浩二は頭も優秀なのね。
この先、裕一が福島に帰るタイミングは、戦争で疎開する時だと思うのですが、その頃には一面リンゴの花が咲いていて、浩二は「福島にリンゴ栽培をもたらした名士」となっているのではないかと予想。
「兄さんはもう家族じゃない(怒)」状態から、「兄ちゃん、上手くリンゴ出来たら贈っから(照)」となって、ホンマに良かった。ほんとのところは、「兄ちゃん」が好きなんだよね。未だに捨ててないスノードームが、浩二の気持ちを物語っていたり。
福島の大事な場面は、いつも自然描写が美しく印象的です。
大将(鉄男)を思いながら泣く幼い頃は、山の向こうのはるかな空。
音さんと別れ留学を取る決意をしたときは、萌える緑の中、蝉の大合唱。
故郷を捨てて父と別れた時は、紅葉の中。
そして今回は、無彩色の冬。
白いしだれ梅、音もなく舞い落ちる雪、赤い椿の一輪。
華やかだった喜多一の実家が、寂しく小さく見えて切なかったけど、新しい時代の幕開けのようにも見えました。もう、浩二が「家長」です。
余談ですが、浩二が農家のマキタスポーツに差し出した「リンゴ栽培企画書」が、いかにも「Wordで作りました」感があって、ちょっと笑ってしまいました(笑)。
昭和初期に農協の企画書だったら、活版印刷はあり得ないと思うので、普通ガリ版刷りではないでしょうか~。NHKの美術様、いかがなのでしょう。高校までガリガリ鉄筆で文集作ってた私は、ちょっと納得いかん★