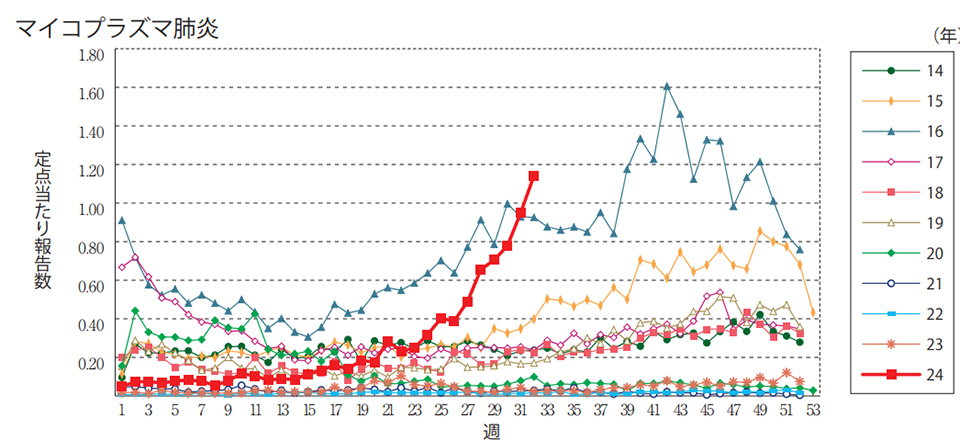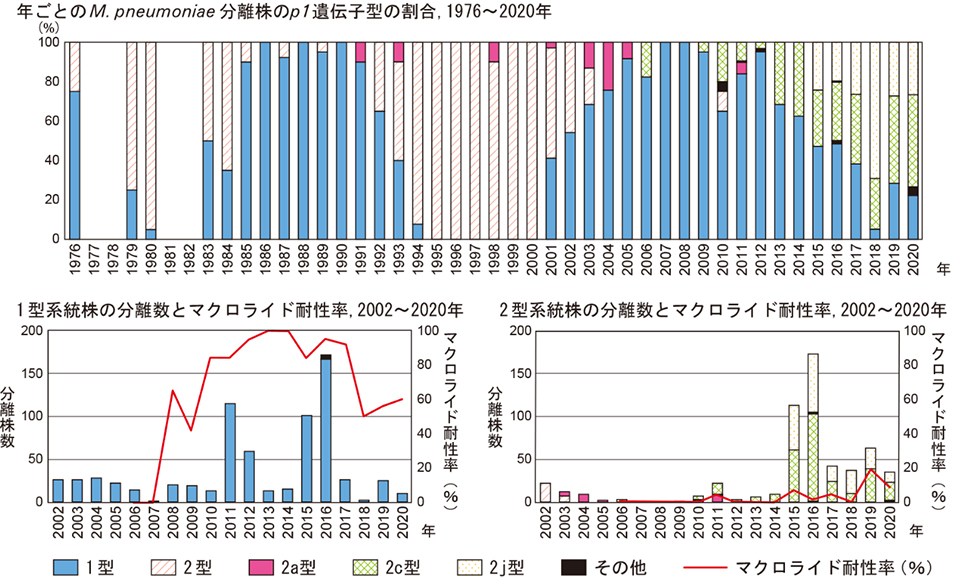10月15日(火)に地域の基幹病院呼吸器内科から転院依頼がきた。当院の呼吸器科外来(大学病院からの応援医師担当)に慢性呼吸不全で通院している70歳代半ばの女性だった。在宅酸素療法(HOT)が導入されている。
電子カルテ(2016年導入、それまではオーダリングだけ)で確認すると、2002年から2008年まで当院の呼吸器科外来に通院している。
最初は非常勤医の外来で、気管支拡張症としてマクロライドのエリスロマイシン300mg/日が処方されていた。2年後の2004年から呼吸器科の常勤医が診ていて、クラリスロマイシン200mg/日に変更された。
2008年に呼吸器科医が退職して閉科となり、市内の内科医院に紹介になったらしい(診療情報提供書の記録はなかった)。
2022年に顔面神経麻痺で当院のい耳鼻咽喉科でステロイドを使用したが、2日後に肺炎があることに気づかれて、内科に紹介された。この時は当時相席した自治医大卒の義務年限の若い内科医が担当した。
通常の肺炎としてセフトリアキソンを使用したが、原疾患として非結核性抗酸菌症が疑われて、その増悪の可能性も考慮していた。(できる先生だった)
クラリスロマイシン・リファンピシンで開始していたが、呼吸器科外来に来ている先生に相談して、アジスロマイシン・エタンブトールに変更になった。
おそらくセフトリアキソンが効いて肺炎は軽快して退院した。その後は、相談した呼吸器外来の先生に通院していた。現在は抗菌薬は中止となっている。
ただ喀痰検査では非結核性抗酸菌症は証明されていない。喀痰塗抹・PCR・培養は陰性だった。画像診断からの判断になる。直近の胸部X線・CT像は下記の通り。




今回は10月11日(金)の夜に意識障害(昏睡状態)が出現して、救急要請された。通院している当院に搬入依頼が来た。当直はバイトで来ている外部の病院の先生(外科医)だった。内科疾患による昏睡は診れないとしてお断りしていた。
患者さんは基幹病院に搬入された。肺炎を契機にしたCO2ナルコーシスと診断されて、NPPV(non-invasive positive pressure ventilation 非侵襲性陽圧換気)が開始された。
転院依頼がきた段階でもNPPVは継続となっている。NPPVが外せない可能性があり、またいったん改善して外しても、再度NPPV装着になるかもしれない。入院が長期になる可能性があり、専門的治療をしても見込みがつかないので、後は通院している当院で診るようにということだった。
「NPPVまでは行うが、気管挿管・人工呼吸まではしない」という慢性呼吸不全の患者さんに特有のDNARの方針になっていた。早急に転院の手配をしたが、最近は入院ベットが厳しいのと計画停電の予定もあって、18日(金)の転院予定となった。
MEさんとも相談したが、NPPVの器械本体は小さいので装着したまま転院して来るんですかねえ、といっていた。後で器械は外して研修医が同乗して来ると連絡が入った。用手的にバッグバルブマスクで補助呼吸をして来るんだ、途中大丈夫かなあ、という話をしていた。転院時はすぐにNPPVを開始するのでMEさんもスタンバイすることにしていた。
当日になって、前日から病状が悪化して転院はキャンセルになったと連絡がきた。持ちこたえられず悪化していくのか、改善したところでまた転院依頼が来るかわからない。
呼吸器外来は週1回非常勤医担当で、在宅酸素療法の患者さんやステロイド使用の患者さん(急性増悪の可能性の高い患者さんたち)がいる。何度か入院した患者差はわかるが、常勤医が全部は把握していない。外来がある時に入院治療を依頼されるとわかりやすいが、時間外に増悪して受診されると、申し訳ないが日当直医によっては対応できないこともある。