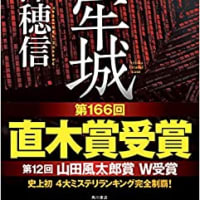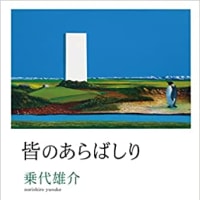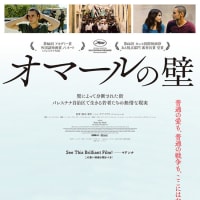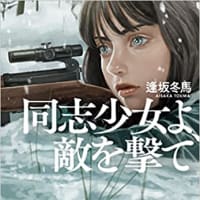映画「NO(チリ=アメリカ映画)」★★★☆
ガエル・ガルシア・ベルナル、アルフレド・カストロ
ルイス・ニェッコ、アントニア・セヘルス
マルシャル・タグレ、ネストル・カンティリャーナ
ハイメ・バデル、パスカル・モンテーロ出演
ロレーヌ・レヴィ監督、
117分 スペイン語 Color, Black & White | 2012年 チリ=アメリカ |
(原題/原作:NO)

<リンク:人気ブログランキングへ">>→ ★映画のブログ★どんなブログが人気なのか知りたい←
第25回東京国際映画祭へ行ってきました。
10/20から28まで開催された恒例の映画祭。
5本目は「コンペティション」部門のチリ=アメリカ映画
「チリに君臨するピノチェト独裁政権の
信任を問う国民投票の実施が決まる。
強者の「YES」陣営に対し、
「NO」陣営は
広告界の若きエグゼクティブを採用して
果敢なキャンペーンを展開する。
88年当時の模様を斬新なスタイルで再現した、
勇気溢れる興奮の政治エンタテインメント。」
(第25回東京国際映画祭HPより抜粋)
映画祭から1ヵ月経って
まだ観た映画を書ききれていませんが、
この映画はガエル・ガルシア・ベルナルの
新作ということでそれだけで選んだ。
長く続くチリの独裁政権の終焉、
信任の国民投票を行う事までこぎつけた
民主化を望む陣営と
これまでの利権を守る政権陣営は
激しいキャンペーンを繰り広げていた。
現政権に「NO」をたたきつける陣営は
そのキャンペーンに売れっ子の広告クリエイターを指名
政治色の薄い出来上がった映像は賛否あったが
新しい風をチリに送るにはふさわしいと
大胆な映像キャンペーンを展開し始める、
焦る「YES」陣営は
様々な圧力をかけ、出来上がったテープを
紛失させるなど妨害を繰り返す。
かなりスリリングなシーンも多く
独裁政権を打倒する困難が伝わる
多くの国でかつて同様なことが行われていた
それを考えれば現在は少しは
国は、政治は成熟し始めているのか、
時々逆行するような事件もあり
人間の繰り返す愚かさを想った。
当時の実際のキャンペーンの映像が流れ
当時を知る人達にインタビューもしたというが
「YES」陣営は積極的に発言してくれたが
「NO」陣営の口は重かったという
まあ、そうだろうが
その時の人々の選択が今に繋がっていると思うと
選挙というものについても
もっと真摯に臨まないといけないんだろうな、
自分達の政治への関わり方も
本当はこんなじゃ、当時の彼らに叱られそうだ。
映像は画面が粗い印象で
一昔前のデジタルじゃない感じと思っていたが
後で資料を見たら撮影にはアナログの
日本製ビンテージカメラが用いられていたそうだ。
それが当時の雰囲気をより効果的にしている
クリエイターってこういうところにまで凝って
それを自分達は僅かな印象の違いで
「なるほど」と思うわけだけど
映画が総合芸術と言われる所以か。
ガエル・ガルシア・ベルナルは一人の個人としても
こういう映画作りに携わる意義を
感じているのかもしれないが
彼らしいところはあまりなく
そのあたりは物足りなかった。
国際映画祭という場にはふさわしい作品だった。
★100点満点で70点★
★この記事が参考になったらココもクリック!よろしく←
東京国際映画祭HP
パブロ・ラライン監督
1976年サンティアゴ生まれ。
2005年に初の長編映画“Fuga”を監督。
次の長編映画『トニー・マネロ』は
08年のカンヌ国際映画祭監督週間でプレミア上映され、
アルフレド・カストロとAntonia Zegers出演の
3作目“Post Mortem”は10年の
ヴェネチア国際映画祭コンペティション部門で上映された。
10年、チリで製作された初のHBOシリーズ「Profugos」を監督。
本作は4本目の長編映画である。
soramove
★この記事が参考になったらココもクリック!よろしく(1日1回有効)←ランキング上昇ボタン
ガエル・ガルシア・ベルナル、アルフレド・カストロ
ルイス・ニェッコ、アントニア・セヘルス
マルシャル・タグレ、ネストル・カンティリャーナ
ハイメ・バデル、パスカル・モンテーロ出演
ロレーヌ・レヴィ監督、
117分 スペイン語 Color, Black & White | 2012年 チリ=アメリカ |
(原題/原作:NO)

<リンク:人気ブログランキングへ">>→ ★映画のブログ★どんなブログが人気なのか知りたい←
第25回東京国際映画祭へ行ってきました。
10/20から28まで開催された恒例の映画祭。
5本目は「コンペティション」部門のチリ=アメリカ映画
「チリに君臨するピノチェト独裁政権の
信任を問う国民投票の実施が決まる。
強者の「YES」陣営に対し、
「NO」陣営は
広告界の若きエグゼクティブを採用して
果敢なキャンペーンを展開する。
88年当時の模様を斬新なスタイルで再現した、
勇気溢れる興奮の政治エンタテインメント。」
(第25回東京国際映画祭HPより抜粋)
映画祭から1ヵ月経って
まだ観た映画を書ききれていませんが、
この映画はガエル・ガルシア・ベルナルの
新作ということでそれだけで選んだ。
長く続くチリの独裁政権の終焉、
信任の国民投票を行う事までこぎつけた
民主化を望む陣営と
これまでの利権を守る政権陣営は
激しいキャンペーンを繰り広げていた。
現政権に「NO」をたたきつける陣営は
そのキャンペーンに売れっ子の広告クリエイターを指名
政治色の薄い出来上がった映像は賛否あったが
新しい風をチリに送るにはふさわしいと
大胆な映像キャンペーンを展開し始める、
焦る「YES」陣営は
様々な圧力をかけ、出来上がったテープを
紛失させるなど妨害を繰り返す。
かなりスリリングなシーンも多く
独裁政権を打倒する困難が伝わる
多くの国でかつて同様なことが行われていた
それを考えれば現在は少しは
国は、政治は成熟し始めているのか、
時々逆行するような事件もあり
人間の繰り返す愚かさを想った。
当時の実際のキャンペーンの映像が流れ
当時を知る人達にインタビューもしたというが
「YES」陣営は積極的に発言してくれたが
「NO」陣営の口は重かったという
まあ、そうだろうが
その時の人々の選択が今に繋がっていると思うと
選挙というものについても
もっと真摯に臨まないといけないんだろうな、
自分達の政治への関わり方も
本当はこんなじゃ、当時の彼らに叱られそうだ。
映像は画面が粗い印象で
一昔前のデジタルじゃない感じと思っていたが
後で資料を見たら撮影にはアナログの
日本製ビンテージカメラが用いられていたそうだ。
それが当時の雰囲気をより効果的にしている
クリエイターってこういうところにまで凝って
それを自分達は僅かな印象の違いで
「なるほど」と思うわけだけど
映画が総合芸術と言われる所以か。
ガエル・ガルシア・ベルナルは一人の個人としても
こういう映画作りに携わる意義を
感じているのかもしれないが
彼らしいところはあまりなく
そのあたりは物足りなかった。
国際映画祭という場にはふさわしい作品だった。
★100点満点で70点★
★この記事が参考になったらココもクリック!よろしく←
東京国際映画祭HP
パブロ・ラライン監督
1976年サンティアゴ生まれ。
2005年に初の長編映画“Fuga”を監督。
次の長編映画『トニー・マネロ』は
08年のカンヌ国際映画祭監督週間でプレミア上映され、
アルフレド・カストロとAntonia Zegers出演の
3作目“Post Mortem”は10年の
ヴェネチア国際映画祭コンペティション部門で上映された。
10年、チリで製作された初のHBOシリーズ「Profugos」を監督。
本作は4本目の長編映画である。
soramove
★この記事が参考になったらココもクリック!よろしく(1日1回有効)←ランキング上昇ボタン