当時、朝日新聞の社長だった広岡知男が、中国政府のいいなりになって、本多勝一に書かせたねつ造話なのです、と題して2017-11-05に発信した章である。
更に、以下の記事も掲載されている。http://blog.goo.ne.jp/nagatachoucafe7/e/54c2756a11c6ef1030acc1da4e9205f2
『朝日新聞・広岡知男社長の大罪。「南京大虐殺」を本多勝一に書かせた』と題した労作である。
朝日新聞記者の本多勝一が書いた「中国の旅」には、「南京大虐殺」のことが書いてあります。
この話は、当時、朝日新聞の社長だった広岡知男が、中国政府のいいなりになって、本多勝一に書かせたねつ造話なのです。
では、その経緯を詳しくご紹介しましょう。
「朝日新聞が避けて通れない、もう一つの戦後責任」
株主総会もすっぽかして訪中していた広岡社長
昭和39年、中国は日本のマスコミ各社と「日中記者交換協定」を結び、
「中国に不利な報道はしない」という条件の下で、各社は特派員を派遣していました。
しかし、文化大革命に関する報道などを巡って、日本の報道機関は軒並み国外退去となり、
昭和45年までに、中国に駐在しているマスコミは次々に中国から撤退していました。
そんな中、朝日新聞の広岡知男社長(当時)は、昭和45年3月から4月にかけて、
議長を務めるべき株主総会もすっぽかし、一か月間も中国に滞在。
他社の特派員が次々と国外追放される中で、広岡社長は当時の周恩来首相と会見するなど、異例の歓待を受けます。
その結果、朝日新聞のみが北京駐在を許されることになりました。
中国から帰国後、広岡社長は本多勝一記者に中国の取材を指示。
本多記者は翌46年6月から40日間かけて中国を取材し、
その結果生まれたのが「中国の旅」です。
本多記者の「中国の旅」は、昭和46年8月から朝日新聞に連載されました。
しかし、一連の取材は、あらかじめ中国共産党外交部新聞司が現地で「証言者」を準備し、本多記者は中国の用意した「語り部」の話を鵜呑みにして記事にしただけでした。
のちに、「中国の旅」を読んだ読者の抗議を受けた本多記者は、「私は、中国側の言うのをそのまま代弁しただけですから、抗議をするなら中国側に直接やっていただけませんか」と、ジャーナリストの発言とは思えぬ、驚くべき回答をしています。
証言者を探す必要もなく、手間いらずのこの取材を、本多記者は次のように証言しています。
「取材そのものは、ある意味では楽な取材だといえるでしょう。レールは敷かれているし、取材相手はこちらから探さなくてもむこうからそろえてくれる。だから、問題は、短時間に相手からいかに大量に聞き出すか、しかも正確に聞き出すか、そういう問題になる」
つまり、本多記者は加害者とされた日本側の「裏付け調査」をまったくせずに、中国側の証言をそのまま記事にしていたということになります。
「中国の旅」は日本人の残虐ぶりを世界に語り継ぐ証拠として、今なお読み継がれています。
また、「中国の旅」をはじめとして、朝日新聞が報道した一連の「南京大虐殺」報道を根拠の一つとして、
中国は「南京大虐殺」を国連のユネスコ記憶遺産に登録申請してます。
「従軍慰安婦」についての検証がはじまった今、朝日新聞が最後の清算として取り組まねばならないのが、この「南京大虐殺ねつ造事件」の徹底調査です。
*この記事は2015-01-23に人類史上最大の図書館であるインターネットに掲載されたものである。*
当時、朝日新聞の社長だった広岡知男が、中国政府のいいなりになって、本多勝一に書かせたねつ造話なのです、と題して2017-11-05に発信した章である。
更に、以下の記事も掲載されている。http://blog.goo.ne.jp/nagatachoucafe7/e/54c2756a11c6ef1030acc1da4e9205f2
『朝日新聞・広岡知男社長の大罪。「南京大虐殺」を本多勝一に書かせた』と題した労作である。
朝日新聞記者の本多勝一が書いた「中国の旅」には、「南京大虐殺」のことが書いてあります。
この話は、当時、朝日新聞の社長だった広岡知男が、中国政府のいいなりになって、本多勝一に書かせたねつ造話なのです。
では、その経緯を詳しくご紹介しましょう。
「朝日新聞が避けて通れない、もう一つの戦後責任」
株主総会もすっぽかして訪中していた広岡社長
昭和39年、中国は日本のマスコミ各社と「日中記者交換協定」を結び、
「中国に不利な報道はしない」という条件の下で、各社は特派員を派遣していました。
しかし、文化大革命に関する報道などを巡って、日本の報道機関は軒並み国外退去となり、
昭和45年までに、中国に駐在しているマスコミは次々に中国から撤退していました。
そんな中、朝日新聞の広岡知男社長(当時)は、昭和45年3月から4月にかけて、
議長を務めるべき株主総会もすっぽかし、一か月間も中国に滞在。
他社の特派員が次々と国外追放される中で、広岡社長は当時の周恩来首相と会見するなど、異例の歓待を受けます。
その結果、朝日新聞のみが北京駐在を許されることになりました。
中国から帰国後、広岡社長は本多勝一記者に中国の取材を指示。
本多記者は翌46年6月から40日間かけて中国を取材し、
その結果生まれたのが「中国の旅」です。
本多記者の「中国の旅」は、昭和46年8月から朝日新聞に連載されました。
しかし、一連の取材は、あらかじめ中国共産党外交部新聞司が現地で「証言者」を準備し、本多記者は中国の用意した「語り部」の話を鵜呑みにして記事にしただけでした。
のちに、「中国の旅」を読んだ読者の抗議を受けた本多記者は、「私は、中国側の言うのをそのまま代弁しただけですから、抗議をするなら中国側に直接やっていただけませんか」と、ジャーナリストの発言とは思えぬ、驚くべき回答をしています。
証言者を探す必要もなく、手間いらずのこの取材を、本多記者は次のように証言しています。
「取材そのものは、ある意味では楽な取材だといえるでしょう。レールは敷かれているし、取材相手はこちらから探さなくてもむこうからそろえてくれる。だから、問題は、短時間に相手からいかに大量に聞き出すか、しかも正確に聞き出すか、そういう問題になる」
つまり、本多記者は加害者とされた日本側の「裏付け調査」をまったくせずに、中国側の証言をそのまま記事にしていたということになります。
「中国の旅」は日本人の残虐ぶりを世界に語り継ぐ証拠として、今なお読み継がれています。
また、「中国の旅」をはじめとして、朝日新聞が報道した一連の「南京大虐殺」報道を根拠の一つとして、
中国は「南京大虐殺」を国連のユネスコ記憶遺産に登録申請してます。
「従軍慰安婦」についての検証がはじまった今、朝日新聞が最後の清算として取り組まねばならないのが、この「南京大虐殺ねつ造事件」の徹底調査です。
*この記事は2015-01-23に人類史上最大の図書館であるインターネットに掲載されたものである。*
当時、朝日新聞の社長だった広岡知男が、中国政府のいいなりになって、本多勝一に書かせたねつ造話なのです、と題して2017-11-05に発信した章である。
更に、以下の記事も掲載されている。http://blog.goo.ne.jp/nagatachoucafe7/e/54c2756a11c6ef1030acc1da4e9205f2
『朝日新聞・広岡知男社長の大罪。「南京大虐殺」を本多勝一に書かせた』と題した労作である。
朝日新聞記者の本多勝一が書いた「中国の旅」には、「南京大虐殺」のことが書いてあります。
この話は、当時、朝日新聞の社長だった広岡知男が、中国政府のいいなりになって、本多勝一に書かせたねつ造話なのです。
では、その経緯を詳しくご紹介しましょう。
「朝日新聞が避けて通れない、もう一つの戦後責任」
株主総会もすっぽかして訪中していた広岡社長
昭和39年、中国は日本のマスコミ各社と「日中記者交換協定」を結び、
「中国に不利な報道はしない」という条件の下で、各社は特派員を派遣していました。
しかし、文化大革命に関する報道などを巡って、日本の報道機関は軒並み国外退去となり、
昭和45年までに、中国に駐在しているマスコミは次々に中国から撤退していました。
そんな中、朝日新聞の広岡知男社長(当時)は、昭和45年3月から4月にかけて、
議長を務めるべき株主総会もすっぽかし、一か月間も中国に滞在。
他社の特派員が次々と国外追放される中で、広岡社長は当時の周恩来首相と会見するなど、異例の歓待を受けます。
その結果、朝日新聞のみが北京駐在を許されることになりました。
中国から帰国後、広岡社長は本多勝一記者に中国の取材を指示。
本多記者は翌46年6月から40日間かけて中国を取材し、
その結果生まれたのが「中国の旅」です。
本多記者の「中国の旅」は、昭和46年8月から朝日新聞に連載されました。
しかし、一連の取材は、あらかじめ中国共産党外交部新聞司が現地で「証言者」を準備し、本多記者は中国の用意した「語り部」の話を鵜呑みにして記事にしただけでした。
のちに、「中国の旅」を読んだ読者の抗議を受けた本多記者は、「私は、中国側の言うのをそのまま代弁しただけですから、抗議をするなら中国側に直接やっていただけませんか」と、ジャーナリストの発言とは思えぬ、驚くべき回答をしています。
証言者を探す必要もなく、手間いらずのこの取材を、本多記者は次のように証言しています。
「取材そのものは、ある意味では楽な取材だといえるでしょう。レールは敷かれているし、取材相手はこちらから探さなくてもむこうからそろえてくれる。だから、問題は、短時間に相手からいかに大量に聞き出すか、しかも正確に聞き出すか、そういう問題になる」
つまり、本多記者は加害者とされた日本側の「裏付け調査」をまったくせずに、中国側の証言をそのまま記事にしていたということになります。
「中国の旅」は日本人の残虐ぶりを世界に語り継ぐ証拠として、今なお読み継がれています。
また、「中国の旅」をはじめとして、朝日新聞が報道した一連の「南京大虐殺」報道を根拠の一つとして、
中国は「南京大虐殺」を国連のユネスコ記憶遺産に登録申請してます。
「従軍慰安婦」についての検証がはじまった今、朝日新聞が最後の清算として取り組まねばならないのが、この「南京大虐殺ねつ造事件」の徹底調査です。
*この記事は2015-01-23に人類史上最大の図書館であるインターネットに掲載されたものである。*
辻元清美の両親の国籍は韓国なんでしょうか? 国籍が韓国である噂は多かったので、 帰化の噂の真相を調べてみますと、
北方四島も同じだ。ロシアはあのとき日本の武装解除を待って攻め込んだ。何ともみっともない所行だが、そこまでするほど日露戦争に負けて領土利権を奪われた恨みは深い
独仏国境のアルザス・ローレーヌはその意味で格好の「戦争」見本だ。 独がまず普仏戦争でここを征服し、独語を教室で教えさせ、ローレーヌもロートリングンと独風の名にした
長い歴史がつながりをもって感じられ、公家や大名家が今にいたるまで存続してきたのも、勝者が徹底して復讐することがなかったからです。
慶長5年(1600年)関ヶ原の戦いでは、西軍として大坂城平野橋を警護したため、戦後所領を没収されるが、頼久とともに徳川氏に仕える。
かつて朝敵といわれた会津松平家の娘さんが皇族と結婚するなど(秩父宮雍仁親王妃)、融和を進めたわけです。
よほどの覚悟がいるということだ。それなのに「あーあ戦争と言っちゃった」と枝野や前科者の辻元がキャーキャー騒ぐ。お前らには外交は無理だ。
it is a popular page yesterday.
神護寺三像 伝平重盛像 日経新聞12月4日16面より…本日の全新聞中の白眉はこれだろう。
縄文時代が、その後の日本文化の基盤を作った。土器も世界に先駆けて作られていました。こういうことを日本人は知らないし、知らせようとしない新聞やメディアがある
以下は下記の日本国民全員が必読の書からである。
歴史の重みが民衆レベルでの一体感を生む
高山
1993年、私がロス特派員で米国にいた時、たまたまクリントン主催のAPECが開かれました。
日本からは細川護煕が来て、マハティールが日本とASEANで東アジア経済協議体(EAEC)という経済機構をつくろうと呼びかけていた時代だから、APECでそれを潰そうとしていた。
シアトルで各国の首脳が並ぶ中、クリントンが腰をかがめて、細川護煕を案内していた姿に驚きました。
まるで劇場の「お席はこちらです」の案内係(usher)のように、細川の前を、腰をかがめて行く。
彼はその後おかしくなったけれども、アーカンソーのドン百姓と400年間続いてきた大名家では、おのずと品格の違いが出ます。
日本のことなど何も知らないクリントンでさえ、やはり歴史を背景とする風格のようなものを彼に感じていた。
細川自身が気付いていないだけで。
渡部
そう、本人が気付いていない(笑)。おもしろいですね。
高山
彼も不思議に思わなかったのでしょうか。
どうしてクリントンが腰をかがめて俺を先導するんだろうって。
テレビを兒ながら、頭を下げたりなんかしないで、胸を張って案内させればいい、と思っていました。
日本にはその場面は放映されなかったかもしれません。
向こうの番組では延々と流していました。
渡部
なるほど。
長い歴史がつながりをもって感じられ、公家や大名家が今にいたるまで存続してきたのも、勝者が徹底して復讐することがなかったからです。
だから日本では、国体が何度か変化しても、天皇を戴くという根本は断絶しませんでした。
例えば明治維新があっても、徳川家が二代にわたって貴族院議長を務め、幕藩時代の大名が華族として待遇されたのは、いわゆる革命とはいいがたい。
かつて朝敵といわれた会津松平家の娘さんが皇族と結婚するなど(秩父宮雍仁親王妃)、融和を進めたわけです。
高山
遡ってみれば関ケ原の後始末も、西軍に参加した大名を外様として存続させ、日本全体で和をもって尊しとした。
これも欧米の歴史にはなかなかないことですね。
渡部
だからこそ日本人はどこかで、やはり日本人同士だという感覚を持てるわけです。
神話の時代から歴史が地続きであり、例えば『古事記』が成立した712年から続く歴史をもっている近代国家はありません。
神話上で国を造った女神・男神の直系の子孫の系図が残っており、それが皇室につながっている。
神話から今の世代にいたるまで系図がつながっている国なんて、ギリシヤ神話でもゲルマン神話でも、ありえないですよ。
そうすると、やはり一体感がほかの国とは違うのではないですか。
外国人に説明して驚くか信じるか分かりませんけれども、2014年、高円宮家のお嬢様である典子女王と出雲神社の権宮司(父の宮司に次ぐ地位)の千家国麿さんが結婚しましたね。
それはどこまで遡るかというと、皇孫である瑣瑣杵尊の子孫が高円宮家で、瑣瑣杵尊の弟が千家家の先祖になるわけです。つまり、神代からのつながりです。
そんないにしえの時代から、両家ともずっと系図がつながっていて、神社まで現存している。
神社も系図も、ともに実物が残っているわけです。
この話を外国にあてはめてみますと、トロイ戦争で攻めていったアカイアのアガメムノンの子孫が、まだ現存して神殿を守っていて、攻められたトロイの子孫もまだ残っており、そのお嬢さんとアガメムノンの子孫が、系図も残っている上で結婚するような、まあ考えられない話になるんで(笑)。 それが考えられるどころか、実現しているじゃないですか。
出雲大社は『古事記』のオオクニヌシの国譲り伝承に出てきますね。
国を譲る代わりに、壮大な出雲大社を建てるように要求した話です。
「底つ石根に宮柱太しり、高天原に千木高しりて治め賜はば、僕は百足らず八十隈手に隠りて侍ひなむ」(土の底の石根に届くまで宮柱を据え、高天原に届くほど高々と千木を立てた大社を建ててくれれば、私は国を譲り、鎮まって籠りましょう)と書いてあるその通りのものが、出雲大社に残っています。
神話の時代の建物の形が残されている。
もっと簡単な話で、東西南北といいますね。
このうち西・南・北の読み方は2つだけです。
西はセイとにし、南はナンとみなみ、北はホクときだ、音と訓です。
ところが東だけは3つあるんです。
トウとひがしとあずま。
これがなぜかといえば、日本武尊の東征神話です。
房総半島に向けて海を渡るために、后の弟橘比売が入水して荒波を鎮めた犠牲を「吾妻はや」と嘆いたのが、東国を「あずま」と呼ぶ起源になりました。
この神話によって、あずまという読みが現代まで続いているわけです。
独特な国であり、一種の奇跡といってもいいでしょう。
高山
その神話を頭から否定して、歴史のつながりを断ち切ろうとしたのもマッカーサーでした。
それでも、神話の時代から有史時代へ、歴史のつながりが感じられるのは、古いものが保存され、日本社会に生き続けているのを実感できるからです。
例えば最近、縄文時代の研究が進んで、日本は世界のはずれの辺境だとずっといわれていたのが、まったく違っていたことが分かってきました。
とても華やかな装飾品や交易品、平等で人間味のある社会を築いていた縄文時代が、その後の日本文化の基盤を作った。土器も世界に先駆けて作られていました。
こういうことを日本人は知らないし、知らせようとしない新聞やメディアがある。
日本人は、それこそ縄文の昔からずっと、クリやヒエを植えて、豊かな自然と調和しながら暮らし、世界に先んじて洗練された集団生活を営み、それが今日の社会や組織のあり方にまで連綿と受け継がれてきたのです。
そうでなければ、これだけ成熟した民主国家はできません。
渡部
そうですね。
高山
先日、壱岐に行きました。『日本書紀』に出てくる月讀神社(京都の月読神社の元宮)、天照大神の弟で素戔鵈尊の兄神である月読命の神社がちゃんと残っていました。
元寇で荒らされても何ら影響を受けず、神社が大切にされていて、おもしろいことに壱岐にはお寺がなくて神社ばかりなんです。
日本のあちこちを訪ねると、神話がそのまま神社として形を残していて、仏教伝来より前の歴史がしっかり保存されている。
古来からのものが受け継がれていることを実感します。
渡部
占領軍は「天皇が神ではない」ことを示すために神道指令(禁止令)を出して日本の宗教に干渉してきました。
例えば神宮皇學館という学校は一時廃止され、國學院大学でも「古事記」を教えることができなくなった。
しかし私のいた上智大学では、教養科目で古事記の講義があったのです。
私はこの講義に出席して古事記そのものを読み、神話が日本人の歴史観の根底をなしていることを知りました。
戦後70年経ってもなお、その事実は変わりませんし、むしろ多くの日本人がそれに気づくようになっています。大した変化です。
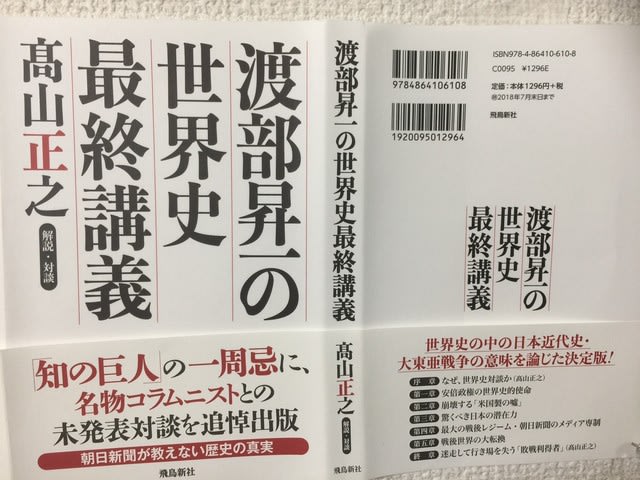
以下は下記の日本国民全員が必読の書からである。
歴史の重みが民衆レベルでの一体感を生む
高山
1993年、私がロス特派員で米国にいた時、たまたまクリントン主催のAPECが開かれました。
日本からは細川護煕が来て、マハティールが日本とASEANで東アジア経済協議体(EAEC)という経済機構をつくろうと呼びかけていた時代だから、APECでそれを潰そうとしていた。
シアトルで各国の首脳が並ぶ中、クリントンが腰をかがめて、細川護煕を案内していた姿に驚きました。
まるで劇場の「お席はこちらです」の案内係(usher)のように、細川の前を、腰をかがめて行く。
彼はその後おかしくなったけれども、アーカンソーのドン百姓と400年間続いてきた大名家では、おのずと品格の違いが出ます。
日本のことなど何も知らないクリントンでさえ、やはり歴史を背景とする風格のようなものを彼に感じていた。
細川自身が気付いていないだけで。
渡部
そう、本人が気付いていない(笑)。おもしろいですね。
高山
彼も不思議に思わなかったのでしょうか。
どうしてクリントンが腰をかがめて俺を先導するんだろうって。
テレビを兒ながら、頭を下げたりなんかしないで、胸を張って案内させればいい、と思っていました。
日本にはその場面は放映されなかったかもしれません。
向こうの番組では延々と流していました。
渡部
なるほど。
長い歴史がつながりをもって感じられ、公家や大名家が今にいたるまで存続してきたのも、勝者が徹底して復讐することがなかったからです。
だから日本では、国体が何度か変化しても、天皇を戴くという根本は断絶しませんでした。
例えば明治維新があっても、徳川家が二代にわたって貴族院議長を務め、幕藩時代の大名が華族として待遇されたのは、いわゆる革命とはいいがたい。
かつて朝敵といわれた会津松平家の娘さんが皇族と結婚するなど(秩父宮雍仁親王妃)、融和を進めたわけです。
高山
遡ってみれば関ケ原の後始末も、西軍に参加した大名を外様として存続させ、日本全体で和をもって尊しとした。
これも欧米の歴史にはなかなかないことですね。
渡部
だからこそ日本人はどこかで、やはり日本人同士だという感覚を持てるわけです。
神話の時代から歴史が地続きであり、例えば『古事記』が成立した712年から続く歴史をもっている近代国家はありません。
神話上で国を造った女神・男神の直系の子孫の系図が残っており、それが皇室につながっている。
神話から今の世代にいたるまで系図がつながっている国なんて、ギリシヤ神話でもゲルマン神話でも、ありえないですよ。
そうすると、やはり一体感がほかの国とは違うのではないですか。
外国人に説明して驚くか信じるか分かりませんけれども、2014年、高円宮家のお嬢様である典子女王と出雲神社の権宮司(父の宮司に次ぐ地位)の千家国麿さんが結婚しましたね。
それはどこまで遡るかというと、皇孫である瑣瑣杵尊の子孫が高円宮家で、瑣瑣杵尊の弟が千家家の先祖になるわけです。つまり、神代からのつながりです。
そんないにしえの時代から、両家ともずっと系図がつながっていて、神社まで現存している。
神社も系図も、ともに実物が残っているわけです。
この話を外国にあてはめてみますと、トロイ戦争で攻めていったアカイアのアガメムノンの子孫が、まだ現存して神殿を守っていて、攻められたトロイの子孫もまだ残っており、そのお嬢さんとアガメムノンの子孫が、系図も残っている上で結婚するような、まあ考えられない話になるんで(笑)。 それが考えられるどころか、実現しているじゃないですか。
出雲大社は『古事記』のオオクニヌシの国譲り伝承に出てきますね。
国を譲る代わりに、壮大な出雲大社を建てるように要求した話です。
「底つ石根に宮柱太しり、高天原に千木高しりて治め賜はば、僕は百足らず八十隈手に隠りて侍ひなむ」(土の底の石根に届くまで宮柱を据え、高天原に届くほど高々と千木を立てた大社を建ててくれれば、私は国を譲り、鎮まって籠りましょう)と書いてあるその通りのものが、出雲大社に残っています。
神話の時代の建物の形が残されている。
もっと簡単な話で、東西南北といいますね。
このうち西・南・北の読み方は2つだけです。
西はセイとにし、南はナンとみなみ、北はホクときだ、音と訓です。
ところが東だけは3つあるんです。
トウとひがしとあずま。
これがなぜかといえば、日本武尊の東征神話です。
房総半島に向けて海を渡るために、后の弟橘比売が入水して荒波を鎮めた犠牲を「吾妻はや」と嘆いたのが、東国を「あずま」と呼ぶ起源になりました。
この神話によって、あずまという読みが現代まで続いているわけです。
独特な国であり、一種の奇跡といってもいいでしょう。
高山
その神話を頭から否定して、歴史のつながりを断ち切ろうとしたのもマッカーサーでした。
それでも、神話の時代から有史時代へ、歴史のつながりが感じられるのは、古いものが保存され、日本社会に生き続けているのを実感できるからです。
例えば最近、縄文時代の研究が進んで、日本は世界のはずれの辺境だとずっといわれていたのが、まったく違っていたことが分かってきました。
とても華やかな装飾品や交易品、平等で人間味のある社会を築いていた縄文時代が、その後の日本文化の基盤を作った。土器も世界に先駆けて作られていました。
こういうことを日本人は知らないし、知らせようとしない新聞やメディアがある。
日本人は、それこそ縄文の昔からずっと、クリやヒエを植えて、豊かな自然と調和しながら暮らし、世界に先んじて洗練された集団生活を営み、それが今日の社会や組織のあり方にまで連綿と受け継がれてきたのです。
そうでなければ、これだけ成熟した民主国家はできません。
渡部
そうですね。
高山
先日、壱岐に行きました。『日本書紀』に出てくる月讀神社(京都の月読神社の元宮)、天照大神の弟で素戔鵈尊の兄神である月読命の神社がちゃんと残っていました。
元寇で荒らされても何ら影響を受けず、神社が大切にされていて、おもしろいことに壱岐にはお寺がなくて神社ばかりなんです。
日本のあちこちを訪ねると、神話がそのまま神社として形を残していて、仏教伝来より前の歴史がしっかり保存されている。
古来からのものが受け継がれていることを実感します。
渡部
占領軍は「天皇が神ではない」ことを示すために神道指令(禁止令)を出して日本の宗教に干渉してきました。
例えば神宮皇學館という学校は一時廃止され、國學院大学でも「古事記」を教えることができなくなった。
しかし私のいた上智大学では、教養科目で古事記の講義があったのです。
私はこの講義に出席して古事記そのものを読み、神話が日本人の歴史観の根底をなしていることを知りました。
戦後70年経ってもなお、その事実は変わりませんし、むしろ多くの日本人がそれに気づくようになっています。大した変化です。
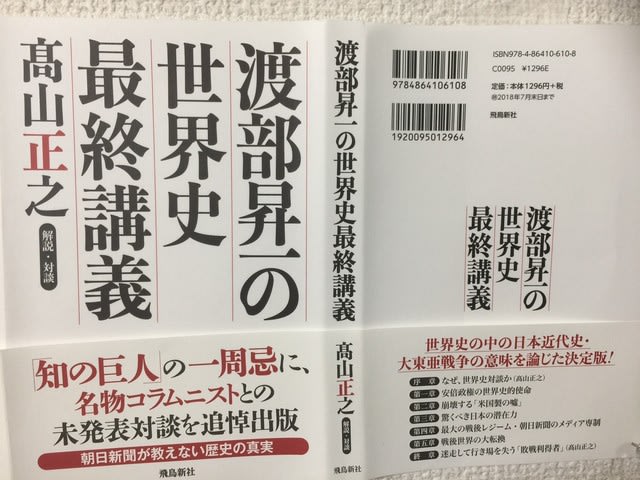
以下は下記の日本国民全員が必読の書からである。
歴史の重みが民衆レベルでの一体感を生む
高山
1993年、私がロス特派員で米国にいた時、たまたまクリントン主催のAPECが開かれました。
日本からは細川護煕が来て、マハティールが日本とASEANで東アジア経済協議体(EAEC)という経済機構をつくろうと呼びかけていた時代だから、APECでそれを潰そうとしていた。
シアトルで各国の首脳が並ぶ中、クリントンが腰をかがめて、細川護煕を案内していた姿に驚きました。
まるで劇場の「お席はこちらです」の案内係(usher)のように、細川の前を、腰をかがめて行く。
彼はその後おかしくなったけれども、アーカンソーのドン百姓と400年間続いてきた大名家では、おのずと品格の違いが出ます。
日本のことなど何も知らないクリントンでさえ、やはり歴史を背景とする風格のようなものを彼に感じていた。
細川自身が気付いていないだけで。
渡部
そう、本人が気付いていない(笑)。おもしろいですね。
高山
彼も不思議に思わなかったのでしょうか。
どうしてクリントンが腰をかがめて俺を先導するんだろうって。
テレビを兒ながら、頭を下げたりなんかしないで、胸を張って案内させればいい、と思っていました。
日本にはその場面は放映されなかったかもしれません。
向こうの番組では延々と流していました。
渡部
なるほど。
長い歴史がつながりをもって感じられ、公家や大名家が今にいたるまで存続してきたのも、勝者が徹底して復讐することがなかったからです。
だから日本では、国体が何度か変化しても、天皇を戴くという根本は断絶しませんでした。
例えば明治維新があっても、徳川家が二代にわたって貴族院議長を務め、幕藩時代の大名が華族として待遇されたのは、いわゆる革命とはいいがたい。
かつて朝敵といわれた会津松平家の娘さんが皇族と結婚するなど(秩父宮雍仁親王妃)、融和を進めたわけです。
高山
遡ってみれば関ケ原の後始末も、西軍に参加した大名を外様として存続させ、日本全体で和をもって尊しとした。
これも欧米の歴史にはなかなかないことですね。
渡部
だからこそ日本人はどこかで、やはり日本人同士だという感覚を持てるわけです。
神話の時代から歴史が地続きであり、例えば『古事記』が成立した712年から続く歴史をもっている近代国家はありません。
神話上で国を造った女神・男神の直系の子孫の系図が残っており、それが皇室につながっている。
神話から今の世代にいたるまで系図がつながっている国なんて、ギリシヤ神話でもゲルマン神話でも、ありえないですよ。
そうすると、やはり一体感がほかの国とは違うのではないですか。
外国人に説明して驚くか信じるか分かりませんけれども、2014年、高円宮家のお嬢様である典子女王と出雲神社の権宮司(父の宮司に次ぐ地位)の千家国麿さんが結婚しましたね。
それはどこまで遡るかというと、皇孫である瑣瑣杵尊の子孫が高円宮家で、瑣瑣杵尊の弟が千家家の先祖になるわけです。つまり、神代からのつながりです。
そんないにしえの時代から、両家ともずっと系図がつながっていて、神社まで現存している。
神社も系図も、ともに実物が残っているわけです。
この話を外国にあてはめてみますと、トロイ戦争で攻めていったアカイアのアガメムノンの子孫が、まだ現存して神殿を守っていて、攻められたトロイの子孫もまだ残っており、そのお嬢さんとアガメムノンの子孫が、系図も残っている上で結婚するような、まあ考えられない話になるんで(笑)。 それが考えられるどころか、実現しているじゃないですか。
出雲大社は『古事記』のオオクニヌシの国譲り伝承に出てきますね。
国を譲る代わりに、壮大な出雲大社を建てるように要求した話です。
「底つ石根に宮柱太しり、高天原に千木高しりて治め賜はば、僕は百足らず八十隈手に隠りて侍ひなむ」(土の底の石根に届くまで宮柱を据え、高天原に届くほど高々と千木を立てた大社を建ててくれれば、私は国を譲り、鎮まって籠りましょう)と書いてあるその通りのものが、出雲大社に残っています。
神話の時代の建物の形が残されている。
もっと簡単な話で、東西南北といいますね。
このうち西・南・北の読み方は2つだけです。
西はセイとにし、南はナンとみなみ、北はホクときだ、音と訓です。
ところが東だけは3つあるんです。
トウとひがしとあずま。
これがなぜかといえば、日本武尊の東征神話です。
房総半島に向けて海を渡るために、后の弟橘比売が入水して荒波を鎮めた犠牲を「吾妻はや」と嘆いたのが、東国を「あずま」と呼ぶ起源になりました。
この神話によって、あずまという読みが現代まで続いているわけです。
独特な国であり、一種の奇跡といってもいいでしょう。
高山
その神話を頭から否定して、歴史のつながりを断ち切ろうとしたのもマッカーサーでした。
それでも、神話の時代から有史時代へ、歴史のつながりが感じられるのは、古いものが保存され、日本社会に生き続けているのを実感できるからです。
例えば最近、縄文時代の研究が進んで、日本は世界のはずれの辺境だとずっといわれていたのが、まったく違っていたことが分かってきました。
とても華やかな装飾品や交易品、平等で人間味のある社会を築いていた縄文時代が、その後の日本文化の基盤を作った。土器も世界に先駆けて作られていました。
こういうことを日本人は知らないし、知らせようとしない新聞やメディアがある。
日本人は、それこそ縄文の昔からずっと、クリやヒエを植えて、豊かな自然と調和しながら暮らし、世界に先んじて洗練された集団生活を営み、それが今日の社会や組織のあり方にまで連綿と受け継がれてきたのです。
そうでなければ、これだけ成熟した民主国家はできません。
渡部
そうですね。
高山
先日、壱岐に行きました。『日本書紀』に出てくる月讀神社(京都の月読神社の元宮)、天照大神の弟で素戔鵈尊の兄神である月読命の神社がちゃんと残っていました。
元寇で荒らされても何ら影響を受けず、神社が大切にされていて、おもしろいことに壱岐にはお寺がなくて神社ばかりなんです。
日本のあちこちを訪ねると、神話がそのまま神社として形を残していて、仏教伝来より前の歴史がしっかり保存されている。
古来からのものが受け継がれていることを実感します。
渡部
占領軍は「天皇が神ではない」ことを示すために神道指令(禁止令)を出して日本の宗教に干渉してきました。
例えば神宮皇學館という学校は一時廃止され、國學院大学でも「古事記」を教えることができなくなった。
しかし私のいた上智大学では、教養科目で古事記の講義があったのです。
私はこの講義に出席して古事記そのものを読み、神話が日本人の歴史観の根底をなしていることを知りました。
戦後70年経ってもなお、その事実は変わりませんし、むしろ多くの日本人がそれに気づくようになっています。大した変化です。
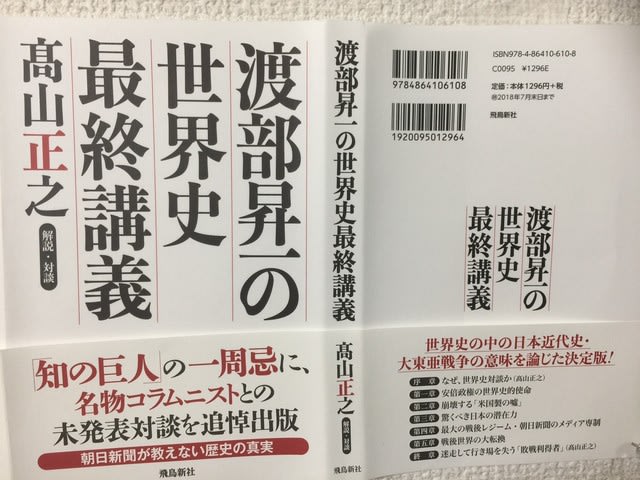
以下は下記の日本国民全員が必読の書からである。
歴史の重みが民衆レベルでの一体感を生む
高山
1993年、私がロス特派員で米国にいた時、たまたまクリントン主催のAPECが開かれました。
日本からは細川護煕が来て、マハティールが日本とASEANで東アジア経済協議体(EAEC)という経済機構をつくろうと呼びかけていた時代だから、APECでそれを潰そうとしていた。
シアトルで各国の首脳が並ぶ中、クリントンが腰をかがめて、細川護煕を案内していた姿に驚きました。
まるで劇場の「お席はこちらです」の案内係(usher)のように、細川の前を、腰をかがめて行く。
彼はその後おかしくなったけれども、アーカンソーのドン百姓と400年間続いてきた大名家では、おのずと品格の違いが出ます。
日本のことなど何も知らないクリントンでさえ、やはり歴史を背景とする風格のようなものを彼に感じていた。
細川自身が気付いていないだけで。
渡部
そう、本人が気付いていない(笑)。おもしろいですね。
高山
彼も不思議に思わなかったのでしょうか。
どうしてクリントンが腰をかがめて俺を先導するんだろうって。
テレビを兒ながら、頭を下げたりなんかしないで、胸を張って案内させればいい、と思っていました。
日本にはその場面は放映されなかったかもしれません。
向こうの番組では延々と流していました。
渡部
なるほど。
長い歴史がつながりをもって感じられ、公家や大名家が今にいたるまで存続してきたのも、勝者が徹底して復讐することがなかったからです。
だから日本では、国体が何度か変化しても、天皇を戴くという根本は断絶しませんでした。
例えば明治維新があっても、徳川家が二代にわたって貴族院議長を務め、幕藩時代の大名が華族として待遇されたのは、いわゆる革命とはいいがたい。
かつて朝敵といわれた会津松平家の娘さんが皇族と結婚するなど(秩父宮雍仁親王妃)、融和を進めたわけです。
高山
遡ってみれば関ケ原の後始末も、西軍に参加した大名を外様として存続させ、日本全体で和をもって尊しとした。
これも欧米の歴史にはなかなかないことですね。
渡部
だからこそ日本人はどこかで、やはり日本人同士だという感覚を持てるわけです。
神話の時代から歴史が地続きであり、例えば『古事記』が成立した712年から続く歴史をもっている近代国家はありません。
神話上で国を造った女神・男神の直系の子孫の系図が残っており、それが皇室につながっている。
神話から今の世代にいたるまで系図がつながっている国なんて、ギリシヤ神話でもゲルマン神話でも、ありえないですよ。
そうすると、やはり一体感がほかの国とは違うのではないですか。
外国人に説明して驚くか信じるか分かりませんけれども、2014年、高円宮家のお嬢様である典子女王と出雲神社の権宮司(父の宮司に次ぐ地位)の千家国麿さんが結婚しましたね。
それはどこまで遡るかというと、皇孫である瑣瑣杵尊の子孫が高円宮家で、瑣瑣杵尊の弟が千家家の先祖になるわけです。つまり、神代からのつながりです。
そんないにしえの時代から、両家ともずっと系図がつながっていて、神社まで現存している。
神社も系図も、ともに実物が残っているわけです。
この話を外国にあてはめてみますと、トロイ戦争で攻めていったアカイアのアガメムノンの子孫が、まだ現存して神殿を守っていて、攻められたトロイの子孫もまだ残っており、そのお嬢さんとアガメムノンの子孫が、系図も残っている上で結婚するような、まあ考えられない話になるんで(笑)。 それが考えられるどころか、実現しているじゃないですか。
出雲大社は『古事記』のオオクニヌシの国譲り伝承に出てきますね。
国を譲る代わりに、壮大な出雲大社を建てるように要求した話です。
「底つ石根に宮柱太しり、高天原に千木高しりて治め賜はば、僕は百足らず八十隈手に隠りて侍ひなむ」(土の底の石根に届くまで宮柱を据え、高天原に届くほど高々と千木を立てた大社を建ててくれれば、私は国を譲り、鎮まって籠りましょう)と書いてあるその通りのものが、出雲大社に残っています。
神話の時代の建物の形が残されている。
もっと簡単な話で、東西南北といいますね。
このうち西・南・北の読み方は2つだけです。
西はセイとにし、南はナンとみなみ、北はホクときだ、音と訓です。
ところが東だけは3つあるんです。
トウとひがしとあずま。
これがなぜかといえば、日本武尊の東征神話です。
房総半島に向けて海を渡るために、后の弟橘比売が入水して荒波を鎮めた犠牲を「吾妻はや」と嘆いたのが、東国を「あずま」と呼ぶ起源になりました。
この神話によって、あずまという読みが現代まで続いているわけです。
独特な国であり、一種の奇跡といってもいいでしょう。
高山
その神話を頭から否定して、歴史のつながりを断ち切ろうとしたのもマッカーサーでした。
それでも、神話の時代から有史時代へ、歴史のつながりが感じられるのは、古いものが保存され、日本社会に生き続けているのを実感できるからです。
例えば最近、縄文時代の研究が進んで、日本は世界のはずれの辺境だとずっといわれていたのが、まったく違っていたことが分かってきました。
とても華やかな装飾品や交易品、平等で人間味のある社会を築いていた縄文時代が、その後の日本文化の基盤を作った。土器も世界に先駆けて作られていました。
こういうことを日本人は知らないし、知らせようとしない新聞やメディアがある。
日本人は、それこそ縄文の昔からずっと、クリやヒエを植えて、豊かな自然と調和しながら暮らし、世界に先んじて洗練された集団生活を営み、それが今日の社会や組織のあり方にまで連綿と受け継がれてきたのです。
そうでなければ、これだけ成熟した民主国家はできません。
渡部
そうですね。
高山
先日、壱岐に行きました。『日本書紀』に出てくる月讀神社(京都の月読神社の元宮)、天照大神の弟で素戔鵈尊の兄神である月読命の神社がちゃんと残っていました。
元寇で荒らされても何ら影響を受けず、神社が大切にされていて、おもしろいことに壱岐にはお寺がなくて神社ばかりなんです。
日本のあちこちを訪ねると、神話がそのまま神社として形を残していて、仏教伝来より前の歴史がしっかり保存されている。
古来からのものが受け継がれていることを実感します。
渡部
占領軍は「天皇が神ではない」ことを示すために神道指令(禁止令)を出して日本の宗教に干渉してきました。
例えば神宮皇學館という学校は一時廃止され、國學院大学でも「古事記」を教えることができなくなった。
しかし私のいた上智大学では、教養科目で古事記の講義があったのです。
私はこの講義に出席して古事記そのものを読み、神話が日本人の歴史観の根底をなしていることを知りました。
戦後70年経ってもなお、その事実は変わりませんし、むしろ多くの日本人がそれに気づくようになっています。大した変化です。
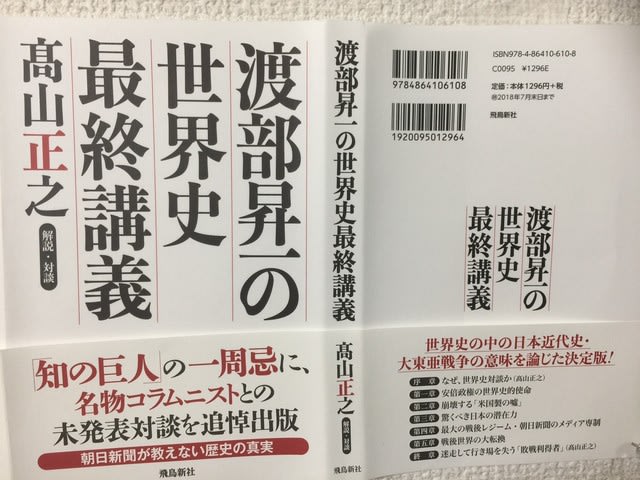
以下は下記の日本国民全員が必読の書からである。
歴史の重みが民衆レベルでの一体感を生む
高山
1993年、私がロス特派員で米国にいた時、たまたまクリントン主催のAPECが開かれました。
日本からは細川護煕が来て、マハティールが日本とASEANで東アジア経済協議体(EAEC)という経済機構をつくろうと呼びかけていた時代だから、APECでそれを潰そうとしていた。
シアトルで各国の首脳が並ぶ中、クリントンが腰をかがめて、細川護煕を案内していた姿に驚きました。
まるで劇場の「お席はこちらです」の案内係(usher)のように、細川の前を、腰をかがめて行く。
彼はその後おかしくなったけれども、アーカンソーのドン百姓と400年間続いてきた大名家では、おのずと品格の違いが出ます。
日本のことなど何も知らないクリントンでさえ、やはり歴史を背景とする風格のようなものを彼に感じていた。
細川自身が気付いていないだけで。
渡部
そう、本人が気付いていない(笑)。おもしろいですね。
高山
彼も不思議に思わなかったのでしょうか。
どうしてクリントンが腰をかがめて俺を先導するんだろうって。
テレビを兒ながら、頭を下げたりなんかしないで、胸を張って案内させればいい、と思っていました。
日本にはその場面は放映されなかったかもしれません。
向こうの番組では延々と流していました。
渡部
なるほど。
長い歴史がつながりをもって感じられ、公家や大名家が今にいたるまで存続してきたのも、勝者が徹底して復讐することがなかったからです。
だから日本では、国体が何度か変化しても、天皇を戴くという根本は断絶しませんでした。
例えば明治維新があっても、徳川家が二代にわたって貴族院議長を務め、幕藩時代の大名が華族として待遇されたのは、いわゆる革命とはいいがたい。
かつて朝敵といわれた会津松平家の娘さんが皇族と結婚するなど(秩父宮雍仁親王妃)、融和を進めたわけです。
高山
遡ってみれば関ケ原の後始末も、西軍に参加した大名を外様として存続させ、日本全体で和をもって尊しとした。
これも欧米の歴史にはなかなかないことですね。
渡部
だからこそ日本人はどこかで、やはり日本人同士だという感覚を持てるわけです。
神話の時代から歴史が地続きであり、例えば『古事記』が成立した712年から続く歴史をもっている近代国家はありません。
神話上で国を造った女神・男神の直系の子孫の系図が残っており、それが皇室につながっている。
神話から今の世代にいたるまで系図がつながっている国なんて、ギリシヤ神話でもゲルマン神話でも、ありえないですよ。
そうすると、やはり一体感がほかの国とは違うのではないですか。
外国人に説明して驚くか信じるか分かりませんけれども、2014年、高円宮家のお嬢様である典子女王と出雲神社の権宮司(父の宮司に次ぐ地位)の千家国麿さんが結婚しましたね。
それはどこまで遡るかというと、皇孫である瑣瑣杵尊の子孫が高円宮家で、瑣瑣杵尊の弟が千家家の先祖になるわけです。つまり、神代からのつながりです。
そんないにしえの時代から、両家ともずっと系図がつながっていて、神社まで現存している。
神社も系図も、ともに実物が残っているわけです。
この話を外国にあてはめてみますと、トロイ戦争で攻めていったアカイアのアガメムノンの子孫が、まだ現存して神殿を守っていて、攻められたトロイの子孫もまだ残っており、そのお嬢さんとアガメムノンの子孫が、系図も残っている上で結婚するような、まあ考えられない話になるんで(笑)。 それが考えられるどころか、実現しているじゃないですか。
出雲大社は『古事記』のオオクニヌシの国譲り伝承に出てきますね。
国を譲る代わりに、壮大な出雲大社を建てるように要求した話です。
「底つ石根に宮柱太しり、高天原に千木高しりて治め賜はば、僕は百足らず八十隈手に隠りて侍ひなむ」(土の底の石根に届くまで宮柱を据え、高天原に届くほど高々と千木を立てた大社を建ててくれれば、私は国を譲り、鎮まって籠りましょう)と書いてあるその通りのものが、出雲大社に残っています。
神話の時代の建物の形が残されている。
もっと簡単な話で、東西南北といいますね。
このうち西・南・北の読み方は2つだけです。
西はセイとにし、南はナンとみなみ、北はホクときだ、音と訓です。
ところが東だけは3つあるんです。
トウとひがしとあずま。
これがなぜかといえば、日本武尊の東征神話です。
房総半島に向けて海を渡るために、后の弟橘比売が入水して荒波を鎮めた犠牲を「吾妻はや」と嘆いたのが、東国を「あずま」と呼ぶ起源になりました。
この神話によって、あずまという読みが現代まで続いているわけです。
独特な国であり、一種の奇跡といってもいいでしょう。
高山
その神話を頭から否定して、歴史のつながりを断ち切ろうとしたのもマッカーサーでした。
それでも、神話の時代から有史時代へ、歴史のつながりが感じられるのは、古いものが保存され、日本社会に生き続けているのを実感できるからです。
例えば最近、縄文時代の研究が進んで、日本は世界のはずれの辺境だとずっといわれていたのが、まったく違っていたことが分かってきました。
とても華やかな装飾品や交易品、平等で人間味のある社会を築いていた縄文時代が、その後の日本文化の基盤を作った。土器も世界に先駆けて作られていました。
こういうことを日本人は知らないし、知らせようとしない新聞やメディアがある。
日本人は、それこそ縄文の昔からずっと、クリやヒエを植えて、豊かな自然と調和しながら暮らし、世界に先んじて洗練された集団生活を営み、それが今日の社会や組織のあり方にまで連綿と受け継がれてきたのです。
そうでなければ、これだけ成熟した民主国家はできません。
渡部
そうですね。
高山
先日、壱岐に行きました。『日本書紀』に出てくる月讀神社(京都の月読神社の元宮)、天照大神の弟で素戔鵈尊の兄神である月読命の神社がちゃんと残っていました。
元寇で荒らされても何ら影響を受けず、神社が大切にされていて、おもしろいことに壱岐にはお寺がなくて神社ばかりなんです。
日本のあちこちを訪ねると、神話がそのまま神社として形を残していて、仏教伝来より前の歴史がしっかり保存されている。
古来からのものが受け継がれていることを実感します。
渡部
占領軍は「天皇が神ではない」ことを示すために神道指令(禁止令)を出して日本の宗教に干渉してきました。
例えば神宮皇學館という学校は一時廃止され、國學院大学でも「古事記」を教えることができなくなった。
しかし私のいた上智大学では、教養科目で古事記の講義があったのです。
私はこの講義に出席して古事記そのものを読み、神話が日本人の歴史観の根底をなしていることを知りました。
戦後70年経ってもなお、その事実は変わりませんし、むしろ多くの日本人がそれに気づくようになっています。大した変化です。
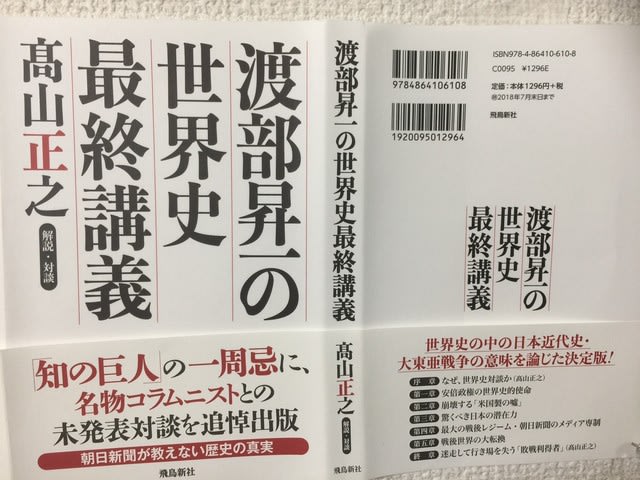
以下は下記の日本国民全員が必読の書からである。
歴史の重みが民衆レベルでの一体感を生む
高山
1993年、私がロス特派員で米国にいた時、たまたまクリントン主催のAPECが開かれました。
日本からは細川護煕が来て、マハティールが日本とASEANで東アジア経済協議体(EAEC)という経済機構をつくろうと呼びかけていた時代だから、APECでそれを潰そうとしていた。
シアトルで各国の首脳が並ぶ中、クリントンが腰をかがめて、細川護煕を案内していた姿に驚きました。
まるで劇場の「お席はこちらです」の案内係(usher)のように、細川の前を、腰をかがめて行く。
彼はその後おかしくなったけれども、アーカンソーのドン百姓と400年間続いてきた大名家では、おのずと品格の違いが出ます。
日本のことなど何も知らないクリントンでさえ、やはり歴史を背景とする風格のようなものを彼に感じていた。
細川自身が気付いていないだけで。
渡部
そう、本人が気付いていない(笑)。おもしろいですね。
高山
彼も不思議に思わなかったのでしょうか。
どうしてクリントンが腰をかがめて俺を先導するんだろうって。
テレビを兒ながら、頭を下げたりなんかしないで、胸を張って案内させればいい、と思っていました。
日本にはその場面は放映されなかったかもしれません。
向こうの番組では延々と流していました。
渡部
なるほど。
長い歴史がつながりをもって感じられ、公家や大名家が今にいたるまで存続してきたのも、勝者が徹底して復讐することがなかったからです。
だから日本では、国体が何度か変化しても、天皇を戴くという根本は断絶しませんでした。
例えば明治維新があっても、徳川家が二代にわたって貴族院議長を務め、幕藩時代の大名が華族として待遇されたのは、いわゆる革命とはいいがたい。
かつて朝敵といわれた会津松平家の娘さんが皇族と結婚するなど(秩父宮雍仁親王妃)、融和を進めたわけです。
高山
遡ってみれば関ケ原の後始末も、西軍に参加した大名を外様として存続させ、日本全体で和をもって尊しとした。
これも欧米の歴史にはなかなかないことですね。
渡部
だからこそ日本人はどこかで、やはり日本人同士だという感覚を持てるわけです。
神話の時代から歴史が地続きであり、例えば『古事記』が成立した712年から続く歴史をもっている近代国家はありません。
神話上で国を造った女神・男神の直系の子孫の系図が残っており、それが皇室につながっている。
神話から今の世代にいたるまで系図がつながっている国なんて、ギリシヤ神話でもゲルマン神話でも、ありえないですよ。
そうすると、やはり一体感がほかの国とは違うのではないですか。
外国人に説明して驚くか信じるか分かりませんけれども、2014年、高円宮家のお嬢様である典子女王と出雲神社の権宮司(父の宮司に次ぐ地位)の千家国麿さんが結婚しましたね。
それはどこまで遡るかというと、皇孫である瑣瑣杵尊の子孫が高円宮家で、瑣瑣杵尊の弟が千家家の先祖になるわけです。つまり、神代からのつながりです。
そんないにしえの時代から、両家ともずっと系図がつながっていて、神社まで現存している。
神社も系図も、ともに実物が残っているわけです。
この話を外国にあてはめてみますと、トロイ戦争で攻めていったアカイアのアガメムノンの子孫が、まだ現存して神殿を守っていて、攻められたトロイの子孫もまだ残っており、そのお嬢さんとアガメムノンの子孫が、系図も残っている上で結婚するような、まあ考えられない話になるんで(笑)。 それが考えられるどころか、実現しているじゃないですか。
出雲大社は『古事記』のオオクニヌシの国譲り伝承に出てきますね。
国を譲る代わりに、壮大な出雲大社を建てるように要求した話です。
「底つ石根に宮柱太しり、高天原に千木高しりて治め賜はば、僕は百足らず八十隈手に隠りて侍ひなむ」(土の底の石根に届くまで宮柱を据え、高天原に届くほど高々と千木を立てた大社を建ててくれれば、私は国を譲り、鎮まって籠りましょう)と書いてあるその通りのものが、出雲大社に残っています。
神話の時代の建物の形が残されている。
もっと簡単な話で、東西南北といいますね。
このうち西・南・北の読み方は2つだけです。
西はセイとにし、南はナンとみなみ、北はホクときだ、音と訓です。
ところが東だけは3つあるんです。
トウとひがしとあずま。
これがなぜかといえば、日本武尊の東征神話です。
房総半島に向けて海を渡るために、后の弟橘比売が入水して荒波を鎮めた犠牲を「吾妻はや」と嘆いたのが、東国を「あずま」と呼ぶ起源になりました。
この神話によって、あずまという読みが現代まで続いているわけです。
独特な国であり、一種の奇跡といってもいいでしょう。
高山
その神話を頭から否定して、歴史のつながりを断ち切ろうとしたのもマッカーサーでした。
それでも、神話の時代から有史時代へ、歴史のつながりが感じられるのは、古いものが保存され、日本社会に生き続けているのを実感できるからです。
例えば最近、縄文時代の研究が進んで、日本は世界のはずれの辺境だとずっといわれていたのが、まったく違っていたことが分かってきました。
とても華やかな装飾品や交易品、平等で人間味のある社会を築いていた縄文時代が、その後の日本文化の基盤を作った。土器も世界に先駆けて作られていました。
こういうことを日本人は知らないし、知らせようとしない新聞やメディアがある。
日本人は、それこそ縄文の昔からずっと、クリやヒエを植えて、豊かな自然と調和しながら暮らし、世界に先んじて洗練された集団生活を営み、それが今日の社会や組織のあり方にまで連綿と受け継がれてきたのです。
そうでなければ、これだけ成熟した民主国家はできません。
渡部
そうですね。
高山
先日、壱岐に行きました。『日本書紀』に出てくる月讀神社(京都の月読神社の元宮)、天照大神の弟で素戔鵈尊の兄神である月読命の神社がちゃんと残っていました。
元寇で荒らされても何ら影響を受けず、神社が大切にされていて、おもしろいことに壱岐にはお寺がなくて神社ばかりなんです。
日本のあちこちを訪ねると、神話がそのまま神社として形を残していて、仏教伝来より前の歴史がしっかり保存されている。
古来からのものが受け継がれていることを実感します。
渡部
占領軍は「天皇が神ではない」ことを示すために神道指令(禁止令)を出して日本の宗教に干渉してきました。
例えば神宮皇學館という学校は一時廃止され、國學院大学でも「古事記」を教えることができなくなった。
しかし私のいた上智大学では、教養科目で古事記の講義があったのです。
私はこの講義に出席して古事記そのものを読み、神話が日本人の歴史観の根底をなしていることを知りました。
戦後70年経ってもなお、その事実は変わりませんし、むしろ多くの日本人がそれに気づくようになっています。大した変化です。
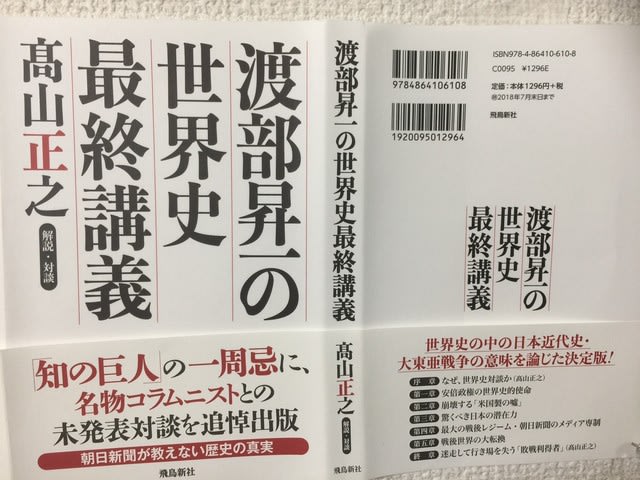
慈照寺(銀閣寺)再建の奉行や京都知恩院の普請奉行を務めた宮城 豊盛。と題して2013-05-18に発信した章である。
"Today last year"
"Timetable of Galaxy train" 2012/5/18
宮城 豊盛(みやぎ とよもり、天文23年(1554年) - 元和6年(1620年))は、戦国時代から江戸時代初期にかけての武将。本姓は大江氏。宮木とも書く。通称、長次郎または長次。宮城堅甫の娘婿で、豊臣氏に仕える。山崎片家の子の頼久を養子とした。妹に鯰江貞勝室。官位は従五位下丹波守。法名は宗広。使用家紋は蝶紋の「揚羽蝶」が「寛政重修諸家譜」に載る。
豊臣秀吉に従い三木合戦で功を挙げ、小田原征伐や文禄・慶長の役に参陣する。京の金戒光明寺再建の奉行を務める。文禄元年(1592年)に豊後国日田郡に蔵入地の代官として赴任し、日隈城を築城した。文禄3年(1594年)の時点で豊後日田・玖珠2万石(4万石とも)の蔵入地代官を務めている。
慶長3年(1598年)慶長の役の最中に秀吉が没した後、徳川家康より命を受け、徳永寿昌、山本重成とともに渡海し、朝鮮へ戦役中の将兵の撤兵を指導した。その功により翌慶長4年(1599年)、従五位下丹波守に任官する。
慶長5年(1600年)関ヶ原の戦いでは、西軍として大坂城平野橋を警護したため、戦後所領を没収されるが、頼久とともに徳川氏に仕える。頼久は慶長10年(1605年)実兄の山崎家盛より但馬国二方郡6000余石を分知され、芦屋に陣屋を構えたが、慶長14年(1609年)豊盛より先立って死去。その子の十二郎(のちの豊嗣)は5歳と幼いため、豊盛が後見として大坂の陣に出陣するなど実質的な当主として活躍した。
その後、駿府の徳川家康に仕え、家康死後は徳川秀忠の御伽衆となった。元和元年(1614年)、慈照寺(銀閣寺)再建の奉行や、元和5年(1619年)京都知恩院の普請奉行を務めている。
翌、同6年(1620年)京都にて67歳で死去。墓所は近江国今勝谷の阿弥陀寺。
以下は下記の日本国民全員が必読の書からである。
歴史の重みが民衆レベルでの一体感を生む
高山
1993年、私がロス特派員で米国にいた時、たまたまクリントン主催のAPECが開かれました。
日本からは細川護煕が来て、マハティールが日本とASEANで東アジア経済協議体(EAEC)という経済機構をつくろうと呼びかけていた時代だから、APECでそれを潰そうとしていた。
シアトルで各国の首脳が並ぶ中、クリントンが腰をかがめて、細川護煕を案内していた姿に驚きました。
まるで劇場の「お席はこちらです」の案内係(usher)のように、細川の前を、腰をかがめて行く。
彼はその後おかしくなったけれども、アーカンソーのドン百姓と400年間続いてきた大名家では、おのずと品格の違いが出ます。
日本のことなど何も知らないクリントンでさえ、やはり歴史を背景とする風格のようなものを彼に感じていた。
細川自身が気付いていないだけで。
渡部
そう、本人が気付いていない(笑)。おもしろいですね。
高山
彼も不思議に思わなかったのでしょうか。
どうしてクリントンが腰をかがめて俺を先導するんだろうって。
テレビを兒ながら、頭を下げたりなんかしないで、胸を張って案内させればいい、と思っていました。
日本にはその場面は放映されなかったかもしれません。
向こうの番組では延々と流していました。
渡部
なるほど。
長い歴史がつながりをもって感じられ、公家や大名家が今にいたるまで存続してきたのも、勝者が徹底して復讐することがなかったからです。
だから日本では、国体が何度か変化しても、天皇を戴くという根本は断絶しませんでした。
例えば明治維新があっても、徳川家が二代にわたって貴族院議長を務め、幕藩時代の大名が華族として待遇されたのは、いわゆる革命とはいいがたい。
かつて朝敵といわれた会津松平家の娘さんが皇族と結婚するなど(秩父宮雍仁親王妃)、融和を進めたわけです。
高山
遡ってみれば関ケ原の後始末も、西軍に参加した大名を外様として存続させ、日本全体で和をもって尊しとした。
これも欧米の歴史にはなかなかないことですね。
渡部
だからこそ日本人はどこかで、やはり日本人同士だという感覚を持てるわけです。
神話の時代から歴史が地続きであり、例えば『古事記』が成立した712年から続く歴史をもっている近代国家はありません。
神話上で国を造った女神・男神の直系の子孫の系図が残っており、それが皇室につながっている。
神話から今の世代にいたるまで系図がつながっている国なんて、ギリシヤ神話でもゲルマン神話でも、ありえないですよ。
そうすると、やはり一体感がほかの国とは違うのではないですか。
外国人に説明して驚くか信じるか分かりませんけれども、2014年、高円宮家のお嬢様である典子女王と出雲神社の権宮司(父の宮司に次ぐ地位)の千家国麿さんが結婚しましたね。
それはどこまで遡るかというと、皇孫である瑣瑣杵尊の子孫が高円宮家で、瑣瑣杵尊の弟が千家家の先祖になるわけです。つまり、神代からのつながりです。
そんないにしえの時代から、両家ともずっと系図がつながっていて、神社まで現存している。
神社も系図も、ともに実物が残っているわけです。
この話を外国にあてはめてみますと、トロイ戦争で攻めていったアカイアのアガメムノンの子孫が、まだ現存して神殿を守っていて、攻められたトロイの子孫もまだ残っており、そのお嬢さんとアガメムノンの子孫が、系図も残っている上で結婚するような、まあ考えられない話になるんです(笑)。 それが考えられるどころか、実現しているじゃないですか。 出雲大社は『古事記』のオオクニヌシの国譲り伝承に出てきますね。
国を譲る代わりに、壮大な出雲大社を建てるように要求した話です。
「底つ石根に宮柱太しり、高天原に千木高しりて治め賜はば、僕は百足らず八十隈手に隠りて侍ひなむ」(土の底の石根に届くまで宮柱を据え、高天原に届くほど高々と千木を立てた大社を建ててくれれば、私は国を譲り、鎮まって籠りましょう)と書いてあるその通りのものが、出雲大社に残っています。
神話の時代の建物の形が残されている。
もっと簡単な話で、東西南北といいますね。
このうち西・南・北の読み方は2つだけです。
西はセイとにし、南はナンとみなみ、北はホクときだ、音と訓です。
ところが東だけは3つあるんです。
トウとひがしとあずま。
これがなぜかといえば、日本武尊の東征神話です。
房総半島に向けて海を渡るために、后の弟橘比売が入水して荒波を鎮めた犠牲を「吾妻はや」と嘆いたのが、東国を「あずま」と呼ぶ起源になりました。
この神話によって、あずまという読みが現代まで続いているわけです。
独特な国であり、一種の奇跡といってもいいでしょう。
高山
その神話を頭から否定して、歴史のつながりを断ち切ろうとしたのもマッカーサーでした。
それでも、神話の時代から有史時代へ、歴史のつながりが感じられるのは、古いものが保存され、日本社会に生き続けているのを実感できるからです。
例えば最近、縄文時代の研究が進んで、日本は世界のはずれの辺境だとずっといわれていたのが、まったく違っていたことが分かってきました。
とても華やかな装飾品や交易品、平等で人間味のある社会を築いていた縄文時代が、その後の日本文化の基盤を作った。土器も世界に先駆けて作られていました。
こういうことを日本人は知らないし、知らせようとしない新聞やメディアがある。
日本人は、それこそ縄文の昔からずっと、クリやヒエを植えて、豊かな自然と調和しながら暮らし、世界に先んじて洗練された集団生活を営み、それが今日の社会や組織のあり方にまで連綿と受け継がれてきたのです。
そうでなければ、これだけ成熟した民主国家はできません。
渡部
そうですね。
高山
先日、壱岐に行きました。『日本書紀』に出てくる月讀神社(京都の月読神社の元宮)、天照大神の弟で素戔鵈尊の兄神である月読命の神社がちゃんと残っていました。
元寇で荒らされても何ら影響を受けず、神社が大切にされていて、おもしろいことに壱岐にはお寺がなくて神社ばかりなんです。
日本のあちこちを訪ねると、神話がそのまま神社として形を残していて、仏教伝来より前の歴史がしっかり保存されている。
古来からのものが受け継がれていることを実感します。
渡部
占領軍は「天皇が神ではない」ことを示すために神道指令(禁止令)を出して日本の宗教に干渉してきました。
例えば神宮皇學館という学校は一時廃止され、國學院大学でも「古事記」を教えることができなくなった。
しかし私のいた上智大学では、教養科目で古事記の講義があったのです。
私はこの講義に出席して古事記そのものを読み、神話が日本人の歴史観の根底をなしていることを知りました。
戦後70年経ってもなお、その事実は変わりませんし、むしろ多くの日本人がそれに気づくようになっています。大した変化です。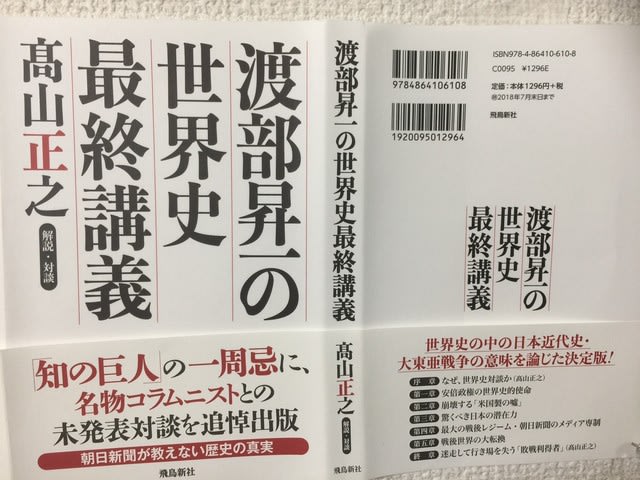
以下は、昨日、発売された週刊新潮に掲載された高山正之の連載コラムからである。
奪われた怨み
昔も今も戦争(War)といえばみな征服(Conquer)戦争を指す。
征服とは相手の領土を奪うことを言う。
旧約聖書時代、ユダヤの神はモーゼに今のイスラエルの地を征服しろ、そこに先住する民は片端から殺して領土を奪えと命じた。
民数記にはミディアン人の征服が微細に記されていて、まず兵士を皆殺しにし、彼らの街も襲って「男は赤ん坊まで殺せ」「既婚の女も殺せ」と命じた。ただ「処女はお前たちへの贈り物にするがいい」
この戦法はユダヤ人に限らずモンゴル人もスペイン人も真似て領土を広げた。
米国人も新大陸につくと先住民を300年かけて殺し尽し、今の国土を得た。
ハーマン・メルビルは「米国人は現代のイスラエルびとだ」と先住民大虐殺をむしろ誇らしげに書いている。
現代の文明人はメルビルみたいな無教養な発言は控え、領土目的でも征服と言わずにただの戦争と言う。
独仏国境のアルザス・ローレーヌはその意味で格好の「戦争」見本だ。
独がまず普仏戦争でここを征服し、独語を教室で教えさせ、ローレーヌもロートリングンと独風の名にした。
仏人作家のアルフォンス・ドーデはそれが悔しくて『最後の授業』を書いた。
次に第一次大戦で仏が取り返すと仏語授業が再開され、第二次大戦ではヒットラーが占領してまたまた独語に戻したが、戦後はみたび仏語に戻っている。
この取り返しごっこでも分かるように、戦争で取られると悔しい。
いつか取り返そうと思う。
逆によその領土を取れば、それは民族的な勝利であり、これ以上誇らしいものはない。
この思いは今も生きる。
例えば支那。
先の戦争ではアジアを裏切って白人国家に与して日本と戦った。
ルーズベルトは蒋介石に裏切りの報酬として「香港と仏印をくれてやろう」(C・ゾーン『米英にとっての太平洋戦争』)と言った。
戦勝国の証としての領土獲得だ。
おまけに両方とも元支那領。
奪われた領土を取り返せるのは至上の喜びだが、蒋は英仏という白人大国の機嫌を損ねるのを恐れて辞退した。
むしろ蒋は支那人のプライドとして日清戦争で日本に取られた朝鮮と台湾を取り返したかった。
白人相手ならしょうがないと諦めもつくが、同じ黄色同士だと取られた悔しさは倍加される。
しかし朝鮮にはもうソ連が出ていた。
蒋介石は台湾だけで我慢した。
同じ思いは、実は蒋介石を追った今の支那共産党政権にもある。
ことに習近平は日清戦争に拘る。
つい先年も日清戦争120年の記念式典で「支那人の偉大なる復興」を語った。
今なら日本には負けない、最低で沖縄くらいは取ろうと思っているのだろう。
その思考の中に台湾も入ってくる。
支那の国家主席として奪われた台湾を自分の領土に編入したとき初めて120年の怨讐が晴れる。
しかし今はすごく中途半端で「一つの支那」論はトランプに一蹴され、台湾人までが「支那人と呼ばないで」とか言い出している。
習近平は今、台湾武力併合を語る。
取られた領土に対する思いはそこまで深い。
北方四島も同じだ。
ロシアはあのとき日本の武装解除を待って攻め込んだ。
何ともみっともない所行だが、そこまでするほど日露戦争に負けて領土利権を奪われた恨みは深い。
ホントは北海道まで征服するつもりだったのに武装解除しても日本軍は強かった。
結果は北方四島を取れただけだが、スターリンは大喜びした。
それほど思い入れのある領土問題について丸山穂高議員が「領土は戦争でしか解決しない」という論理を舌足らずに発言した。
趣旨はいい。
戦争でしか解決できない問題を別の手段でやるなら経済封鎖とか国交断絶とか、よほどの覚悟がいるということだ。
それなのに「あーあ戦争と言っちゃった」と枝野や前科者の辻元がキャーキャー騒ぐ。
お前らには外交は無理だ。
以下は、昨日、発売された週刊新潮に掲載された高山正之の連載コラムからである。
奪われた怨み
昔も今も戦争(War)といえばみな征服(Conquer)戦争を指す。
征服とは相手の領土を奪うことを言う。
旧約聖書時代、ユダヤの神はモーゼに今のイスラエルの地を征服しろ、そこに先住する民は片端から殺して領土を奪えと命じた。
民数記にはミディアン人の征服が微細に記されていて、まず兵士を皆殺しにし、彼らの街も襲って「男は赤ん坊まで殺せ」「既婚の女も殺せ」と命じた。ただ「処女はお前たちへの贈り物にするがいい」
この戦法はユダヤ人に限らずモンゴル人もスペイン人も真似て領土を広げた。
米国人も新大陸につくと先住民を300年かけて殺し尽し、今の国土を得た。
ハーマン・メルビルは「米国人は現代のイスラエルびとだ」と先住民大虐殺をむしろ誇らしげに書いている。
現代の文明人はメルビルみたいな無教養な発言は控え、領土目的でも征服と言わずにただの戦争と言う。
独仏国境のアルザス・ローレーヌはその意味で格好の「戦争」見本だ。
独がまず普仏戦争でここを征服し、独語を教室で教えさせ、ローレーヌもロートリングンと独風の名にした。
仏人作家のアルフォンス・ドーデはそれが悔しくて『最後の授業』を書いた。
次に第一次大戦で仏が取り返すと仏語授業が再開され、第二次大戦ではヒットラーが占領してまたまた独語に戻したが、戦後はみたび仏語に戻っている。
この取り返しごっこでも分かるように、戦争で取られると悔しい。
いつか取り返そうと思う。
逆によその領土を取れば、それは民族的な勝利であり、これ以上誇らしいものはない。
この思いは今も生きる。
例えば支那。
先の戦争ではアジアを裏切って白人国家に与して日本と戦った。
ルーズベルトは蒋介石に裏切りの報酬として「香港と仏印をくれてやろう」(C・ゾーン『米英にとっての太平洋戦争』)と言った。
戦勝国の証としての領土獲得だ。
おまけに両方とも元支那領。
奪われた領土を取り返せるのは至上の喜びだが、蒋は英仏という白人大国の機嫌を損ねるのを恐れて辞退した。
むしろ蒋は支那人のプライドとして日清戦争で日本に取られた朝鮮と台湾を取り返したかった。
白人相手ならしょうがないと諦めもつくが、同じ黄色同士だと取られた悔しさは倍加される。
しかし朝鮮にはもうソ連が出ていた。
蒋介石は台湾だけで我慢した。
同じ思いは、実は蒋介石を追った今の支那共産党政権にもある。
ことに習近平は日清戦争に拘る。
つい先年も日清戦争120年の記念式典で「支那人の偉大なる復興」を語った。
今なら日本には負けない、最低で沖縄くらいは取ろうと思っているのだろう。
その思考の中に台湾も入ってくる。
支那の国家主席として奪われた台湾を自分の領土に編入したとき初めて120年の怨讐が晴れる。
しかし今はすごく中途半端で「一つの支那」論はトランプに一蹴され、台湾人までが「支那人と呼ばないで」とか言い出している。
習近平は今、台湾武力併合を語る。
取られた領土に対する思いはそこまで深い。
北方四島も同じだ。
ロシアはあのとき日本の武装解除を待って攻め込んだ。
何ともみっともない所行だが、そこまでするほど日露戦争に負けて領土利権を奪われた恨みは深い。
ホントは北海道まで征服するつもりだったのに武装解除しても日本軍は強かった。
結果は北方四島を取れただけだが、スターリンは大喜びした。
それほど思い入れのある領土問題について丸山穂高議員が「領土は戦争でしか解決しない」という論理を舌足らずに発言した。
趣旨はいい。
戦争でしか解決できない問題を別の手段でやるなら経済封鎖とか国交断絶とか、よほどの覚悟がいるということだ。
それなのに「あーあ戦争と言っちゃった」と枝野や前科者の辻元がキャーキャー騒ぐ。
お前らには外交は無理だ。
以下は、昨日、発売された週刊新潮に掲載された高山正之の連載コラムからである。
奪われた怨み
昔も今も戦争(War)といえばみな征服(Conquer)戦争を指す。
征服とは相手の領土を奪うことを言う。
旧約聖書時代、ユダヤの神はモーゼに今のイスラエルの地を征服しろ、そこに先住する民は片端から殺して領土を奪えと命じた。
民数記にはミディアン人の征服が微細に記されていて、まず兵士を皆殺しにし、彼らの街も襲って「男は赤ん坊まで殺せ」「既婚の女も殺せ」と命じた。ただ「処女はお前たちへの贈り物にするがいい」
この戦法はユダヤ人に限らずモンゴル人もスペイン人も真似て領土を広げた。
米国人も新大陸につくと先住民を300年かけて殺し尽し、今の国土を得た。
ハーマン・メルビルは「米国人は現代のイスラエルびとだ」と先住民大虐殺をむしろ誇らしげに書いている。
現代の文明人はメルビルみたいな無教養な発言は控え、領土目的でも征服と言わずにただの戦争と言う。
独仏国境のアルザス・ローレーヌはその意味で格好の「戦争」見本だ。
独がまず普仏戦争でここを征服し、独語を教室で教えさせ、ローレーヌもロートリングンと独風の名にした。
仏人作家のアルフォンス・ドーデはそれが悔しくて『最後の授業』を書いた。
次に第一次大戦で仏が取り返すと仏語授業が再開され、第二次大戦ではヒットラーが占領してまたまた独語に戻したが、戦後はみたび仏語に戻っている。
この取り返しごっこでも分かるように、戦争で取られると悔しい。
いつか取り返そうと思う。
逆によその領土を取れば、それは民族的な勝利であり、これ以上誇らしいものはない。
この思いは今も生きる。
例えば支那。
先の戦争ではアジアを裏切って白人国家に与して日本と戦った。
ルーズベルトは蒋介石に裏切りの報酬として「香港と仏印をくれてやろう」(C・ゾーン『米英にとっての太平洋戦争』)と言った。
戦勝国の証としての領土獲得だ。
おまけに両方とも元支那領。
奪われた領土を取り返せるのは至上の喜びだが、蒋は英仏という白人大国の機嫌を損ねるのを恐れて辞退した。
むしろ蒋は支那人のプライドとして日清戦争で日本に取られた朝鮮と台湾を取り返したかった。
白人相手ならしょうがないと諦めもつくが、同じ黄色同士だと取られた悔しさは倍加される。
しかし朝鮮にはもうソ連が出ていた。
蒋介石は台湾だけで我慢した。
同じ思いは、実は蒋介石を追った今の支那共産党政権にもある。
ことに習近平は日清戦争に拘る。
つい先年も日清戦争120年の記念式典で「支那人の偉大なる復興」を語った。
今なら日本には負けない、最低で沖縄くらいは取ろうと思っているのだろう。
その思考の中に台湾も入ってくる。
支那の国家主席として奪われた台湾を自分の領土に編入したとき初めて120年の怨讐が晴れる。
しかし今はすごく中途半端で「一つの支那」論はトランプに一蹴され、台湾人までが「支那人と呼ばないで」とか言い出している。
習近平は今、台湾武力併合を語る。
取られた領土に対する思いはそこまで深い。
北方四島も同じだ。
ロシアはあのとき日本の武装解除を待って攻め込んだ。
何ともみっともない所行だが、そこまでするほど日露戦争に負けて領土利権を奪われた恨みは深い。
ホントは北海道まで征服するつもりだったのに武装解除しても日本軍は強かった。
結果は北方四島を取れただけだが、スターリンは大喜びした。
それほど思い入れのある領土問題について丸山穂高議員が「領土は戦争でしか解決しない」という論理を舌足らずに発言した。
趣旨はいい。
戦争でしか解決できない問題を別の手段でやるなら経済封鎖とか国交断絶とか、よほどの覚悟がいるということだ。
それなのに「あーあ戦争と言っちゃった」と枝野や前科者の辻元がキャーキャー騒ぐ。
お前らには外交は無理だ。









