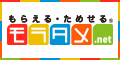水谷がこの論争の矢面に立ったのは、その(彼の妻の)死の直後だった。彼の判断を、「非人道的」とし、これを、「殺人」であると、全てのメディアがうたい、そのメディアを通して彼のことを知った全ての人間が、彼に背を向けたのだ。
彼は、満身創痍の中、城山からの取材を受けた。城山は、
「あなたの考え方が間違っていないということを、訴えるのです。私だけは、あなたの味方です!」
と、興奮気味に語ったが、水谷は、あまり興味を示さなかった。まだ20代後半の若さだった城山は、そんな弱々しい水谷の人となりを、特集記事として世に送り出した。そして、彼が、妻の安楽死を選ばざるを得なかった原因を、紙面の向こう側にいる人々に訴えた。他に身寄りの無い水谷夫妻に、憐れみの言葉を浴びせる人間は数多くいたが、彼らの悲壮感を揺り動かせる人間はいなかったのだ。
城山は、記事に、あらゆることに金がかかり過ぎることと、老いた女の介護をする人間が年老いた夫、たった1人だけだったことを、主に大きく取り上げ、町内の人々から、病院、果ては日本国政府に至るまで、2人に手を差し伸べてこなかったものを、逆に叩き始めた。そして、この記事をして、この老人が自らの悲壮感を破り、胸を張って生きていくことができるようにすること、それが、自分が記者として、いや、人間として、この記事を書く、唯一の、そして最大の、目的だと思ったのだ。
本当に、そう思っていただけだったのに、と城山は思った。そう信じて何度となく書いてきた記事で、自分は、雑誌記者などという野暮ったい肩書きを捨て、ジャーナリストと呼ばれるようになり、その、自分の名前の前に付くカタカナを否定する間も無いまま、テレビに出るようにもなった。そして水谷老人は、城山の記事によって、全国から応援と資金援助の手紙を、何十、何百と受け取って、次第に世間に受け入れられていった(しかも好意的に、だ)。
そうだ。こうなることを信じてここまで来たのだ。
これが信じた道だった。・・・これで良かったのだ。
そう、・・・信じていた。1人の老人の死を聞くまでは。
自分は、この論争と心中するつもりでいた。しかし、老人は、1人で先に死んでしまった。この論争と自分の2つを道連れにすることなしに。・・・ということは、彼の死は、城山を始めとして、彼の味方となった多くの人たちだけでなく、水谷本人にとっても、予期することのできなかった突然の死だということだ。問題は、これが、事故か、事件に巻き込まれた死だったのか。それによって、自分が水谷の死を、記事としてどう扱うかも変わってくる。が、どちらにしても、その大きな見出しの下に載るであろう、それと同等、あるいはそれ以上の大きさの城山の名前が、記事の内容よりも先に、読み手の興味を引くのに間違いは無い。
(つづく)
彼は、満身創痍の中、城山からの取材を受けた。城山は、
「あなたの考え方が間違っていないということを、訴えるのです。私だけは、あなたの味方です!」
と、興奮気味に語ったが、水谷は、あまり興味を示さなかった。まだ20代後半の若さだった城山は、そんな弱々しい水谷の人となりを、特集記事として世に送り出した。そして、彼が、妻の安楽死を選ばざるを得なかった原因を、紙面の向こう側にいる人々に訴えた。他に身寄りの無い水谷夫妻に、憐れみの言葉を浴びせる人間は数多くいたが、彼らの悲壮感を揺り動かせる人間はいなかったのだ。
城山は、記事に、あらゆることに金がかかり過ぎることと、老いた女の介護をする人間が年老いた夫、たった1人だけだったことを、主に大きく取り上げ、町内の人々から、病院、果ては日本国政府に至るまで、2人に手を差し伸べてこなかったものを、逆に叩き始めた。そして、この記事をして、この老人が自らの悲壮感を破り、胸を張って生きていくことができるようにすること、それが、自分が記者として、いや、人間として、この記事を書く、唯一の、そして最大の、目的だと思ったのだ。
本当に、そう思っていただけだったのに、と城山は思った。そう信じて何度となく書いてきた記事で、自分は、雑誌記者などという野暮ったい肩書きを捨て、ジャーナリストと呼ばれるようになり、その、自分の名前の前に付くカタカナを否定する間も無いまま、テレビに出るようにもなった。そして水谷老人は、城山の記事によって、全国から応援と資金援助の手紙を、何十、何百と受け取って、次第に世間に受け入れられていった(しかも好意的に、だ)。
そうだ。こうなることを信じてここまで来たのだ。
これが信じた道だった。・・・これで良かったのだ。
そう、・・・信じていた。1人の老人の死を聞くまでは。
自分は、この論争と心中するつもりでいた。しかし、老人は、1人で先に死んでしまった。この論争と自分の2つを道連れにすることなしに。・・・ということは、彼の死は、城山を始めとして、彼の味方となった多くの人たちだけでなく、水谷本人にとっても、予期することのできなかった突然の死だということだ。問題は、これが、事故か、事件に巻き込まれた死だったのか。それによって、自分が水谷の死を、記事としてどう扱うかも変わってくる。が、どちらにしても、その大きな見出しの下に載るであろう、それと同等、あるいはそれ以上の大きさの城山の名前が、記事の内容よりも先に、読み手の興味を引くのに間違いは無い。
(つづく)