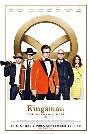今年最初の試写は、『ハートロッカー』(08)『ゼロ・ダーク・サーティ』(12)の“女オリバー・ストーン”こと、キャサリン・ビグローが、1967年のデトロイト暴動の最中に起きた「アルジェ・モーテル事件」を描いた『デトロイト』だった。

前半は、暴動が広がる様子を、中盤はアルジェ・モーテル事件を、後半は裁判を描く、という三幕構成。アルジェ・モーテル事件における、白人警官が黒人に強いる、逃げ場のない“死のゲーム”の執拗な描写を見ていると、案外、女性の方がしつこいのかもしれないと思えてくる。
ただならぬというか、不快な緊張感が漂う中、警官役のウィル・ポールターの嫌悪感しか抱かせないような演技が秀逸だ。こういう映画を見ると、今も続く、白人警官による黒人への暴力の原因は、単純なものではなく、人種、貧困、労働など、根深い問題をはらんでいる、と改めて感じさせられた。
ところで、モータウンがデトロイトの治安の悪さからロサンゼルスに移ったのは知っていたが、「イン・ザ・レイン」を歌っていたドラマティックスが事件に巻き込まれていたことは知らなかった。72年に発表されたこの曲は、事件との直接の関係はないのだが、映画を見た後で久しぶりにこの曲を聴き、歌詞の意味を考えたら、感慨深いものがあった。