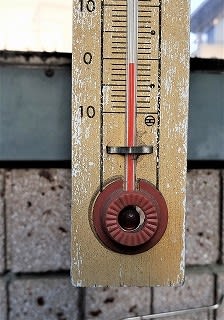写真右側の消印(Aさんから)は2月6日の12~18時、左側の消印(B社から)は2月7日の12~18時、Aさんと同じ居住区のわが家へ届いたのは両方とも2月8日の15時ころ。切手の消印日付を見ていて面白いことに気づいた。Aは居住区内のポストに投函。Bはわが家から90キロ近く離れている山口市でAより1日遅れの投函、それが同時に届いた。
Bの届いた状況から推測すればAは1日早く届くのが当たり前ではと、苦笑しながら見比べる。日本郵便(株)も民営化するとき「サービスが低下することはない」という宣言だったが、その通りに運んでいない。一例だが、郵便の収集配達していた局が業務の合理化とかで、その業務を他局と統合され配達時間が半日あまり遅くなった。ほかにも不便が生じている。
配達は仕事と言わず、HPでは「サービス」となっている。サービスと言えば奉仕とか客の便利を図ることに使う。配達は仕事と思っていたが仕事ではなくサービス、だから、しなければならない、ことではないことになるのだろう。サービス精神では郵便を投函した人の委託を真摯に遂行する姿勢が欠ける社員が存在するかもしれない。
60年以上昔の話し。高校時代3年間、夏と冬の繁忙期に郵便配達のアルバイトをした。赤色の自転車が唯一の動く乗り物、鞄や籠を荷台に乗せて走り回った。日給300円、それでも当時では高額バイトだった。今なら20分ほどの金額しかない。ささいな切手の消印からあれこれ思いつくのは、毎日サンデーのせいだろうか。