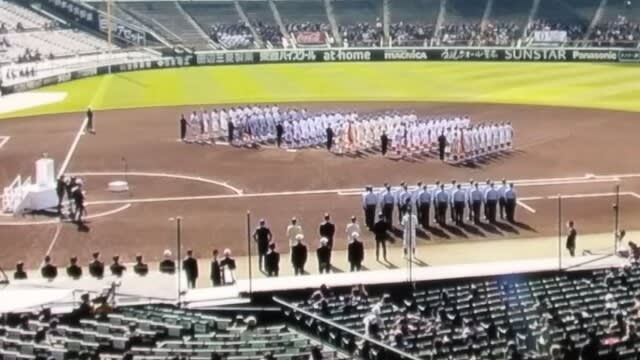令和3年3月21日(日)
お彼岸 : 彼岸会

春分の日・秋分の日を中日として、その前後三日ずつ
の七日間をいう。
彼岸は、梵語(古代インドの文語、サンスクリット)の
波羅の漢訳である仏教用語由来し、生死流転に迷うこの
世界、即ち此岸(しがん)に対して、煩悩の流れを渡っ
て到達した悟りの境地の意である。 この間を彼岸会と
呼んで、寺や墓に詣でたり、寺院では読経、法話を行う。
この風習は中国、インドには無く、日本では聖徳太子の
時代に始まったと言われる。
春秋二期の彼岸の時を涅槃彼岸に近づくための仏道精進
の期間として、中古以来盛んに行われて来たが、近世に
至り、宗教が幕府の統制下に置かれる様になって以降は
もっぱら葬式法要のみを事とし、祖先の追善供養習慣と
なった。
春の彼岸は単に「彼岸」と呼び、秋の彼岸は「秋彼岸」
「後彼岸」という。「暑さ寒さも彼岸まで」と言われる
ように、春は庭木が萌え、秋は秋草が盛りという良い
陽気となるので、野遊びを兼ねた墓参風景が随所で見ら
れる。

彼岸の墓地はよく清掃され、洗われた墓には新しい供花
が上がり、線香の匂い立ち込める。そうした中に何の事
情か、詣でる人の無い墓がヒッソリと立っているのは、
何とも哀れをそそる。
春は、彼岸を境に一気に春が定まるようである、、、。


昨夜から雨が降り続く、、、遂、出そびれて、午後に
カミさんが慌てて「牡丹餅」を買いに走る。


最近、茶請けには和菓子が良い(これも齢の所為か)
(それでも、娘の手土産のケーキも確り食べる)
今日の1句
お彼岸の牡丹餅買ひに奔りけり ヤギ爺