「天作会展」に出品された森本順子さん、ハシグチ リンタロウさんの作品を紹介します。


●
森本順子
森本さんの作品の素晴らしさは
とても言葉では表現できません。
ただただ茫然と立ち尽くし、魂の奥まで解放される。
そんな至福の時を与えてくれる。
そんな感じです。
師匠の越智先生の感想をどうぞごらんください。



●
ハシグチ リンタロウ
ハシグチさんとは、会場で初めてお目にかかり
いろいろとお話を伺うことができました。
若くて穏やかな方で、技術的なことまで詳しく教えてくださいました。
作品の下に、ひっそりとおかれたA4のプリント「STATEMENT 「光影残象」」は
書だけではなく、芸術、そして「生きる」ということまで
深く考えさせる文章でした。
その文章を読みながら、この2点の作品をご覧ください。

光影残象

柱
●
以下は、「柱」の部分です。



●
ハシグチ リンタロウさんの「STATEMENT」

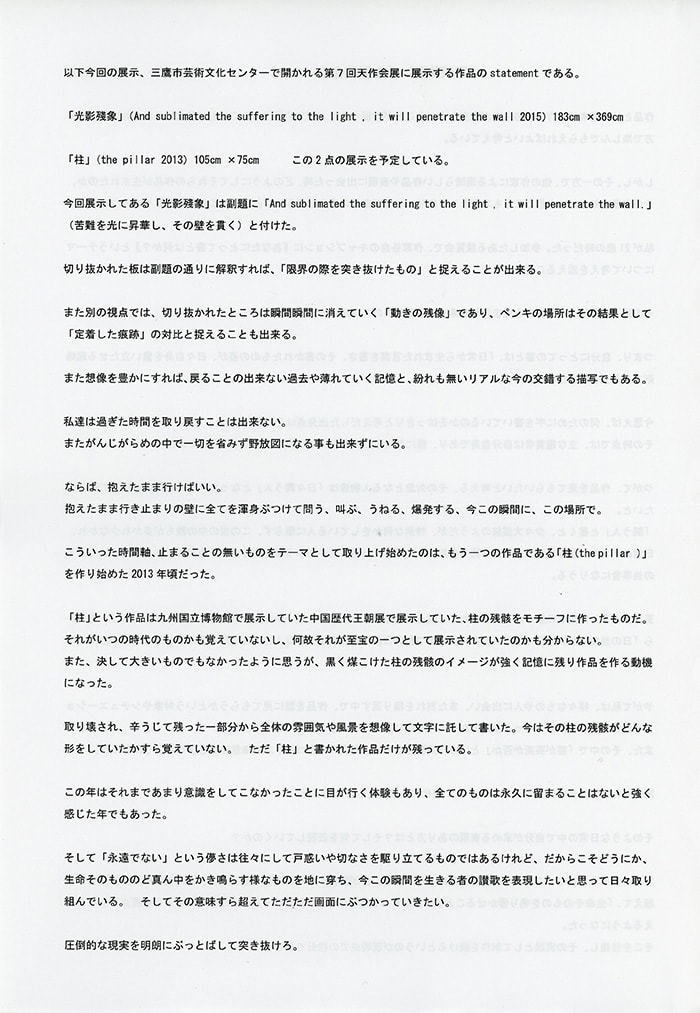
この文章があまりにも素晴らしく、示唆に富んでいるので
以下、テキスト化しておきます。
STATEMENT 「光影残象」ハシグチ チリンタロウ
作品とは、基本的に作品そのものが自立していることが前提であり、釈文や解説は無くとも、見た人それぞれの受け取り方で楽しんでもらえればよいと考えている。
しかし、その一方で、他の作家による素晴らしい作品や表現に出会った時、どのようにしてそれらの作品が生まれたのか、その背景を知りたいと思うことも本音としてあり、ならば自分の場合はどうか? と思い、この文章を書くことにした。
私が21歳の時だった。参加したある展覧会で、作家各自のキャプションに『あなたにとって書とは何か?』というテーマについて考えを添えることになった。
その時、私は短く「日常から生まれた日常を生きるためのエネルギー」とだけ書いた。
つまり、自分にとっての書とは、「日常から生まれた言葉を書き、その書かれたものの姿が、日々自身を奮い立たせる起爆剤である」と考えたのだ。
今思えば、何のために字を書いているのかをはっきりと考えだした出発点はその頃だった。
その時点では、主な鑑賞者は自分自身であり、誰に見て欲しいか? については、ぼんやりとしていた。
やがて、作品を見てもらいたいと考える、その対象となる人物像は「日々闘う人」となった。そんな人たちに見てもらいたいと。
「闘う人」と書くと、少々大袈裟のようだが、特別な何かをしている人に限らず、この世の中の誰もが多かれ少なかれ、日常のーコマ、すなわち、日々ある種の岐路の上に常に立たされているようなものであり、当然のことながら、誰もがその当事者になりうる。
更に、そうした無名の誰かが、何かのために闘っている、というシチュエーションは「知られざるもの」であり、そこから「日の当たらない場所で闘う人」と、少しずつ私の作品の鑑賞者はこんな人物ではなかろうか? という輪郭が出来ていった。
やがて私は、様々なものや人に出会い、また別れを繰り返す中で、作品を誰に見てもらうかという対象やシチュエーションを区切ることをやめ、もっと根源的なテーマを取り扱いたいと思うようになっていった。
また、その中で「書が芸術か否か」といった問題を含めて、表現の力テゴライズの無意味さを感じるようになった。
隔てられ、細分化されるカテゴリー。現代の人間生活もまた同じだ。
そのような日常の中で自分が求める表現のあり方とは? そして何を表現していくのか?
思索を続けるなかで、これまでの動機を下地としつつも、書が芸術かどうかの壁を乗り越え、また技法の巧拙新旧を飛び超えて、「生命そのものを鳴り響かせること」が目指すべき場所であり、同時にそれこそが表現そのものの原点であると考えるようになった。
そこを目指し、その実践として制作を続けるというのが現時点での指針である。
*
以下今回の展示、三鷹市芸術文化センターで聞かれる第7回天作会展に展示する作品のstatementである。
「光影残象」(And subIimated the suffering to the Iight , it wi11 penetrate the walI 2015) 183cm×369cm
「柱」(the piIlar 2013) 105cm×75cm この2点の展示を予定している。
今回展示してある「光影残象」は副題に「And sublimated the suffering to the Iight , it wi11 penetrate the walI」(苦難を光に昇華し、その壁を貫く)と付けた。
切り抜かれた板は副題の通りに解釈すれば、「限界の際を突き抜けたもの」と捉えることが出来る。
また別の視点では、切り抜かれたところは瞬間瞬間に消えていく「動きの残像」であり、ペンキの場所はその結果として「定着した痕跡」の対比と捉えることも出来る。
また想像を豊かにすれば、戻ることの出来ない過去や薄れていく記憶と、紛れも無いリアルな今の交錯する描写でもある。
私達は過ぎた時間を取り戻すことは出来ない。
またがんじがらめの中で一切を省みず野放図になる事も出来ずにいる。
ならば、抱えたまま行けばいい。
抱えたまま行き止まりの壁に全てを渾身ぶつけて問う、叫ぶ、うねる、爆発する、今この瞬間に、この場所で。
こういった時間軸、止まることの無いものをテーマとして取り上げ始めたのは、もう一つの作品である「柱(the piIlar)」を作り始めた2013年頃だった。
「柱」という作品は九州国立博物館で展示していた中国歴代王朝展で展示していた、柱の残骸をモチーフに作ったものだ。それがいつの時代のものかも覚えていないし、何故それが至宝のーつとして展示されていたのかも分からない。
また、決して大きいものでもなかったように思うが、黒く煤こけた柱の残骸のイメージが強く記憶に残り作品を作る動機になった。
取り壊され、辛うじて残った一部分から全体の雰囲気や風景を想像して文字に託して書いた。今はその柱の残骸がどんな形をしていたかすら覚えていない。ただ「柱」と書かれた作品だけが残っている。
この年はそれまであまり意識をしてこなかったことに目が行く体験もあり、全てのものは永久に留まることはないと強く感じた年でもあった。
そして「永遠でない」という儚さは往々にして戸惑いや切なさを駆り立てるものではあるけれど、だからこそどうにか、生命そのもののど真ん中をかき鳴らす様なものを地に穿ち、今この瞬間を生きる者の讃歌を表現したいと思って日々取り組んでいる。そしてその意味すら超えてただただ画面にぶつかっていきたい。
圧倒的な現実を明朗にぶっとばして突き抜けろ。

















