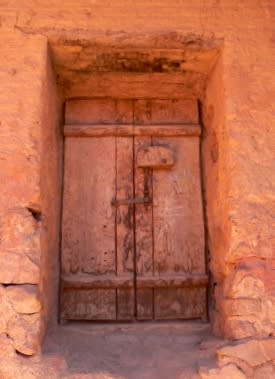『夏目漱石最後の〈笑い〉『明暗』の凡常』第二章 4 細谷博 著 進典社 南山大学学術業書 メモ
『夏目漱石最後の〈笑い〉『明暗』の凡常』
第二章 3の続き
「気の能く廻る津田の頭」(80)
「技巧的な彼」(80)
「怜悧」
小林→津田
「君という男は、非常に用意周到なようで何処か抜けているね。あんまり抜けますまい抜けますまいとするから、、、、、、、」
ここまで読んではいたが、しばらく他の本を読み中断していた『夏目漱石最後の〈笑い〉『明暗』の凡常』。
理由は簡単。
夏目漱石著の『明暗』の読み進みが追いついていないため。
とりあえず『夏目漱石最後の〈笑い〉『明暗』の凡常』を先へ進もうと端折ってはみたが、漱石の本文が私には追いついてないことが欠点となる。
ページは、『夏目漱石最後の〈笑い〉『明暗』の凡常』の124頁まで進んだところで、一旦ストップ。
付箋だらけで王冠をかぶったような『夏目漱石最後の〈笑い〉『明暗』の凡常』の状態には、我ながら恥ずかしさを覚える。
『夏目漱石最後の〈笑い〉『明暗』の凡常』を読むだけでも十分に興味深く、読む価値は十二分にある。しかしながら、私の性格としては原作を押さえておきたい。
よって、ここしばらくは『明暗』そのものを先に進み、また『夏目漱石最後の〈笑い〉『明暗』の凡常』に戻ることにしようと思う。
小林→津田
「君という男は、非常に用意周到なようで何処か抜けているね。あんまり抜けますまい抜けますまいとするから、、、、、、、」
から124頁にかけての中で次のことに興味を持った。
吉川夫人の重要性が
見合いの席での位置関係
そして興味を持った言葉は、
「良夫(おっと)というものは、ただ妻の情愛を吸い込むためのみに生存する海綿に過ぎないのだろうか」(P.111)
原作に上の三点(青色)が出てくることを楽しみに、一旦『夏目漱石最後の〈笑い〉『明暗』の凡常』を横に置き参考にしながら、漱石作『明暗』の続きを読んでいくことにする。
社会人入学か履修生になって国文を学びたいと思ってはいた。
だが、コロナ禍に加え授業料の高さ、距離の遠さに意気消沈した私。
今更ながらに、国文を専攻しておけば良かったという後悔は大きい。
だが、このような良書を知り、本の力及びアドバイスを借りて、文学や古典を学ぶことができるのは嬉しい限りである。
国文学の入門の一つとして、こう行った本を知ることができたのは、幸運というほかはない。
では、古典に加えて、漱石の続きを読むことにする。
加えて、遠野地方にも行ってみたいので、以前読んだが柳田國男の『山の人生』ほか多くを今一度読んでおこう。
柳田國男全集の『山の人生』の載った巻は家族が持ち帰っているので、購入なり図書館でお借りしようと思う。
やりたいことが多過ぎて、困るが、これも幸せな人生だとつくづく感じる。







写真は興福寺 薪能
みなさま
お越しくださいまして、ありがとうございます。
心より感謝いたしております。