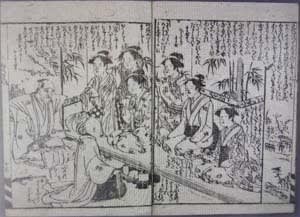『猫画之物語』(みょうがのものがたり)3 上/三冊 黒本 江戸時代 1枚

(一部写す)
村
名月は
まるといふ
まんじ一八十八
平のじなれば
壬午村源平と
たづねか
まんじ一八十八
平のじなれば
平の字を分解すると
一
八
十
八
で「平」の字となる。
壬午村源平は平家の関係なので、
まんじ一八十八
平のじなれば
と書かれているのであろう。
壬午村源平
壇ノ浦の戦いに関係する人物か?
壬午村
壬午村というのがあるらしい。

黒本
ヘ13 04285
[猫画之物語](みょうがのものがたり) 上,中,下
[出版地不明 江戸か]
[出版者不明 版元:鶴屋喜右衛門か]
[出版年不明 宝暦一三刊(1763)か]
17cm
公開者 早稲田大学図書館 (Waseda University Library)




『猫画之物語』(みょうがのものがたり)1 上/三冊 黒本 江戸時代 (2枚)
『猫画之物語』(みょうがのものがたり)2 上/三冊 黒本 江戸時代 1枚
『猫画之物語』(みょうがのものがたり)3 上/三冊 黒本 江戸時代 1枚