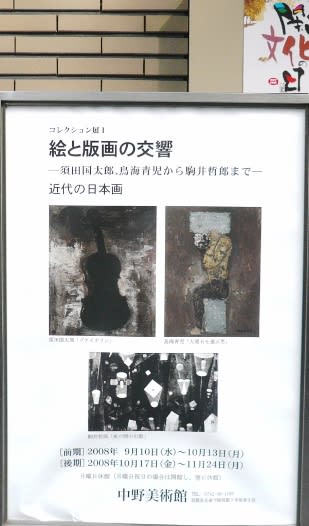中野美術館で
小出楢重・須田国太郎作品を楽しむ

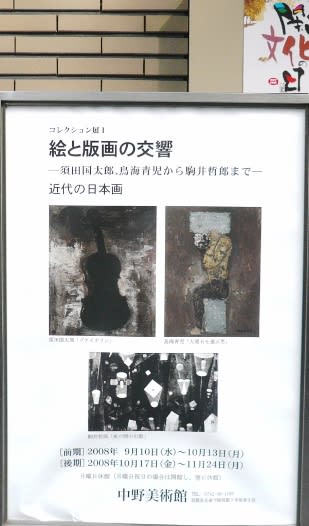
11月23日
念願の中野美術館に行く。
この日は関西文化の日。
入館料は無料。
十時からの開場。
半時間程度早く着いた私は、美術館の前で『宮田登日本を語る』を読み始めた。
すると、物腰の柔らかい紳士が、
「どうぞお入り下さいませ。」
と私に勧めて下さった。
他にもこの美術館を見たくて早く来られたご年配のご夫婦がいらっしゃって、
「私たちは一般人なのですが、入っても良いのでしょうか。」
っと、私に尋ねられる。
「宜しいのでは ございませんでしょうか・・・。」
と答えると、深々と挨拶して下さったのには 少々戸惑いを覚えた。
さてスリッパに履き替えて、中野美術館に入ると、たいそう上品で居心地の良い館内。
テヘラン(イラン)のガラス博物館のような、とても洒落た洋画の展示方には、心が躍る。
京都にも関係した、私の大好きな須田国太郎画伯の油二枚。
青銅色の入れ物は美しい。
重厚なナイフを潔く使ったバイオリンは、独立美術の特徴を顕著に表わしている。
かって父が描いた自画像は、画伯のこの絵のほんの一部分でも臭わしていることは喜ばしい。
まぁ、厚かましい思いである(笑み)
その右横には、これも私の大好きな小出楢重画伯の作品。静物画が一枚。
私の好きな、雑巾の捻れのような腰をした、女性裸婦像はなかった。
鏡のある静物は、空間がある種の雰囲気をかもしだし、絵に包み込むような色気を感じるのは素晴らしい。
流石の小出楢重画伯の一枚で、何度も何度も見とれてしまい、その場を離れられなかった。
鏡に映る景色は一体何だろうか・・・。
年月のたった、洋風の窓辺の木枠のサンの一部だろうか・・・。
京都の鳴滝にある 別荘風な室内を思い浮かべ、ほくそ笑んでしまう。今はあの家は、どうなったのだろう・・・。取り壊されてしまっているのだろうか・・・。感慨深く、作品を眺める。
この作品は一見何の変哲も無い静物画に思えるかも知れないが、実際にはドラマティックな作品。
構図においても 視線がぐるぐると回転し、その計算はセザンヌにも通じる。
洋画コーナーでは他にも多く展示されていた。
印象的なのは、長谷川利行画伯。
この画家は恥ずかしいことに 今まで知らなかった。
キャンバスの半分を占める顔の色彩は豊かで、コーラルレッドやオレンジ系の中に、寒色も加えられ、重厚感は素晴らしいと感じた。
鳥飼青児画伯の作品は多くあったが、私には構図のとり方が少しわからなかった。
これらは計算の上に、わざと外された遊びなのだろうか・・・。
勉強の余地あり。探りながら、数々の絵を見つめる。
駒井哲朗画伯のエッチングなどは洒落ていた。
音楽が流れていて数学的で、欲しいなと感じた作品が多かった。
たはは・・・、欲しいと思って手に入れられるような作品ではない(笑み)
階を変えると、日本画の展示室。
品の良い茶室に掛け軸。
この展示法は好きだった。
実際にこの茶室でお茶を点てられて、楽しまれるのかと思うと、絵が余計に生かされているように思う。幸せな気分に浸れた。
二十二日に東福寺の雪舟寺でニ時間程度を楽しんでいたので、茶室は余計に心に響いたのかも知れない。
立派な掛け軸などの見著重くする中、高村光雲作の女性像はどの角度から見ても美しい、品位を感じる作品だった。
また品を感じる作品として、入江波光画伯の『雛鳥』は見事に私の心をつかんで離さない。
本気で欲しいと感じさせる作品だった。あはは、バカだな。
村上華岳画伯の中国列仙傳の内からは二枚展示されていたが、すべて観てみたいと思わせる力作。
中野美術館はかなり上品で洒落ている。
この美術館は日本画展示室の前に、鴨の集まる美しい池が望める。
洋画質でも黒のゆったりとした椅子が設けられ、ゆっくりと楽しむことができる工夫がされている。
絵を選んだ方の知性と品格、美術館の居心地の良い洒落た空間には、見事に心をとらえられてしまった。
繰り返しになるが、私の好きなガラス博物館と重複したイメージで、洒落ていて居心地が良い。
好きな美術館がふえて、とても嬉しい。
最後に、輝くような素敵な時間をありがとうございました。
この場を借りまして、中野美術館関係者の方々に厚く御礼申し上げます。
中野美術館 (奈良・学園前 近鉄南出口 徒歩八分)
中野美術館 公式HP ▼
http://www.nakano-museum.ecweb.jp/























 ①
① ②
②