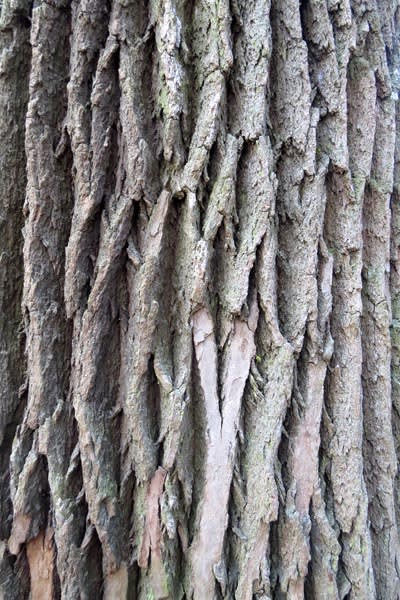図録
特別陳列『お水取り』
平成二十七年二月七日
編集・発行 奈良国立博物館

原付バイクで奈良情報図書館に行く。
片道、小一時間。往復二時間。
郡山までは度々行くわタック氏だが、そこからさらに二十分。
結構長い距離である。
それとなく図録を手に取る。
昨年度版の特別陳列『お水取り』
しかしながら、陳列は今年の三月七日に楽しんだ特別展の『お水取り展』とほぼ同じであった。
『お水取り展』はこれまでにも何度となく言っている。道理で今年も馴染みの深いものが多いと思ったわけだ。
しかしながら図録の中で、紙衣のページの説明は今年のものと異なっていた。
今年の紙衣の説明では、紙衣(紙で造った衣)の下に、木綿が縫い合わされてあると記されていた。
だが、平成二十七年二月七日の図録にはそれはない。
また展示物の近くの説明では、
[修行が激しいためにすぐに敗れるので、お水取り中、何度も替える]
とあったように思う。
ボランティアガイドの説明では、修行中、それを着続けると言われていたのと、紙衣の下には木綿が貼って縫い合わされている説明はされなかったのが印象深い。
やはりこう言った興味深いことは、自分の目で確かめ、資料を読まねばならないと痛感した。
昨日読んだ図録 特別陳列『お水取り』では、『二月堂縁起』二巻の多くが載せられていた。
時間の関係上、『二月堂縁起』の詞書は図書館内で読むのは省いた。
今年の特別展示では、「青い衣(の女?)」と「経を読み間違えた話」の部分が申し訳程度に出されていた。
あまりにも短いので、今年の展示部分は、三度ばかり読めた。
以前、あべのハルカスで、『東大寺展』が開催された。
この時は、東大寺関係の絵巻物を多く展示してくださったのでもごたえがあった。
絵巻物の好きな私は、あれこれと想像しながら、昨年度版の図録 特別陳列『お水取り』を楽しんでいた。

みなさま、ご訪問くださいまして、誠にありがとうございます。