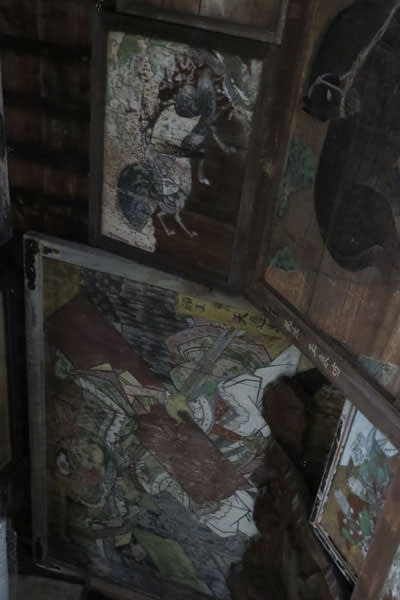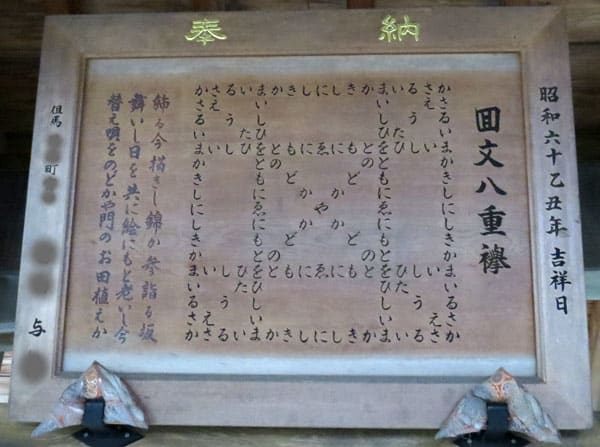『無縁・公界・楽』1 【縁切り寺、駆け込み寺】
網野 善彦 (日本中世の自由と平和 平凡社ライブラリー 1165)
以前にも読んだことがあるのか、あるいは、内容が重複しているのか、おさらい的な感じがする。
しかし、網野 善彦著の本は興味深いので、もう一度よみ始めている。
江戸時代の縁切り寺や若狭の駆け込み寺や周防ぐの無縁所まで読んでみたが、中には監視や今でいう監視役を兼ねた駆け込み寺があったことに驚いた。
関税免除の特権を認められた「無縁所」が全国でも何例か認められたらしい。
また寺によっては、借銭・借米の追求禁止。
無縁所を保護しつつ祈願することによって、戦国大名が無縁所の原理を閉じ込めようとした。
次は京の無縁所。
京とあっては、丁寧に楽しまねばなるまい^^
たまたま家人の本棚に無造作に置かれていた『無縁・公界・楽』だが、こういった内容は好きなので、時間を過ごす口実がまた一つ見つかったと喜んでいる。
公界(くがい)
① 公の場所。おおやけのこと。表向き。晴れの場。公的な用事。
「述懐は私事、弓矢の道は-の義/太平記 19」
② ひとなか。ひとまえ。世間。公衆。
「さやうの事を仰せられたらば、-で恥をかかせられう/狂言・花争」
③ 交際。ひとづきあい。
④ 「苦界くがい」に同じ。
⑤ 課役。