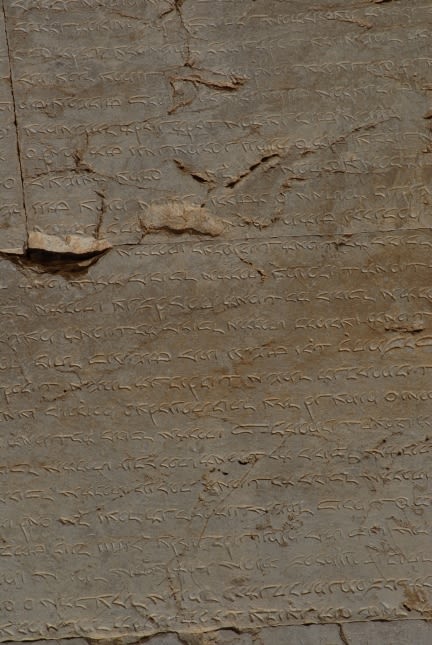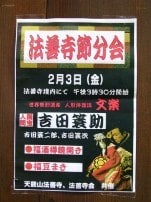(写真は法善寺横町のお食事処。格子戸に『初春大歌舞伎』のポスターが貼られていた。)
(記録だけ。今回は 夜の部三演目全てをまとめて記録しています。)
家族と、大阪松竹座壽 初春大歌舞伎 夜の部に行く。
演目は次の通り。
一、御所桜堀川夜討 弁慶上使
二、義経千本桜 吉野山
三、恋飛脚大和往来 玩辞楼十二曲の内 封印切
演目の感想の前に、一言述べたい。
今回出会わした、一部の 一階客に一言物申す。
とにかく うるさい。
もしかすれば、これもまた、イヤホンガイドの、不要な笑わせの因なるか・・・。
一度はイヤホンガイドたる物を借りてみて その実態を知り、イヤホンガイドにクレームを付けてみたいとも思うたが、観劇(時間と観劇代金)が無駄になるので、実行するには至らない。
よって今回の貧相な感性の客が、イヤホンガイドによるものか、あるいは、客自身の人間性や感受性によるものなのかは定かではない。
『弁慶上使』でのこと。
子が切られ、悲しい 切ない対面の山場で、歌舞伎を見に行っているにもかかわらず、仕草が現代風でないとて、なぜ笑うことが出来るのだろうか・・・。
『吉野山』の佐藤忠信実は源九郎狐の言い回しや仕草で笑うとは、何ぞや!
『封印切』の小判の封を切ったことを梅川が知らされた際、
「しぇ~~ぇえぇ~~。」
といいつつ、横たわる場面で、大笑いをするとは、品がない。
こういった目に余る 客の多さと回数に閉口。
己を知れ、そして、恥よ。
ここまで地に落ちた大人数の客と でくわせたのは初めてだっただけに、ショックは隠しきれない。
これも時代の流れというものか・・・。
何かにつけ、ことを探しては げらげらと大笑いの二、三十人の客。舞台の精神的進行を妨げるではない。
もうこれ以上はいいますまい。
辛口御免!!ネガティブ、御免!!

さてと、気を取り直して・・・。
今回の夜の部、大変わかりやすい演目ばかりを選ばれていた。
中でも興味深いのは『封印切』。
かなり台詞も変え、仕草や表情もはっきりと演じられていた。
なぜだろう・・・と裏を嗅ぐことは止めにしよう・・・。
一、御所桜堀川夜討(ごしょざくらほりかわようち)
弁慶上使(べんけいじょうし)
武蔵坊弁慶 橋之助
侍従太郎 彌十郎
腰元しのぶ/卿の君 新 悟
花の井 吉 弥
おわさ 扇 雀
『弁慶上使』も、何度見てもよい。
今回も泣いた。
弁慶がわが子を殺した後、夫婦袂合わせで我が子と知る・・・。
ここで琴線に触れる。
母親の、子をなくし、弁慶と再会といった複雑な心理の揺れを、上手く演じられるかどうかがこの演目の見どころ。
今回の新春歌舞伎昼の部でも感じたが、扇雀丈の実力がめっきりと上がり始めている。
橋之助丈の武蔵坊弁慶は男前。
花の井の吉弥丈は出しゃばらず役を演じておられる。
侍従太郎役の 彌十郎丈は見事な口調と声色で、演目全体を引き締めていたように感じる。
上手い。
二、義経千本桜(よしつねせんぼんざくら)
吉野山(よしのやま)
佐藤忠信実は源九郎狐 三津五郎
早見藤太 橋之助
静御前 藤十郎
藤十郎丈の静御前、品良し。今回も美しい。
佐藤忠信実は源九郎狐役の三津五郎丈、仕草や舞、決めポーズに見とれてしまう。
上のほう(三階)から、
「待ってました!」
の声が掛かると、水を得た魚のように、その見事さは加速をまして山場に達する。
素晴らしい。
橋之助丈の早見藤太は、ビックリするほどの男前。
眉をつなぎ、ダメ主人だが、もともと男前過ぎる橋の助丈、お顔においては、男前さが隠し切れない。
こんな早見藤太も、また楽し!
花道の、
「待て。待て。待て、待て、待て。」
や、
「申し、申し、旦那様、行きつ行かれつ、行かれては・・・・・・。」
の部分は馴染み深く、内心 口ずさんでわくわくしてしまう。
三、恋飛脚大和往来(こいびきゃくやまとおうらい)
玩辞楼十二曲の内 封印切(ふういんきり)
新町井筒屋の場
亀屋忠兵衛 翫 雀
丹波屋八右衛門 橋之助
井筒屋おえん 竹三郎
槌屋治右衛門 彌十郎
傾城梅川 扇 雀
今回の『封印切』は、
切れてしまった、切れてしまったが・・・どうしよう。ええい、切ってしまったんだ・・・。
といった心情の揺れ動きを、翫雀丈がわかり易く、オーバーな表情で、上手く演じておられた。
私は、役者や興行によって、解釈が違い、演じ方が違う封印を切る場を楽しみにしている。
『切れてしまった』或いは『切ってやった』の演じ方を、毎回楽しみにしている。
翫雀丈が花道から現れた時の、
「梶原源太は男でごじゃるてかなぁ~~。」
の台詞は、何度聞いても、格好が良く、胸のすく思い。
梶原源太は、梅ノ木を腰の後ろにさして戦いに挑んだという。
忠兵衛もこれから丹波屋の出むいて梅川と会い、相手の気持ちを知りたい・・・梅川の梅と、梶原源太の梅ノ木をかけて、いざ出陣、といったところであろう。(乱鳥解釈)
歌舞伎にはこういった遊び心が多く、楽しい。
竹三郎丈のおえんさんも引き締まった感じでよかった。
好きな秀太郎丈とはまた違ったおえんさんで、新鮮な感じがした。
上方歌舞伎は関西弁(大阪弁)が使えこなせるかどうかが、勝負所のひとつともいえる。
丹波屋八右衛門などは重要な役で、どちらかというと、関西で幼少時代をすごした役者の方が、演じやすいのかも知れない。
その点で言うと、仁左衛門丈や我当丈の方がやりやすいのかも知れない。
今回の橋之助丈は、勢い良く気持ちよく演じられていたことを付け加えておく。
今年の新春歌舞伎の『封印切』は上にも書いたように、随分言葉がかえてあった。
もともとわかりやすい演目だが、一層平たく変えてあったのは、ご時世というものか・・・。
歌舞伎も昔から行われていたように、時代に合わせ、試行錯誤を繰り返すこととなるのであろう。
大阪松竹座壽 初春大歌舞伎の夜の部も、好きな演目と役者さんがいっぱいで、楽しい時間をすごすことが出来た。
好きな演目と役者の多い私は、いつ歌舞伎を観ても、大概楽しむことができる、気楽な阿呆なのだ。