京都国立博物館の庭にて
山村流日本舞踊について
山村流日本舞踊を知らないことに引っかかり、確かめることにしたが、たいそう意味のある舞踊の流派だった。
『日本舞踊上方舞山村流公式配信 第百回 小唄『福寿三番叟』を拝見させていただくと、『三番叟』とあるが舟を漕ぐような踊りであった。
また、能楽にも近く、それでいて、歌舞伎のように形を作る。
さらに足の運びが特徴的で、滑らすような所作をされることにも興味を持った。
『高砂』はひたすら舟を漕ぐようにと習ったと云う方がいらっしゃったが、まさしく舟を漕ぐように舞うのは『福寿三番叟』か或いは山村流舞踊の特徴と言えるなのではないかと確信した。
『福寿三番叟』には、「宝船」と云う言葉が出てくる。
それを考えると、『高砂』にも関係するのかとも思われるが定かでない。
こう云う時に、国文に籍を置いておけば、ご存知の先生がいらっしゃるかもしれない。
ややこしい事柄になると、調べかたがわからない。
『日本古典文学大辞典』になら載っているのか。
能楽本で調べるのか、舞踊で調べるのか、こう言った場合、悪戦苦闘で時間を費やすわりには実りは薄い。
世の中には知らないことが多く、恥を書くこともしばしばあるが、多少の調べ物によって多少の知識が加わり、わからずともわかった気になるのはありがたい。誠、幸せな鳥である。
『二人椀久』なら馴染みがあるが『三面椀久』とはどんな舞踊なのだろうか。
椀久とは、日本大百科全書(ニッポニカ)では次のように解説されている。
歌舞伎(かぶき)、浄瑠璃(じょうるり)、音曲(おんぎょく)などの一題材。
大坂堺筋(さかいすじ)の商人椀屋久右衛門(きゅうえもん)が新町(しんまち)の遊女松山と契り、節分の豆撒(ま)きに金銀を撒き散らすほどの豪遊で、座敷牢(ろう)に入れられ、1677年(延宝5)精神に異常をきたして水死したという実話を、椀屋久兵衛の名で脚色。
流行小唄(こうた)や井原西鶴(さいかく) の小説『椀久一世の物語』にも扱われたが、歌舞伎では七回忌にちなんで1684年(貞享1)大坂で大和屋甚兵衛(やまとやじんべえ)が演じたのが最初という。
の小説『椀久一世の物語』にも扱われたが、歌舞伎では七回忌にちなんで1684年(貞享1)大坂で大和屋甚兵衛(やまとやじんべえ)が演じたのが最初という。
その後、紀海音(きのかいおん)作『椀久末松山(すえのまつやま)』など人形浄瑠璃にも脚色されたが、とくに舞踊、音曲には狂乱物の一系列として多く扱われた。
一中(いっちゅう)節『椀久道行』、長唄『其面影二人(そのおもかげににん)椀久』(1774年、9世市村羽左衛門(うざえもん)初演)、常磐津(ときわず)『狂乱廓三曲(みだれごころさとのてごと)(三つ面(みつめん)椀久)』(1839年、4世中村歌右衛門(うたえもん)初演)などが有名。
明治以後では、舞踊に初世市川右団次(うだんじ)が演じた『盟約誓十徳(にせかけてちかいのじっとく)』、6世尾上(おのえ)菊五郎初演の『幻(まぼろし)椀久』(岡村柿紅(しこう)作)など、戯曲に初世中村鴈治郎(がんじろう)が得意にした渡辺霞亭(かてい)作『椀久末松山』をはじめ、田村西男作『椀久』、真山青果(せいか)作『椀屋久兵衛』などがある。 [松井俊諭]
『三つ面椀久』 2017年にフェスティバルホールで、山村友五郎さんによる上方舞「三ツ面椀久」があったと云う。(歌舞伎美人:松竹株引用)
2017年4月28日(金)、大阪 フェスティバルホールで、第55回大阪国際フェスティバル2017「花舞台浪花賑(はなぶたいなにわのにぎわい)」
第55回大阪国際フェスティバル2017
花舞台浪花賑(はなぶたいなにわのにぎわい)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
上方舞「手打唄」梅の小袖(てうちうた うめのこそで)
京都 宮川町芸妓・舞妓
上方舞「三ツ面椀久」(みつめんわんきゅう)
椀久:山村友五郎
舞踊「宝塚、春爛漫」
瀬戸内美八 南風舞 ほか宝塚歌劇団OG
歌舞伎舞踊 楳茂都「三人連獅子」(うめもと さんにんれんじし)
父獅子:片岡愛之助
母獅子:中村壱太郎
子獅子:片岡千之助
山村流日本舞踊について
2世は1世の養子友三郎 (16~95) で,1世の没後2世友五郎を襲名して宗家格になり,劇場の振付師として活躍する一方,山村流の舞を整理完成し,今日の山村流を大成した。
1世の養女れんは,九郎右衛門町の山村「九山村」の1世家元を称し,京坂の劇場の振付師としても活躍したが,1881年に没し家元の後継者がない。
1世の養女登久は,島の内の山村「島山村」の1世家元となり,その孫若子は今日の女性本位の座敷舞としての地歌舞を完成し,1942年3月推されて3世宗家を継ぎ,2世山村舞扇斎吾斗を襲名。
このとき,その孫山村菊が2世若子を襲名したが,48年4月4世宗家を継ぎ,若と改称。
4世没後,92年孫の山村武が6世宗家を襲名,5世宗家はその母故山村糸に追贈された。
〘名〙 日本舞踊の流派の一つ。 文政(一八一八‐三〇)のころ、大坂の振付師山村友五郎が、地唄の名人在原検校と提携し、観世流の能を研究して創始したもの。
優婉閑雅を特色とし、劇場における振付のほか、花柳界や家庭にも進出した。
山村流日本舞踊
日本舞踊,上方舞の一流派。
流祖は1世山村友五郎 (1781~1844) 。
上方の歌舞伎役者藤川岩松の子で,1世山村友右衛門の門弟となり,師の初名友五郎を襲名したが,文化1 (04) 年6月師が没したので俳優をやめ振付師となった。
3世中村歌右衛門の専属的振付師となり,天保年間 (30~44) には上方一の振付師とされ,山村舞扇斎,舞扇斎吾斗と称した。
『三つ面椀久』などの歌舞伎舞踊のほか,地歌舞の大成者として山村流の基礎を確立。
上方(かみがた)舞の流派。
流祖は初世山村友五郎(ともごろう)(1781―1844)で、のち山村舞扇斎吾斗(ぶせんさいごと)と号した。
大坂に生まれ、歌舞伎(かぶき)俳優であったが、3世中村歌右衛門(うたえもん)に起用され、上方歌舞伎の振付師に転じた。
天保(てんぽう)期(1830~44)の名振付師として劇場舞台における優れた作品を生むと同時に、座敷舞としての山村の舞をつくりあげた。
おもな作品に『三つ面椀久(みつめんわんきゅう)』『江戸土産(えどみやげ)』 などがある。
などがある。
初世没後は養子の2世友五郎(1816―88)が「新町の山村」として活躍し、山村の舞を大成した。
また彼の義姉妹の二人(初世の養女)の山村れんは「九郎右衛門町の山村」、山村登久(とく)は「島の内の山村」とよばれ、ともにその舞を伝えた。
1949年(昭和24)に島の内系の山村若(わか)(1905―91)が4世宗家を名のった。
現在はその孫、若が6世宗家である。
現在、新町系の山村、また北山村、東山村などがある。
人間国宝の山村たかは新町系の出身であった。
〘名〙 日本舞踊の流派の一つ。
文政(一八一八‐三〇)のころ、大坂の振付師山村友五郎が、地唄の名人在原検校と提携し、観世流の能を研究して創始したもの。
優婉閑雅を特色とし、劇場における振付のほか、花柳界や家庭にも進出した。
※細雪(1943‐48)〈谷崎潤一郎〉中「観世水に四君子の花丸の模様のある山村流の扇をかざして」
悦子は学校から帰って来ると、毎年お花見の時より外にはめったに着ることのない和服を着て、足に合わない大ぶりの足袋を穿いて、観世水に四君子の花丸の模様のある山村流の扇をかざして
(https://furigana.info/w/四君子:しくんし)
四君子とは(ウィキペディアより)
四君子(しくんし)とは、蘭、竹、菊、梅の4種を、草木の中の君子として称えた言葉。
また、それらを全て使った図柄、模様。
本来、中国語で君子は徳と学識、礼儀を備えた人を指し、文人はみな君子になることを目指した。
蘭、竹、菊、梅の4種の植物がもつ特長が、まさに君子の特性と似ていることから、文人画の代表的な素材にもなった。
蘭はほのかな香りと気品を備え、竹は寒い冬にも葉を落とさず青々としている上、曲がらずまっすぐな性質を持っている。梅が早春の雪の中で最初に花を咲かせる強靱さ、菊が晩秋の寒さの中で鮮やかに咲く姿が好まれた。
それぞれの気品の高い美しさから、中国宋代より東洋画の画題としてよく用いられ、春は蘭、夏は竹、秋は菊、冬は梅と、四季を通じての題材となる。
また、これら4つの草木を描くにあたって基本的な筆遣いを全て学べるため、書を学ぶ場合の永字八法と同じように、画法を学ぶ重要な素材となっている。
麻雀牌の花牌として4枚1組で用いられることもある。中国麻雀では常用されるが、日本の麻雀ではほとんど用いられず、日本で発売される麻雀牌のセットからも省略されている。中国の麻雀牌をモチーフにしたゲーム『上海』では花牌として用いられている。
日本舞踊の流派の一。天保年間(1830~1844)に大坂の振付師山村友五郎が創始。女流の地唄舞に特色をもつ。
日本舞踊の上方舞の流派名。
天保年間(1830‐44)に大坂で名振付師として活躍した初世山村友五郎(ともごろう)(のちの初世舞扇斎吾斗(ぶせんさいごとう))を流祖とする。
初世は《慣(みなろうて)ちょっと七化》や《三つ面椀久》などを振り付け,地歌や能を舞にとり入れて上方舞を完成させた名手だが,その伝統は2世友五郎(新町に住んだので〈新町の山村〉とも),養女の山村れん(九郎右衛門町),同じく養女の山村登久(島の内)に継承され,明治の大阪芸界を風靡(ふうび)した。
世界大百科事典内の山村流の言及
…さらに新舞踊からも新流派はあり,藤蔭流,五条流,林きむ子(1886‐1967)の林流,
西崎緑の西崎流がある。上方舞では篠塚文三郎(?‐1845)を祖とする篠塚流,
井上八千代の井上流,山村友五郎による山村流,
楳茂都(うめもと)扇性の楳茂都流,吉村ふじ(?‐1909)の吉村流等がある。
歌舞伎舞踊【菊池 明】。
井上八千代の井上流は、井上さん^^v
楳茂都(うめもと)扇性の楳茂都流は、確か、片岡愛之助さんか、、、
楳茂都流は確か、大阪歴博で掛け軸か何かを見たような気がする。
2世は1世の養子友三郎 (16~95) で,1世の没後2世友五郎を襲名して宗家格になり,劇場の振付師として活躍する一方,山村流の舞を整理完成し,今日の山村流を大成した。
1世の養女れんは,九郎右衛門町の山村「九山村」の1世家元を称し,京坂の劇場の振付師としても活躍したが,1881年に没し家元の後継者がない。
1世の養女登久は,島の内の山村「島山村」の1世家元となり,その孫若子は今日の女性本位の座敷舞としての地歌舞を完成し,1942年3月推されて3世宗家を継ぎ,2世山村舞扇斎吾斗を襲名。
このとき,その孫山村菊が2世若子を襲名したが,48年4月4世宗家を継ぎ,若と改称。
4世没後,92年孫の山村武が6世宗家を襲名,5世宗家はその母故山村糸に追贈された。
〘名〙 日本舞踊の流派の一つ。 文政(一八一八‐三〇)のころ、大坂の振付師山村友五郎が、地唄の名人在原検校と提携し、観世流の能を研究して創始したもの。
優婉閑雅を特色とし、劇場における振付のほか、花柳界や家庭にも進出した。
後水尾天皇の第一皇女、文智内親王により営まれたのが始まり。
華道山村御流は明治の後期第6代門跡伏見宮文秀内親王によって基礎が築かれた後、第十代山本静山門跡が山村御流初代家元となりました。
とりとめもない記録にお付き合いくださいまして誠にありがとうございます。
みなさま、楽しいお時間をお過ごしください。

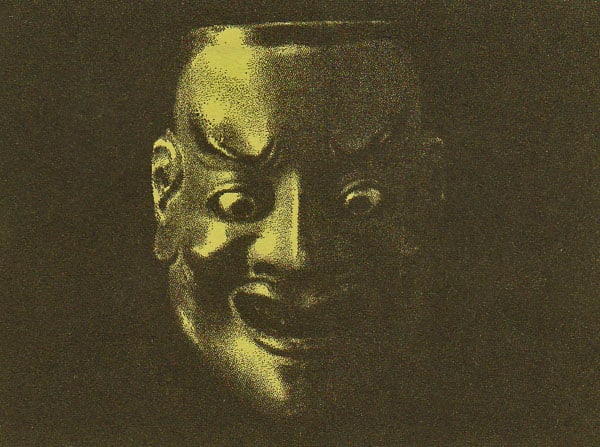

































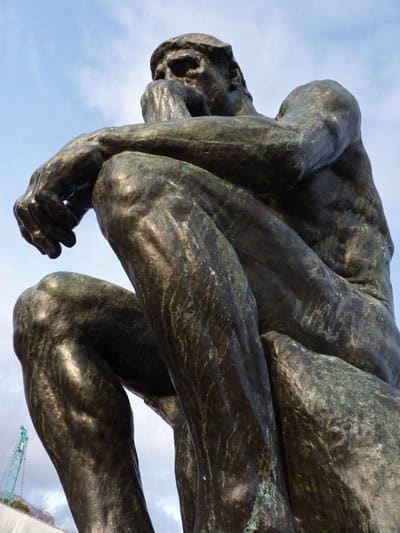
 の小説『椀久一世の物語』にも扱われたが、歌舞伎では七回忌にちなんで1684年(貞享1)大坂で大和屋甚兵衛(やまとやじんべえ)が演じたのが最初という。
の小説『椀久一世の物語』にも扱われたが、歌舞伎では七回忌にちなんで1684年(貞享1)大坂で大和屋甚兵衛(やまとやじんべえ)が演じたのが最初という。

















